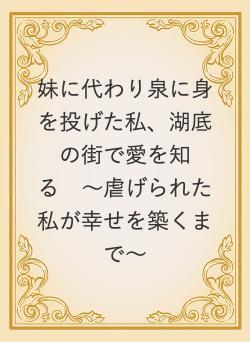「坊ちゃん、本日もお疲れ様でした」
執務を終えたレオネルの元に現れたのは、執事のヘンリーだ。彼は数日に一度、レオネルの執務室で屋敷内の様子を話し合っていた。
二人きりの時だけレオネルの事を『坊ちゃん』と呼ぶ。最初は止めて欲しいと告げたレオネルだったが、毎日ニコニコと笑って話す彼に根負けしてこの呼び方で定着している。
「ああ、ヘンリー。ここ数日色々と助かった」
まさか婚約者であるブレンダ――もといエスペランサが国境の関所に一人で置いていかれるとは思わなかった。王国での彼女の扱いが、朧げながらではあるが想像がつく。
そもそも本当にブレンダを帝国に送るのであれば、花嫁一人で来させるなどあり得ない。諜報員たちの情報によれば、特にホイートストン公爵家のブレンダは、鳥よ花よと育てられた娘だと聞いている。
手塩をかけて育てた娘を単身で送るなどするだろうか。
関所を抜けた際、衛兵からそのような話を聞き疑問に思ったものだ。それが正しかった事はすぐに判明したが。
彼女の事を考えていたレオネルにヘンリーが声をかけた。
「まさか坊ちゃんが開口一番に『君はブレンダ嬢なのか?』と訊ねるとは思いませんでした。普段の坊ちゃんであれば、あのような事はしないと思うのですが……何かありましたか?」
ヘンリーは普段と変わらない笑みをたたえながら、レオネルに話しかける。けれども、長い付き合いである彼には分かる。エスペランサと対面した時、レオネルの些細な変化に彼は気づいているという事に。
「よろしいのですよ、坊ちゃん。ここには私しかおりませんから」
やはりヘンリーは分かっていたのだ。レオネルは大きなため息をひとつついた後、頭を抱える。そんな主人の珍しい行動に、ヘンリーは「おやっ?」と瞬きを忘れたように見つめた。
「……ったんだ」
レオネルの声は小さく、距離を取っていたヘンリーの耳には届かない。
「申し訳ございません。老体ですのでもう少し大きな声で――」
「エスペランサ嬢が可愛かったんだ!」
執務を終えたレオネルの元に現れたのは、執事のヘンリーだ。彼は数日に一度、レオネルの執務室で屋敷内の様子を話し合っていた。
二人きりの時だけレオネルの事を『坊ちゃん』と呼ぶ。最初は止めて欲しいと告げたレオネルだったが、毎日ニコニコと笑って話す彼に根負けしてこの呼び方で定着している。
「ああ、ヘンリー。ここ数日色々と助かった」
まさか婚約者であるブレンダ――もといエスペランサが国境の関所に一人で置いていかれるとは思わなかった。王国での彼女の扱いが、朧げながらではあるが想像がつく。
そもそも本当にブレンダを帝国に送るのであれば、花嫁一人で来させるなどあり得ない。諜報員たちの情報によれば、特にホイートストン公爵家のブレンダは、鳥よ花よと育てられた娘だと聞いている。
手塩をかけて育てた娘を単身で送るなどするだろうか。
関所を抜けた際、衛兵からそのような話を聞き疑問に思ったものだ。それが正しかった事はすぐに判明したが。
彼女の事を考えていたレオネルにヘンリーが声をかけた。
「まさか坊ちゃんが開口一番に『君はブレンダ嬢なのか?』と訊ねるとは思いませんでした。普段の坊ちゃんであれば、あのような事はしないと思うのですが……何かありましたか?」
ヘンリーは普段と変わらない笑みをたたえながら、レオネルに話しかける。けれども、長い付き合いである彼には分かる。エスペランサと対面した時、レオネルの些細な変化に彼は気づいているという事に。
「よろしいのですよ、坊ちゃん。ここには私しかおりませんから」
やはりヘンリーは分かっていたのだ。レオネルは大きなため息をひとつついた後、頭を抱える。そんな主人の珍しい行動に、ヘンリーは「おやっ?」と瞬きを忘れたように見つめた。
「……ったんだ」
レオネルの声は小さく、距離を取っていたヘンリーの耳には届かない。
「申し訳ございません。老体ですのでもう少し大きな声で――」
「エスペランサ嬢が可愛かったんだ!」