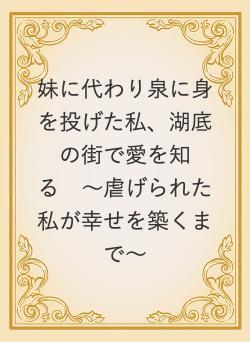「なるほどな」
私の話を聞いた公爵様は考え込む。彼に相談したのは、朝の事についてだ。
私はどうしても日の出と共に目が覚めてしまう体質だった。けれども、夜遅くまで働いているリーナたちをそんな早くから私に付き合わせたいと思っていない。だから、リーナたちも他の使用人と同じくらいの時間から、私の世話を始めるようにしてほしいと考えていた。
私はまだ婚約者の立場。侍女の仕事を勝手に変える事などできないのだ。
「私としては朝、読書に集中する時間ができるので有難いな、と思いまして」
「まあ、君が良いというならそれでも構わない」
思った以上にすんなりと許可を出した公爵様に驚いたのは、リーナだったようだ。
「旦那様、本当によろしいのですか?」
「ああ、屋敷内の事だからな。エスペランサ嬢が問題ないと言うのなら、それで良い。ただ、来訪者が泊まりで来る場合などもある。その時はマルセナの指示に従ってほしい」
「承知いたしました」
有難い事に許可を得る事ができたので、明日からは通常の時間に顔を出してもらえば良い。二人に苦労をかけなくて良かったと胸を撫で下ろした。
しばらく雑談をした私たち。そろそろお邪魔かと思い、訓練場を後にしようと考えていたが、公爵様の後ろからルノーが現れた。
彼は私を見て、二度瞬きをしてから手で目を擦る。
「おや、初めて見るお嬢さんですな?」
「……エスペランサ・ホイートストンと申します。この度公爵様の婚約者としてこちらに参りました」
ルノーに礼を執ると、彼は再度目を見開いて私を見た。そして今まで武人の顔つきだった彼の表情が、私の言葉で一瞬にして穏やかな顔つきに変わる。
「やはり魔導皇女様の……いやはや、魔導皇女様によく似ていらっしゃる」
「母の事をご存知なのですか?」
母が亡くなってから乳母も追い出されてしまったため、母の幼少の頃の事を聞く機会がなかったのだ。記憶にある母は、私を抱きしめてくれて「大丈夫よ」と声を掛けて微笑んでくれた。優しかった母。
ルノーは昔話を懐かしく感じているのか、目を細めて遠くを見ながら話し始めた
「儂は昔、公爵様のように帝都の騎士として働いてましてね。まあ、しがない子爵家の三男坊だったので、儂は騎士として身を立てていたわけです。儂は騎士としての才能があったらしくてですねぇ、一時期バレンティナ様の護衛を勤めさせていただいたのですよ」
母が十一歳くらいの話らしい。
「あの時の皇女様はそれはそれはお転婆で……あの時から魔法や魔術に傾倒されていましたよ。いつも魔法や魔術を色々と試しては、失敗されていましたね。それでも『楽しい』と笑っているお方でした」
私の頭の中の母とは似ても似つかない。けれども、なんとなく想像ができるような気がした。確かに母はいつも微笑んでいた。けれども、たまに舌をぺろっと出したり、片目をつぶったり……お茶目なところもあったように思う。
「帝国へと嫁がれる、とお聞きした時は驚いたものです。ですが、こんな可愛らしいお嬢様を残されたのですね」
ルノーは母を思い出して感極まったのか、私の手を取ろうとした――その時。
「ルノー様、淑女の手に易々と触れてはなりません」
私の前に颯爽と現れたのは、マルセナだった。
私の話を聞いた公爵様は考え込む。彼に相談したのは、朝の事についてだ。
私はどうしても日の出と共に目が覚めてしまう体質だった。けれども、夜遅くまで働いているリーナたちをそんな早くから私に付き合わせたいと思っていない。だから、リーナたちも他の使用人と同じくらいの時間から、私の世話を始めるようにしてほしいと考えていた。
私はまだ婚約者の立場。侍女の仕事を勝手に変える事などできないのだ。
「私としては朝、読書に集中する時間ができるので有難いな、と思いまして」
「まあ、君が良いというならそれでも構わない」
思った以上にすんなりと許可を出した公爵様に驚いたのは、リーナだったようだ。
「旦那様、本当によろしいのですか?」
「ああ、屋敷内の事だからな。エスペランサ嬢が問題ないと言うのなら、それで良い。ただ、来訪者が泊まりで来る場合などもある。その時はマルセナの指示に従ってほしい」
「承知いたしました」
有難い事に許可を得る事ができたので、明日からは通常の時間に顔を出してもらえば良い。二人に苦労をかけなくて良かったと胸を撫で下ろした。
しばらく雑談をした私たち。そろそろお邪魔かと思い、訓練場を後にしようと考えていたが、公爵様の後ろからルノーが現れた。
彼は私を見て、二度瞬きをしてから手で目を擦る。
「おや、初めて見るお嬢さんですな?」
「……エスペランサ・ホイートストンと申します。この度公爵様の婚約者としてこちらに参りました」
ルノーに礼を執ると、彼は再度目を見開いて私を見た。そして今まで武人の顔つきだった彼の表情が、私の言葉で一瞬にして穏やかな顔つきに変わる。
「やはり魔導皇女様の……いやはや、魔導皇女様によく似ていらっしゃる」
「母の事をご存知なのですか?」
母が亡くなってから乳母も追い出されてしまったため、母の幼少の頃の事を聞く機会がなかったのだ。記憶にある母は、私を抱きしめてくれて「大丈夫よ」と声を掛けて微笑んでくれた。優しかった母。
ルノーは昔話を懐かしく感じているのか、目を細めて遠くを見ながら話し始めた
「儂は昔、公爵様のように帝都の騎士として働いてましてね。まあ、しがない子爵家の三男坊だったので、儂は騎士として身を立てていたわけです。儂は騎士としての才能があったらしくてですねぇ、一時期バレンティナ様の護衛を勤めさせていただいたのですよ」
母が十一歳くらいの話らしい。
「あの時の皇女様はそれはそれはお転婆で……あの時から魔法や魔術に傾倒されていましたよ。いつも魔法や魔術を色々と試しては、失敗されていましたね。それでも『楽しい』と笑っているお方でした」
私の頭の中の母とは似ても似つかない。けれども、なんとなく想像ができるような気がした。確かに母はいつも微笑んでいた。けれども、たまに舌をぺろっと出したり、片目をつぶったり……お茶目なところもあったように思う。
「帝国へと嫁がれる、とお聞きした時は驚いたものです。ですが、こんな可愛らしいお嬢様を残されたのですね」
ルノーは母を思い出して感極まったのか、私の手を取ろうとした――その時。
「ルノー様、淑女の手に易々と触れてはなりません」
私の前に颯爽と現れたのは、マルセナだった。