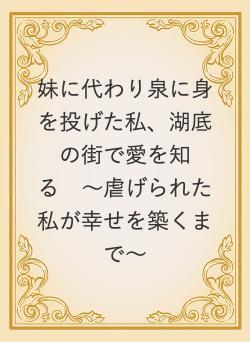嵐が過ぎ去った後、公爵様は仕事を終わらせるために執務室へと戻っていく。ヘンリーもその後退出し、私は一人のんびりと過ごしていた。
カップの紅茶もそろそろ空になるだろうか、という頃。扉から入ってきたのはヘンリーだった。後ろから侍女の服を着た女性が二人入ってくる。
先頭の女性は澄ました表情を崩す事はない。
礼儀作法を極めている女性らしく、無駄がなく美しい動作で礼を執っている。私も王国では背が高い方に分類されていたが、彼女はそんな私よりも身長がありそうだ。眼鏡と髪をひとつに後ろでまとめており、凛とした立ち姿は王国の教育係を思い出した。
一方で後ろの女性は緊張しているためか、顔が強張っていた。
先頭の女性は華やかな美人なら、後ろの女性は可愛らしい可憐な女の子という感じだろうか。髪を三つ編みにし、上目遣いでこちらを窺う様子はまるで小動物のようだ。
私が血統主義である王国から来た、という事で少し警戒しているのだ。
まあ、その態度を咎めるつもりはない。もし、この場に本物のブレンダが来ていたとしたら、彼女たちは罵詈雑言を聞かされていただろうから。
ヘンリーは二人に言葉をかける。
「こちらにいらっしゃるお方が、公爵様の婚約者であらせられるブレンダ様――いえ、エスペランサ様でございます」
ヘンリーは包み隠さず私の身分を話す事にしたようだ。
大人びた女性は私の姿を見て予想していたのか、少しだけ目を細めただけだった。一方で可愛らしい女の子の方は、驚きを隠せなかったのか顔にありありと現れている。
女の子の表情に気がついた女性は、左手で彼女の腰辺りをポンと軽く叩く。その衝撃で女の子は我に返ったらしい。半開きになっていた口を慌てて引き締める。
「エスペランサ様の専属侍女として仕えますマルセナとリーナです。何かあれば二人に申し付けください」
マルセナは完璧な礼を執って頭を下げる。リーナはそんな彼女を見てあたふたと礼をした。対照的な二人ね、なんて思いながら私は二人に声を掛けた。
「私はエスペランサ・ホイートストン。よろしく頼むわね」
「こちららこそ、お仕えできて光栄です」
「あ……私も、お仕えできる事、楽しみにしておりましたっ……!」
冷静沈着なマルセナ、少しドジっ子気質のリーナ。
まさか自分専用の侍女が付くとは思わなかった。ありがたい事だと、心の中で公爵様に感謝を述べた。
カップの紅茶もそろそろ空になるだろうか、という頃。扉から入ってきたのはヘンリーだった。後ろから侍女の服を着た女性が二人入ってくる。
先頭の女性は澄ました表情を崩す事はない。
礼儀作法を極めている女性らしく、無駄がなく美しい動作で礼を執っている。私も王国では背が高い方に分類されていたが、彼女はそんな私よりも身長がありそうだ。眼鏡と髪をひとつに後ろでまとめており、凛とした立ち姿は王国の教育係を思い出した。
一方で後ろの女性は緊張しているためか、顔が強張っていた。
先頭の女性は華やかな美人なら、後ろの女性は可愛らしい可憐な女の子という感じだろうか。髪を三つ編みにし、上目遣いでこちらを窺う様子はまるで小動物のようだ。
私が血統主義である王国から来た、という事で少し警戒しているのだ。
まあ、その態度を咎めるつもりはない。もし、この場に本物のブレンダが来ていたとしたら、彼女たちは罵詈雑言を聞かされていただろうから。
ヘンリーは二人に言葉をかける。
「こちらにいらっしゃるお方が、公爵様の婚約者であらせられるブレンダ様――いえ、エスペランサ様でございます」
ヘンリーは包み隠さず私の身分を話す事にしたようだ。
大人びた女性は私の姿を見て予想していたのか、少しだけ目を細めただけだった。一方で可愛らしい女の子の方は、驚きを隠せなかったのか顔にありありと現れている。
女の子の表情に気がついた女性は、左手で彼女の腰辺りをポンと軽く叩く。その衝撃で女の子は我に返ったらしい。半開きになっていた口を慌てて引き締める。
「エスペランサ様の専属侍女として仕えますマルセナとリーナです。何かあれば二人に申し付けください」
マルセナは完璧な礼を執って頭を下げる。リーナはそんな彼女を見てあたふたと礼をした。対照的な二人ね、なんて思いながら私は二人に声を掛けた。
「私はエスペランサ・ホイートストン。よろしく頼むわね」
「こちららこそ、お仕えできて光栄です」
「あ……私も、お仕えできる事、楽しみにしておりましたっ……!」
冷静沈着なマルセナ、少しドジっ子気質のリーナ。
まさか自分専用の侍女が付くとは思わなかった。ありがたい事だと、心の中で公爵様に感謝を述べた。