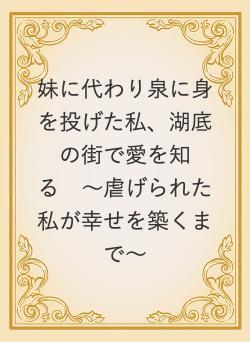段々と顔から血の気が引いていく。目の前の景色が歪んだ瞬間、私の両肩に大きな手が置かれた。
「エスペランサ嬢、大丈夫か? ヘンリー、何か飲み物を」
「おや……顔色が悪いですねぇ……」
ヘンリーが私に紅茶を淹れてくれる。私は震える手でそれを取ろうとしたが、その前に公爵様が私の手を取った。
――温かい。
彼の手の温もりは、生前の母を彷彿とさせる。人の温もりを感じたのは、母が亡くなって以来だ。
「ここには君を貶める者はいない。安心してくれ」
彼の力強い言葉に、私は涙があふれそうになる。
涙を堪えていた私に、のんびりとした声がかけられた。セヴァルだ。
「そうですよぉ〜。お嬢様の魔力は非常に興味深いですからねぇ〜……あ、むしろ私と魔法研究でもしてみますぅ? とっても楽しいですよ!」
揉み手をしながら話すセヴァルに、ヘンリーが突っ込む。
「セヴァル、あなたは一旦口を閉じましょうか?」
「えー、ヘンリーさんまでぇ? 分かりましたよ」
セヴァルとヘンリーの微笑ましいやり取りを見て、私は思わず笑ってしまう。笑うのも久しぶりだ。
笑いが止まらない私を見て、最初目を丸くしていた三人だったが、私に釣られたのか彼らも笑い始めたのだった。
「エスペランサ嬢、大丈夫か? ヘンリー、何か飲み物を」
「おや……顔色が悪いですねぇ……」
ヘンリーが私に紅茶を淹れてくれる。私は震える手でそれを取ろうとしたが、その前に公爵様が私の手を取った。
――温かい。
彼の手の温もりは、生前の母を彷彿とさせる。人の温もりを感じたのは、母が亡くなって以来だ。
「ここには君を貶める者はいない。安心してくれ」
彼の力強い言葉に、私は涙があふれそうになる。
涙を堪えていた私に、のんびりとした声がかけられた。セヴァルだ。
「そうですよぉ〜。お嬢様の魔力は非常に興味深いですからねぇ〜……あ、むしろ私と魔法研究でもしてみますぅ? とっても楽しいですよ!」
揉み手をしながら話すセヴァルに、ヘンリーが突っ込む。
「セヴァル、あなたは一旦口を閉じましょうか?」
「えー、ヘンリーさんまでぇ? 分かりましたよ」
セヴァルとヘンリーの微笑ましいやり取りを見て、私は思わず笑ってしまう。笑うのも久しぶりだ。
笑いが止まらない私を見て、最初目を丸くしていた三人だったが、私に釣られたのか彼らも笑い始めたのだった。