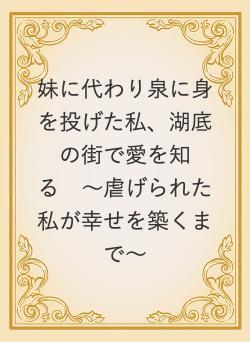「まずこちらのクマに掛けられている禁術から説明しましょう。『声封じの魔法』……これは、名前の通り声を封じる魔法ですねぇ。ちなみにもうひとつの『名封じの魔法』と言うのは、自分の名前が言えなくなるという魔法なのですが……まさか他人の名前を言わせる効果もあるとは思いませんでしたねぇ!」
セヴァルは私を一瞥する。
「ええ。私は『ブレンダ』として嫁ぐよう国王陛下より指示されましたので」
公爵様は眉間に皺を寄せ、セヴァルは肩をすくめる。
「本当に王国は姑息な真似をいたしますねぇ……いや、失礼」
「私に気を遣わなくても良いですわ。私もセヴァルと同じように思っていますので」
そう告げれば、セヴァルは興味深そうに私を見つめていたが、すぐに貼り付けたような笑みを浮かべた。
「おや、それであればこのままで進めます。次にこちらのバレンティナ様が作成された宝石に関してですが、『姿変えの魔術』『顕呪の魔術』『封魔の魔術』が込められていたようですねぇ――」
「『姿変えの魔術』は、目の色と髪の色を変える魔術で、『顕呪の魔術』は掛けられた魔法を顕著させる魔術だろう?」
公爵様の言葉に彼はわざとらしくため息をつく。
「おや、公爵様。私の仕事が無くなってしまうではありませんか。ですが、仰る通りです。顕呪の魔術によって、浮かび上がった魔法をこのクマへと封印した所でしょうか。お嬢様に掛かっている魔法はもう残っていなさそうですねぇ。それよりも……禁術は解除してしまうと、術者に跳ね返る場合があるんですよ。解除せず、クマへと封印したのは、正解だったかと思われますねぇ」
ずっと隠し持っていた母から渡された絵本。その中に、人形へと自分に掛けられた魔法を移すという話があったのだ。もしかしたら、私もできるのでは……と馬車内で考えて、真似てみたのだけれど。まさか本当にできるとは思わなかったわ。
頭の中で考えをめぐらせていると、公爵様が口を開く。
「ふむ、クマが役に立って良かった。それよりも、『封魔の魔術』についてを教えてくれるか?」
そう言われて、セヴァルはわざとらしく眉間に皺を寄せた。
「公爵様、先を急がせますねぇ。『封魔の魔術』とは、魔力を封印する術です。お嬢様は……そうですねぇ。正確に測定しないと分かりませんが、バレンティナ様に匹敵する魔力量の持ち主かと思われます。羨ましいですねぇ!」
「私の魔力はそんなにあるのですか……?」
彼の言葉に私は目を見開いた。
もし魔力が封印されていなかったら、私の扱いはどうなっていただろうか……考えて私は身震いした。元婚約者の卑劣さを感じさせる笑いを思い出したからだ。
彼らはいつぞや、こんな話をしていたのだ。
『あ〜あ、あの女の魔力量が多ければ、魔獣退治の最前線に送り込んで……それで勝手に死んでくれれば事は簡単に済むんだがな。帝国には『名誉の死』という事で報告して、私は好きに婚約者を決められるのに。本当に使えないやつだな』
『仕方ないっすよ。その女は結局穢れた血を持つんですから』
『我々のような高貴な血を持つ者に魔力が敵うわけありませんよ』
嘲笑う彼と側近たちの言葉を思い出し、胸に刺さる。魔力がある事を知られていたら、きっと彼らの言う通りに私は死んでいた可能性もあったのだから。
セヴァルは私を一瞥する。
「ええ。私は『ブレンダ』として嫁ぐよう国王陛下より指示されましたので」
公爵様は眉間に皺を寄せ、セヴァルは肩をすくめる。
「本当に王国は姑息な真似をいたしますねぇ……いや、失礼」
「私に気を遣わなくても良いですわ。私もセヴァルと同じように思っていますので」
そう告げれば、セヴァルは興味深そうに私を見つめていたが、すぐに貼り付けたような笑みを浮かべた。
「おや、それであればこのままで進めます。次にこちらのバレンティナ様が作成された宝石に関してですが、『姿変えの魔術』『顕呪の魔術』『封魔の魔術』が込められていたようですねぇ――」
「『姿変えの魔術』は、目の色と髪の色を変える魔術で、『顕呪の魔術』は掛けられた魔法を顕著させる魔術だろう?」
公爵様の言葉に彼はわざとらしくため息をつく。
「おや、公爵様。私の仕事が無くなってしまうではありませんか。ですが、仰る通りです。顕呪の魔術によって、浮かび上がった魔法をこのクマへと封印した所でしょうか。お嬢様に掛かっている魔法はもう残っていなさそうですねぇ。それよりも……禁術は解除してしまうと、術者に跳ね返る場合があるんですよ。解除せず、クマへと封印したのは、正解だったかと思われますねぇ」
ずっと隠し持っていた母から渡された絵本。その中に、人形へと自分に掛けられた魔法を移すという話があったのだ。もしかしたら、私もできるのでは……と馬車内で考えて、真似てみたのだけれど。まさか本当にできるとは思わなかったわ。
頭の中で考えをめぐらせていると、公爵様が口を開く。
「ふむ、クマが役に立って良かった。それよりも、『封魔の魔術』についてを教えてくれるか?」
そう言われて、セヴァルはわざとらしく眉間に皺を寄せた。
「公爵様、先を急がせますねぇ。『封魔の魔術』とは、魔力を封印する術です。お嬢様は……そうですねぇ。正確に測定しないと分かりませんが、バレンティナ様に匹敵する魔力量の持ち主かと思われます。羨ましいですねぇ!」
「私の魔力はそんなにあるのですか……?」
彼の言葉に私は目を見開いた。
もし魔力が封印されていなかったら、私の扱いはどうなっていただろうか……考えて私は身震いした。元婚約者の卑劣さを感じさせる笑いを思い出したからだ。
彼らはいつぞや、こんな話をしていたのだ。
『あ〜あ、あの女の魔力量が多ければ、魔獣退治の最前線に送り込んで……それで勝手に死んでくれれば事は簡単に済むんだがな。帝国には『名誉の死』という事で報告して、私は好きに婚約者を決められるのに。本当に使えないやつだな』
『仕方ないっすよ。その女は結局穢れた血を持つんですから』
『我々のような高貴な血を持つ者に魔力が敵うわけありませんよ』
嘲笑う彼と側近たちの言葉を思い出し、胸に刺さる。魔力がある事を知られていたら、きっと彼らの言う通りに私は死んでいた可能性もあったのだから。