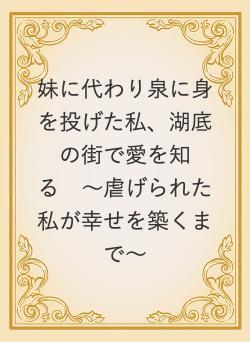「終わったの……か……?」
公爵様が声を出した事で、ヘンリーも我に返ったらしい。二人は同時に私へと視線を送ってきた。きっと二人のことだ。私が呪いから解放されたのかどうか、を気にかけてくれているのだろう。
うん、喉が軽い。
声を出そうとして、変な突っかかりもない。
問題なく、呪いをクマに移せたのではないかしら。そう安堵したのと同時に、私の手の中にあった母の形見の宝石がパリン、と音を立てて割れた。まるで役目を果たしたかのように……。
私は割れた宝石をじっと見つめていた。
そう言えば、何故お母様はこの首飾りを渡したのかしら。
『絶対、取られてはだめよ? その時が来たら使いなさい』
お母様に物心ついた頃からそう言われ続けていたの。
無邪気だった私は尋ねたわ。『その時ってどんな時なの?』って。
『その時が来れば……分かるわ』って言っていたけれど、まさか本当にその時が来るとは思わなかったもの。
まさか、お母様はこの事を知っていた……?
でも、そんな事一言も言っていなかった気がするのだけれど……。
考えてみたけれども、堂々巡りになるだけだ。
むしろここは帝国でお母様の母国。ここでお母様の事について訊ねれば、分かるかもしれない。
そう思って私は公爵様とヘンリーに顔を向けたのだけれど……。
二人は私をじっと見つめている。ヘンリーは口を半開きにしたまま、まばたきすら忘れているようだ。
公爵様の視線は、信じられないものを見ているかように私の髪を追っている。
どうしたのかしら……と首を傾げると、自身の髪の毛が視界に入ってくる。その髪色は見慣れていたホイートストン公爵と同じブロンド……ではなかった。
母と同じ夜空を編んだような黒色――。
私は慌てて暖炉の上に飾られた鏡で自分の姿を確認する。
するとそこには、見惚れるほどの艶やかな黒色の髪を靡かせている少女。
深い夜の帳を閉じ込めたような美しさ――その色は私の母の髪と同じだった。
公爵様が声を出した事で、ヘンリーも我に返ったらしい。二人は同時に私へと視線を送ってきた。きっと二人のことだ。私が呪いから解放されたのかどうか、を気にかけてくれているのだろう。
うん、喉が軽い。
声を出そうとして、変な突っかかりもない。
問題なく、呪いをクマに移せたのではないかしら。そう安堵したのと同時に、私の手の中にあった母の形見の宝石がパリン、と音を立てて割れた。まるで役目を果たしたかのように……。
私は割れた宝石をじっと見つめていた。
そう言えば、何故お母様はこの首飾りを渡したのかしら。
『絶対、取られてはだめよ? その時が来たら使いなさい』
お母様に物心ついた頃からそう言われ続けていたの。
無邪気だった私は尋ねたわ。『その時ってどんな時なの?』って。
『その時が来れば……分かるわ』って言っていたけれど、まさか本当にその時が来るとは思わなかったもの。
まさか、お母様はこの事を知っていた……?
でも、そんな事一言も言っていなかった気がするのだけれど……。
考えてみたけれども、堂々巡りになるだけだ。
むしろここは帝国でお母様の母国。ここでお母様の事について訊ねれば、分かるかもしれない。
そう思って私は公爵様とヘンリーに顔を向けたのだけれど……。
二人は私をじっと見つめている。ヘンリーは口を半開きにしたまま、まばたきすら忘れているようだ。
公爵様の視線は、信じられないものを見ているかように私の髪を追っている。
どうしたのかしら……と首を傾げると、自身の髪の毛が視界に入ってくる。その髪色は見慣れていたホイートストン公爵と同じブロンド……ではなかった。
母と同じ夜空を編んだような黒色――。
私は慌てて暖炉の上に飾られた鏡で自分の姿を確認する。
するとそこには、見惚れるほどの艶やかな黒色の髪を靡かせている少女。
深い夜の帳を閉じ込めたような美しさ――その色は私の母の髪と同じだった。