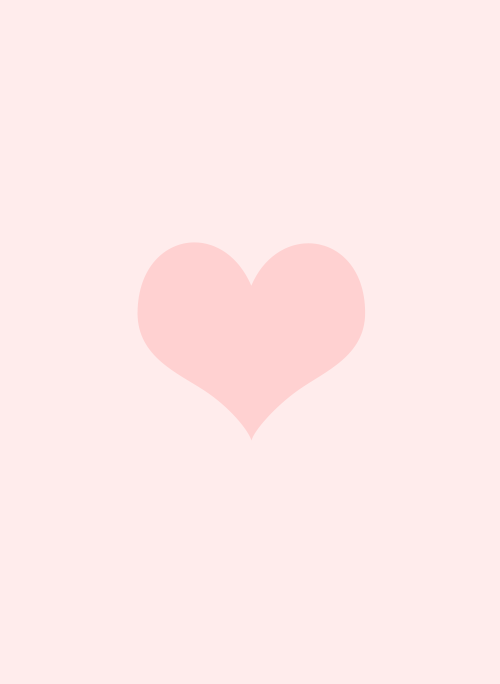「優、ちゃん……?」
イザベラの口から発せられたのは、聞き間違えるはずもない。日本の女子高生だった頃、大親友でいつも行動を共にしていた相羽優子の名前だった。
思い返してみれば、なんだかイザベラの言動はやけに優子に似ていた気がする。気の強いところも、正義感が強いところも。そんなに似ていたのに、何故気付けなかったのか。もっと早く気付いていれば、何かできたかもしれないのに。それが悔やまれてならない。
「そうだよ、穂香」
こうして改めて見てみると、イザベラの笑い方は優子によく似ていた。勝ち気だが人情味のある温かい笑み。
「私、ごめん……なんで、今まで気づかなかったんだろう」
「ずっとイザベラらしく振舞う癖がついていたし、元々の性格が似ていたみたいだからね。私、上手にイザベラやれてたでしょ?」
「ええ、本当に。今まで私達と同じ転生者だったなんて全く気付きませんでしたよ」
ため息をつきながら上野さんは笑った。私も息を整えて、久しぶりの親友と色々話をしたくなった。
「優ちゃん、なんでそんなに真面目にイザベラのふりを?」
「だって、イザベラは別に不幸な運命を辿らないもの。だったらシナリオ通りに進んでもらった方が、ファンとしては楽しいじゃない? それにね、あんな風に死んだ直後だったから、取り乱していた私を家族は優しく接してくれたの。その恩に報いたかっただけよ」
過去を懐かしむように遠くを見ながら優子が話す。軽く話しているが、絶対に聞き逃してはいけない言葉が気になった。
「……死んだって、どういうこと?」
「「え?」」
私の言葉に驚いたのは、優子と上野さんだった。驚く私をよそに、二人は顔を見合わせる。
「えっと、上野……さん? 貴方は」
「病死でした。最期は病院のベッドの上です」
「私は事件に巻き込まれて……そっか、穂香は覚えてないんだ」
二人はとんとん拍子に会話を進めるが、私には何のことだか分からない。目を白黒させていると、少し考えた優子が私の方を向いた。
「うん……覚えてないなら、それでいいよ。そんな記憶、なくてもいい」
「それには全面的に賛成です」
なんだか勝手に二人の間で話が終わってしまったみたいだ。完全に私は置いてけぼり状態だ。
「え? やっぱりここって死後の世界なの? 私は気付いたらリリアンナになってただけなんだけど⁉」
「気にしなくていいよ、穂香」
「そうです忘れましょう」
優子と上野さんの笑みは穏やかで優しくて、私はそれ以上何も言えなかった。
それからは私は優子がイザベラになった後の話を聞いた。
今の両親が大好きな優子は、とりあえずイザベラらしく過ごすことに決めたらしい。別に悪役令嬢と言う枠ではあるものの、シナリオ本編にイザベラはほとんど関与しない。それならば、シナリオに沿った動きさえすれば後はどうとでもなる。幸い、イザベラと似通った性格だった優子はすんなり環境に順応できたらしい。
問題だったのは、ナンニー二家が商売人の家系だったこと。社交界でも積極的にドレスや布、宝飾品を宣伝するのがナンニー二家での常だった。ただの女子高生だった優子が、そんな派手な生活についていけるわけがない。日本円で考えたら何十万、何百万もしそうな商品を前にして、最初は眩暈がしていたらしい。それでもやるしかないとなんとか噛り付いていき、商品を気に入ってくれるお客様や自分たちが作った物が売れて喜んでいる制作者の様子を見て、徐々に今の環境を気に入ったと言うのだ。そうして、あの原作そっくりの派手好きなイザベラが誕生した。
「リリアンナの変化や私の存在は気にならなかったのですか?」
「気になりはしたけど、すでに私の存在が異質だもの。そんな変化もあるだろうし、私が知らなかっただけで他にも側近候補が存在していたって不思議じゃないわ」
本当に、すごい順応力だ。ちょっとした違和感は全てそういうものとして受け取り、自分には関係がないと切り捨てていった。優子はそういうさっぱりしているというか、サバサバしたタイプだったことを思い出す。
「今度は二人の番よ。転生してからどうしてきたの?」
「私は大したことは特に。精神が幼い頃から大人でしたし、ゲームの知識もありましたから。それを使ってなんとしても側近候補になってやろうと、躍起になっていただけです」
そういえば、上野さんの口から改めて話を聞くのは始めてかもしれない。私が知っている情報は、シヴァが集めたものだけだ。
「なんでそこまでして側近候補に? やっぱり、自分が作ったゲームがリアルで繰り広げられているのを見たかったからですか?」
楽しそうに優子が質問する。相変わらず、物おじせずにずけずけと話をするタイプだ。実に優子らしい。
「そうですね、それもありますが……」
言葉を止めると、上野さんは私の方を見た。何が言いたいのか分からず首を傾げると、上野さんは困ったように笑う。
「リリアンナに会いたかったんです。私がこうして転生しているなら、もしかしたら妻も……と。ただの都合がいい想像でしたけどね」
……あ。
そうだった。リリアンナは、上野さんの奥さんがモデルだったと聞いた。それなら、外見は違っても妻本人が転生している可能性もあるし、そうでなくても妻の面影を辿ることはできる。それなのに、よりによって転生したのは私で中身が別人に変わってしまっていたのだ。それを知った上野さんの落胆と絶望は、どれほどのものだろうか。
「……ごめんなさい」
想像しただけで泣きそうになってしまう。そんな私の顔を見て、上野さんは笑った。
「気にしないで下さい。ただの都合のいい想像。賭けでしかありませんから。……それに、ファンと交流できることも十分嬉しいですよ?」
その表情は明るい。さすが大人だ。私だったらきっと、ずっと気持ちを引きずってしまうだろうから。
「え? 何? 何の話?」
事情が分からず不思議がる優子に、私と上野さんは事情を説明した。上野さんはついでにシヴァの裏設定なども話してくれる。その話に喜ぶ優子の顔を見て、彼も満足げだ。車内にはすっかり明るい雰囲気が広がっていた。
イザベラの口から発せられたのは、聞き間違えるはずもない。日本の女子高生だった頃、大親友でいつも行動を共にしていた相羽優子の名前だった。
思い返してみれば、なんだかイザベラの言動はやけに優子に似ていた気がする。気の強いところも、正義感が強いところも。そんなに似ていたのに、何故気付けなかったのか。もっと早く気付いていれば、何かできたかもしれないのに。それが悔やまれてならない。
「そうだよ、穂香」
こうして改めて見てみると、イザベラの笑い方は優子によく似ていた。勝ち気だが人情味のある温かい笑み。
「私、ごめん……なんで、今まで気づかなかったんだろう」
「ずっとイザベラらしく振舞う癖がついていたし、元々の性格が似ていたみたいだからね。私、上手にイザベラやれてたでしょ?」
「ええ、本当に。今まで私達と同じ転生者だったなんて全く気付きませんでしたよ」
ため息をつきながら上野さんは笑った。私も息を整えて、久しぶりの親友と色々話をしたくなった。
「優ちゃん、なんでそんなに真面目にイザベラのふりを?」
「だって、イザベラは別に不幸な運命を辿らないもの。だったらシナリオ通りに進んでもらった方が、ファンとしては楽しいじゃない? それにね、あんな風に死んだ直後だったから、取り乱していた私を家族は優しく接してくれたの。その恩に報いたかっただけよ」
過去を懐かしむように遠くを見ながら優子が話す。軽く話しているが、絶対に聞き逃してはいけない言葉が気になった。
「……死んだって、どういうこと?」
「「え?」」
私の言葉に驚いたのは、優子と上野さんだった。驚く私をよそに、二人は顔を見合わせる。
「えっと、上野……さん? 貴方は」
「病死でした。最期は病院のベッドの上です」
「私は事件に巻き込まれて……そっか、穂香は覚えてないんだ」
二人はとんとん拍子に会話を進めるが、私には何のことだか分からない。目を白黒させていると、少し考えた優子が私の方を向いた。
「うん……覚えてないなら、それでいいよ。そんな記憶、なくてもいい」
「それには全面的に賛成です」
なんだか勝手に二人の間で話が終わってしまったみたいだ。完全に私は置いてけぼり状態だ。
「え? やっぱりここって死後の世界なの? 私は気付いたらリリアンナになってただけなんだけど⁉」
「気にしなくていいよ、穂香」
「そうです忘れましょう」
優子と上野さんの笑みは穏やかで優しくて、私はそれ以上何も言えなかった。
それからは私は優子がイザベラになった後の話を聞いた。
今の両親が大好きな優子は、とりあえずイザベラらしく過ごすことに決めたらしい。別に悪役令嬢と言う枠ではあるものの、シナリオ本編にイザベラはほとんど関与しない。それならば、シナリオに沿った動きさえすれば後はどうとでもなる。幸い、イザベラと似通った性格だった優子はすんなり環境に順応できたらしい。
問題だったのは、ナンニー二家が商売人の家系だったこと。社交界でも積極的にドレスや布、宝飾品を宣伝するのがナンニー二家での常だった。ただの女子高生だった優子が、そんな派手な生活についていけるわけがない。日本円で考えたら何十万、何百万もしそうな商品を前にして、最初は眩暈がしていたらしい。それでもやるしかないとなんとか噛り付いていき、商品を気に入ってくれるお客様や自分たちが作った物が売れて喜んでいる制作者の様子を見て、徐々に今の環境を気に入ったと言うのだ。そうして、あの原作そっくりの派手好きなイザベラが誕生した。
「リリアンナの変化や私の存在は気にならなかったのですか?」
「気になりはしたけど、すでに私の存在が異質だもの。そんな変化もあるだろうし、私が知らなかっただけで他にも側近候補が存在していたって不思議じゃないわ」
本当に、すごい順応力だ。ちょっとした違和感は全てそういうものとして受け取り、自分には関係がないと切り捨てていった。優子はそういうさっぱりしているというか、サバサバしたタイプだったことを思い出す。
「今度は二人の番よ。転生してからどうしてきたの?」
「私は大したことは特に。精神が幼い頃から大人でしたし、ゲームの知識もありましたから。それを使ってなんとしても側近候補になってやろうと、躍起になっていただけです」
そういえば、上野さんの口から改めて話を聞くのは始めてかもしれない。私が知っている情報は、シヴァが集めたものだけだ。
「なんでそこまでして側近候補に? やっぱり、自分が作ったゲームがリアルで繰り広げられているのを見たかったからですか?」
楽しそうに優子が質問する。相変わらず、物おじせずにずけずけと話をするタイプだ。実に優子らしい。
「そうですね、それもありますが……」
言葉を止めると、上野さんは私の方を見た。何が言いたいのか分からず首を傾げると、上野さんは困ったように笑う。
「リリアンナに会いたかったんです。私がこうして転生しているなら、もしかしたら妻も……と。ただの都合がいい想像でしたけどね」
……あ。
そうだった。リリアンナは、上野さんの奥さんがモデルだったと聞いた。それなら、外見は違っても妻本人が転生している可能性もあるし、そうでなくても妻の面影を辿ることはできる。それなのに、よりによって転生したのは私で中身が別人に変わってしまっていたのだ。それを知った上野さんの落胆と絶望は、どれほどのものだろうか。
「……ごめんなさい」
想像しただけで泣きそうになってしまう。そんな私の顔を見て、上野さんは笑った。
「気にしないで下さい。ただの都合のいい想像。賭けでしかありませんから。……それに、ファンと交流できることも十分嬉しいですよ?」
その表情は明るい。さすが大人だ。私だったらきっと、ずっと気持ちを引きずってしまうだろうから。
「え? 何? 何の話?」
事情が分からず不思議がる優子に、私と上野さんは事情を説明した。上野さんはついでにシヴァの裏設定なども話してくれる。その話に喜ぶ優子の顔を見て、彼も満足げだ。車内にはすっかり明るい雰囲気が広がっていた。