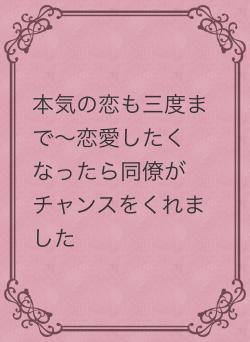「飲まないのか?」
「ああ、今日は社長から呼び出しがかかるかもしれない。
大体それがわかってるからお前もここに呼び出したんだろ?」
「まあな。こんな時間にも秘書さまはご苦労なことだ」
悠真はわざとらしく貴也に驚いてみせる。
「親子揃って働きすぎだよ。
秘書としてはいい加減にして欲しいね」
冗談混じりの貴也の言葉に悠真も笑いが漏れた。
「近々社長との打ち合わせの時間取ってくれないか?
勝手に進められる前に親父に釘を刺しときたい」
悠真は表情を引き締めると、眼下の夜景を眺めながら言った。
「わかった。候補日調整つけて連絡する。
親子で俺を挟むなよ」
貴也はノンアルコールビールを飲みながら表情を変えずに答える。
「で、今人事の件、どう動いてる?」
「秘書として言わせてもらうと、今のお前の実績での役員昇格は十分適正だ。
友人として言えるのは、お前の親父さんはやっぱすごい。社内の掌握も根回しも十分すぎるくらい準備は進んでるよ」
「そうか」
社長秘書として多くは話せない貴也の答えとしてはこれくらいが聞き出せる限度だろう。
悠真もそれ以上深く聞くことはせず、グラスを手に取る。
「新しいアシスタントの田宮さん、どうなんだ?」
配置換え程度だから把握してるとは思わなかったので、貴也が田宮さんのことを聞いてきたことに驚いた。それくらい父が過敏に俺の動向を監視しているのだろう、と悠真は思った。
「元々部下だから、評価は変わらない。
よくやってくれてるよ。
何も知らない秘書課の人間をつけられるのはもうごめんだな」
「秘書課の人間捕まえていうことかよ」
貴也が苦笑いするが、この表情は悠真が「もうごめんだ」という理由をよくわかっているからだ。
加山の休暇中に秘書課から悠真につけられたのは、秘書としてはベテランの女性社員。
スケジューリングなど一般的秘書業務は問題なかったのだが、プライドが高く秘書業務以外のアシスタント業務は一切手をつけようとせず、他の部課員との軋轢を生んだ。
期間限定だからと切り分けて考えてはいたものの、あれでは今後自分が役員になっても秘書は付けたくないと悠真は強く思った。
「肩書きや仕事で態度が変わるような秘書は配置換えすべきだな。会社の信用にかかわる」
「お前が役員になってからの仕事が見つかって何よりだよ」
貴也は笑って何も否定しなかった。
彼も社長付きで課内すべてを掌握しているわけではないから、色々と思うところがあっても口を出さないようにしているのだろう。
しばらく話し込んでいると、貴也が「やっぱりきたよ」とスマホの着信を確認して席を立つ。
それに合わせてチェックを済ませ、悠真も店を後にした。
「ああ、今日は社長から呼び出しがかかるかもしれない。
大体それがわかってるからお前もここに呼び出したんだろ?」
「まあな。こんな時間にも秘書さまはご苦労なことだ」
悠真はわざとらしく貴也に驚いてみせる。
「親子揃って働きすぎだよ。
秘書としてはいい加減にして欲しいね」
冗談混じりの貴也の言葉に悠真も笑いが漏れた。
「近々社長との打ち合わせの時間取ってくれないか?
勝手に進められる前に親父に釘を刺しときたい」
悠真は表情を引き締めると、眼下の夜景を眺めながら言った。
「わかった。候補日調整つけて連絡する。
親子で俺を挟むなよ」
貴也はノンアルコールビールを飲みながら表情を変えずに答える。
「で、今人事の件、どう動いてる?」
「秘書として言わせてもらうと、今のお前の実績での役員昇格は十分適正だ。
友人として言えるのは、お前の親父さんはやっぱすごい。社内の掌握も根回しも十分すぎるくらい準備は進んでるよ」
「そうか」
社長秘書として多くは話せない貴也の答えとしてはこれくらいが聞き出せる限度だろう。
悠真もそれ以上深く聞くことはせず、グラスを手に取る。
「新しいアシスタントの田宮さん、どうなんだ?」
配置換え程度だから把握してるとは思わなかったので、貴也が田宮さんのことを聞いてきたことに驚いた。それくらい父が過敏に俺の動向を監視しているのだろう、と悠真は思った。
「元々部下だから、評価は変わらない。
よくやってくれてるよ。
何も知らない秘書課の人間をつけられるのはもうごめんだな」
「秘書課の人間捕まえていうことかよ」
貴也が苦笑いするが、この表情は悠真が「もうごめんだ」という理由をよくわかっているからだ。
加山の休暇中に秘書課から悠真につけられたのは、秘書としてはベテランの女性社員。
スケジューリングなど一般的秘書業務は問題なかったのだが、プライドが高く秘書業務以外のアシスタント業務は一切手をつけようとせず、他の部課員との軋轢を生んだ。
期間限定だからと切り分けて考えてはいたものの、あれでは今後自分が役員になっても秘書は付けたくないと悠真は強く思った。
「肩書きや仕事で態度が変わるような秘書は配置換えすべきだな。会社の信用にかかわる」
「お前が役員になってからの仕事が見つかって何よりだよ」
貴也は笑って何も否定しなかった。
彼も社長付きで課内すべてを掌握しているわけではないから、色々と思うところがあっても口を出さないようにしているのだろう。
しばらく話し込んでいると、貴也が「やっぱりきたよ」とスマホの着信を確認して席を立つ。
それに合わせてチェックを済ませ、悠真も店を後にした。