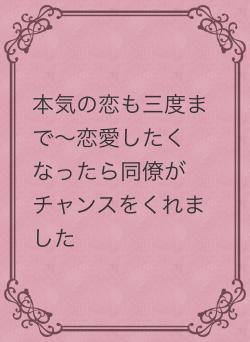ページを捲る音すら立てられないような張り詰めた空気の中、隣のテーブルに神経を集中させる。
席と席の仕切りもない、テーブル二つ、カウンター席四つの本当に小さな珈琲店。
結衣(ゆい)はテーブル席の一つを占領し、資格試験のテキストを広げていた。
結衣の隣のテーブルで向かい合わせに座る男女。
テキストに集中して、二人が入ってきた時には気づかなかった。しかし程なく会話が聞こえてくると、人様の話だからいけないと思いつつも、二人に意識が引っ張られた。
男性は結衣の並び席で顔が見えない。向かいの席に座る女性はとても綺麗な人。
年は二十六歳の結衣より少し上くらいだろうか。
ふんわりとカールした艶のある栗毛は女性の顔立ちによく似合っている。寂しげな表情でも華がある。
「もう別れましょう。」
先ほどから「あなたから連絡をもらえないから寂しい。なぜ会ってくれないのか」と涙ながらに意思を伝えていた女性からついにその言葉が出た。
するとそれまで一言も発しなかった男性が大きなため息をついた。
「別れることに異論はない。
それじゃあ
今この場で私の連絡先消してくれるかな?」
「えっ」
女性の声と結衣の心の声が重なる。
「君とは他に接点がない。だから今後君と連絡を取ることもないだろ?
後から連絡されても困るんだ。
別れたくなかったとか、なぜ引き止めてくれないのかとか。君がそうとはいわないが、そんな女性もいるからね。
私の連絡先は今ここで消してくれ」
女性の反応を気にしていないのか、男性は手元のスマホを操作している。
女性の連絡先を消しているのだろうか。
「最低です」
女性は立ち上がり、涙目で男性を睨みつけると店をあとにした。
男性は、一度大きく息をつき、アイスコーヒーを飲み干すと立ち上がり、出入口の方へと歩きだす。
ドラマみたいな場面に遭遇しちゃった。
結衣はドキドキしながら俯いたまま、あわてて右手のペンを握り直し、テキストを見る素振りで、そっと男性の方へ視線を上げた。
すると男性は立ち止まり結衣を見ていた。
「田宮さん、ここで見たことは忘れてくれるかな」
こちらを見ていたのは、上司である湊部長だった。
しまった。
まさか知っている人だとは思わなかった。
「部長、お疲れ様です」
「お疲れ様、ね。
これ口止め料ね。
じゃあ、仕事に戻るから」
苦笑いしながら結衣のテーブルの伝票も一緒に掴むと、結衣が口を挟む間もなく彼は会計を済ませ出て行った。
時刻は夜九時。
こんな時間まで働いてるんだ。
オフィス近くの珈琲店オアシス。
奥まった路地にあるかなり古い喫茶店で、階上に住んでいる年配のマスター小谷(こたに)さんと奥様の美子(よしこ)さんが二人で営んでいる小さな店。
マスターは道楽だよというが、豆にも焙煎にもこだわっていて、本当にリラックスできる一杯が味わえる。
純粋にコーヒーを楽しむ店で、食事メニューもない。食事がないこの店は、ランチが終わった時間帯から夜遅くまで営業している。
田宮結衣(たみやゆい)は、会社の人と会うこともなく一人で安心してくつろげるこの店で、仕事帰りの時間を過ごすことが日課となっていた。
はぁ、ここで会社の人に会うなんて…。
それにしても、これからまた仕事に戻るなんて、部長は何時まで働いてるんだろう。
ぼんやりとオフィスの様子を思い浮かべた。
彼、湊悠真(みなとゆうま)部長は、結衣が勤める会社の社長の子息だ。
結衣がまだ新人の頃、彼が二十九歳で部長となったのも大抜擢だったが、社長の息子だからという一部の批判的な声は、彼が次々と上げ続ける成果を前にして聞こえなくなった。今の会社の業績好調の要因には彼が中心になっているところは間違いない。
現在三十二歳の彼は、次の役員改選ではいよいよ役員に名を連ねるのではないかとの噂もある。
スラリと背が高く、切れ長の目に軽く流した髪、まるで小説に出てくる外国の貴族のような風貌。そして優しくて部下から慕われる上司だ。
まるでどこぞの王子様のような彼が、女性にあんなキツイことを言うのが意外だった。
「相手の女性、綺麗だったな。」
つぶやいた結衣は、夜の街を眺めるふりをして、窓に映る自分の姿を見つめる。
胸あたりまで伸びた黒髪を後ろで一つに結び、二十六歳になったが就活の頃から変わらないシンプルな黒スーツスタイル。決してくたびれてはいないのだが、お世辞にも仕事ができるようには見えない。
店員に似合ってると勧められて選んだオーバルフレームのメガネは、おとなしめな結衣の表情をより重たく見せてしまっていた。
そっと髪を解いてみたところで、大して印象は変わらない。
頭に入ってこないテキストを閉じると、残っていたコーヒーを飲んで席を立った。
「あら、結衣ちゃん今日は早いわね」
美子さんから声がかかる。
「お代も払ってもらっちゃったし、今日は失礼します」
「素敵な人だったわね」
「会社の上司なんです。あんなに若いのに部長さんなんですよ。私とは住む世界がちがいますから」
結衣がははっと笑うと、美子は幼子を叱るような顔をする。
「いつも言うけど、結衣ちゃんかわいいんだから、もっと自信持ったらいいのよ」
地方から東京へ就職のために出てきた結衣にとって、マスターと美子は頼れる親戚のような存在だ。
「美子さん、ありがとうございます」
オアシスを出ると、外の空気はじわっと湿気を含んでいた。
もう十月だと言うのに、秋の気配は感じられない。
今日も湿度が高いせいか。歩けばじんわり汗ばむような気色さえ感じられた。
席と席の仕切りもない、テーブル二つ、カウンター席四つの本当に小さな珈琲店。
結衣(ゆい)はテーブル席の一つを占領し、資格試験のテキストを広げていた。
結衣の隣のテーブルで向かい合わせに座る男女。
テキストに集中して、二人が入ってきた時には気づかなかった。しかし程なく会話が聞こえてくると、人様の話だからいけないと思いつつも、二人に意識が引っ張られた。
男性は結衣の並び席で顔が見えない。向かいの席に座る女性はとても綺麗な人。
年は二十六歳の結衣より少し上くらいだろうか。
ふんわりとカールした艶のある栗毛は女性の顔立ちによく似合っている。寂しげな表情でも華がある。
「もう別れましょう。」
先ほどから「あなたから連絡をもらえないから寂しい。なぜ会ってくれないのか」と涙ながらに意思を伝えていた女性からついにその言葉が出た。
するとそれまで一言も発しなかった男性が大きなため息をついた。
「別れることに異論はない。
それじゃあ
今この場で私の連絡先消してくれるかな?」
「えっ」
女性の声と結衣の心の声が重なる。
「君とは他に接点がない。だから今後君と連絡を取ることもないだろ?
後から連絡されても困るんだ。
別れたくなかったとか、なぜ引き止めてくれないのかとか。君がそうとはいわないが、そんな女性もいるからね。
私の連絡先は今ここで消してくれ」
女性の反応を気にしていないのか、男性は手元のスマホを操作している。
女性の連絡先を消しているのだろうか。
「最低です」
女性は立ち上がり、涙目で男性を睨みつけると店をあとにした。
男性は、一度大きく息をつき、アイスコーヒーを飲み干すと立ち上がり、出入口の方へと歩きだす。
ドラマみたいな場面に遭遇しちゃった。
結衣はドキドキしながら俯いたまま、あわてて右手のペンを握り直し、テキストを見る素振りで、そっと男性の方へ視線を上げた。
すると男性は立ち止まり結衣を見ていた。
「田宮さん、ここで見たことは忘れてくれるかな」
こちらを見ていたのは、上司である湊部長だった。
しまった。
まさか知っている人だとは思わなかった。
「部長、お疲れ様です」
「お疲れ様、ね。
これ口止め料ね。
じゃあ、仕事に戻るから」
苦笑いしながら結衣のテーブルの伝票も一緒に掴むと、結衣が口を挟む間もなく彼は会計を済ませ出て行った。
時刻は夜九時。
こんな時間まで働いてるんだ。
オフィス近くの珈琲店オアシス。
奥まった路地にあるかなり古い喫茶店で、階上に住んでいる年配のマスター小谷(こたに)さんと奥様の美子(よしこ)さんが二人で営んでいる小さな店。
マスターは道楽だよというが、豆にも焙煎にもこだわっていて、本当にリラックスできる一杯が味わえる。
純粋にコーヒーを楽しむ店で、食事メニューもない。食事がないこの店は、ランチが終わった時間帯から夜遅くまで営業している。
田宮結衣(たみやゆい)は、会社の人と会うこともなく一人で安心してくつろげるこの店で、仕事帰りの時間を過ごすことが日課となっていた。
はぁ、ここで会社の人に会うなんて…。
それにしても、これからまた仕事に戻るなんて、部長は何時まで働いてるんだろう。
ぼんやりとオフィスの様子を思い浮かべた。
彼、湊悠真(みなとゆうま)部長は、結衣が勤める会社の社長の子息だ。
結衣がまだ新人の頃、彼が二十九歳で部長となったのも大抜擢だったが、社長の息子だからという一部の批判的な声は、彼が次々と上げ続ける成果を前にして聞こえなくなった。今の会社の業績好調の要因には彼が中心になっているところは間違いない。
現在三十二歳の彼は、次の役員改選ではいよいよ役員に名を連ねるのではないかとの噂もある。
スラリと背が高く、切れ長の目に軽く流した髪、まるで小説に出てくる外国の貴族のような風貌。そして優しくて部下から慕われる上司だ。
まるでどこぞの王子様のような彼が、女性にあんなキツイことを言うのが意外だった。
「相手の女性、綺麗だったな。」
つぶやいた結衣は、夜の街を眺めるふりをして、窓に映る自分の姿を見つめる。
胸あたりまで伸びた黒髪を後ろで一つに結び、二十六歳になったが就活の頃から変わらないシンプルな黒スーツスタイル。決してくたびれてはいないのだが、お世辞にも仕事ができるようには見えない。
店員に似合ってると勧められて選んだオーバルフレームのメガネは、おとなしめな結衣の表情をより重たく見せてしまっていた。
そっと髪を解いてみたところで、大して印象は変わらない。
頭に入ってこないテキストを閉じると、残っていたコーヒーを飲んで席を立った。
「あら、結衣ちゃん今日は早いわね」
美子さんから声がかかる。
「お代も払ってもらっちゃったし、今日は失礼します」
「素敵な人だったわね」
「会社の上司なんです。あんなに若いのに部長さんなんですよ。私とは住む世界がちがいますから」
結衣がははっと笑うと、美子は幼子を叱るような顔をする。
「いつも言うけど、結衣ちゃんかわいいんだから、もっと自信持ったらいいのよ」
地方から東京へ就職のために出てきた結衣にとって、マスターと美子は頼れる親戚のような存在だ。
「美子さん、ありがとうございます」
オアシスを出ると、外の空気はじわっと湿気を含んでいた。
もう十月だと言うのに、秋の気配は感じられない。
今日も湿度が高いせいか。歩けばじんわり汗ばむような気色さえ感じられた。