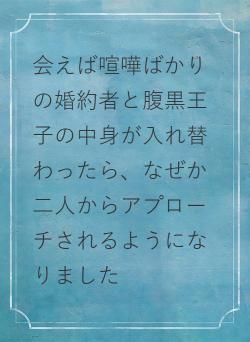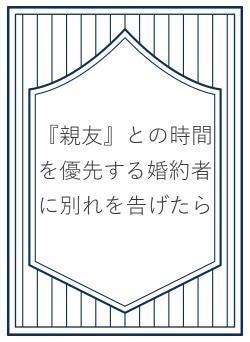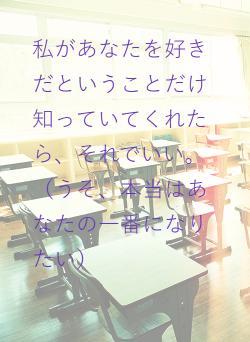クロエの実家であるオーリク子爵家。
その執務室では、オーリク子爵……ではなくその息子が執務机にかじりつく勢いで書類を捌いていた。
本来その仕事をしなければならない父親は今手が空いていないからだ。
常日頃から父の手伝いをしているので要領は得ている。隣には手伝ってくれる筆頭執事もいる。
――――大丈夫。俺はやれる! だから……父上はそんな目でこっちを見ないでくれ!
執務室内に置いてある来客対応用の机を挟んでオーリク子爵とクロエは対峙していた。クロエの横にはオーリク子爵夫人も座っている。そう、この狭い執務室に家族全員揃っているのだ。とても珍しいことである。家族愛に溢れるオーリク子爵、これがただの家族団欒の場であれば喜んでいたことだろう。だが、残念ながら違った。
オーリク子爵のこめかみから冷や汗が落ちる。後ろにいる息子に助けを求めようとしたが視線は全く合わなかった。
クロエの横に座っている妻はずっと微笑んでいるだけで何も言わない。いったい何を考えているのだろうか。
そして、愛娘クロエはというと……
「お父様」
「は、はい」
「もう、充分でしょう?」
にっこりと微笑むクロエ。けれど、その目からは有無を言わせない圧を感じる。
それでもオーリク子爵はなんとか抗おうとした。
「い、いや、でも、あんな噂があったばかりだ。落ち着くまでもう少しここにいても」
「お父様」
「はいっ」
「わざわざ噂を助長させるつもりですか?」
「ま、まさか!」
クロエに睨まれたオーリク子爵は姿勢を正して、必死に首を横に振った。
「あなた」
口を挟んだのは愛する妻。彼女なら、自分の気持ちをわかってくれるだろうと期待の目を向ける。
「もう許してあげましょう」
ガーン、とオーリク子爵は固まる。オーリク子爵夫人はそんな彼を見て、困った人と微笑みながら言った。
「もう充分よ。これ以上はクロエも可哀相だわ」
「し、しかし……あいつはクロエを私達から三年以上も奪っておいて、あんな噂を流される隙を作ったんだぞ?!」
「その隙を作ったのは私達のせいでもあるわ。彼は三年以上も私達との約束を守ってくれているじゃない。……あなたとは違って」
オーリク子爵は言葉を詰まらせた。
妻の言う通り、自分には婚前交渉をして妻を孕ませてしまった過去がある。その結果、今後ろで執務に追われている息子が生まれた。でも、後悔は今もしていない。
オーリク子爵はぐぬぬぬと唸り声を上げた後、とうとう肩を落としてクロエの意見を受け入れた。
クロエは喜び、明るい声を上げる。
「お父様ありがとう! お母様も、お兄様も!」
心の底から喜んでいるクロエを見て、この場にいる全員の顔に笑みが浮かんだ。
その時、何やら外が騒がしいことに気づく。
クロエの耳は微かに聞こえてきた声を聞き逃さなかった。
「お母様。私、行くわ!」
「ええ、行ってらっしゃい」
心得ているようにオーリク子爵夫人が応える。クロエは淑女のあれやこれを投げ捨て、執務室を飛び出した。
ドレスを持ち、階段を駆け下りる。
エントランスには予想通りの人物がいた。
「ダニエル!」
「クロエ!」
気がはやり過ぎていたのだろう。階段を踏み外した。クロエは痛みに備えて目をぎゅっと閉じる。
けれど、いつまで経っても痛みはやってこなかった。代わりに懐かしい感触が全身を包み込む。
目を開けば、愛しいダニエルの顔が眼前にあった。ダニエルは眉を下げて、クロエを覗き込む。
「クロエ、俺の寿命が縮まるから足元には気をつけて」
「ふふ、それは困るから。次から気をつけるわ」
そう言って、ダニエルの首に手を回す。ぎゅっと抱きつけば、ぎゅううううううと抱き返してくる。
――――ああ、コレよコレ。
少々苦しいが、これくらいがちょうどいい。
「もっと、時間がかかると思ってた。頑張ったのね」
「うん。俺、頑張った。クロエに早く会いたかったから」
えらいえらいと片手で頭を撫でれば、ダニエルはクロエの首あたりに顔を押し付ける。実はクロエの匂いを嗅ぐ為の行動なのだが、クロエはただ甘えているだけだと思ってさらによしよし頭を撫でる。
そんな二人を階段上から、オーリク子爵が目を血走らせながら見つめていた。今にも邪魔をしに行きそうなオーリク子爵の腕に己の腕を絡めて足止めしているオーリク子爵夫人は微笑ましげに二人を見守っていた。
ちなみに、息子と執事は今も執務室で必死に仕事と向き合っている。
数十分後。クロエはそっとダニエルから離れた。ダニエルは物足りなそうな顔をしていたが、クロエの意思を汲み取って離れる。
クロエはダニエルをじっと見つめた。
「ダニエル」
「ん?」
「私も、ダニエルと離れている間頑張っていたのよ」
よくわからないが、うんと頷くダニエル。
クロエは少し照れくさそうに、そして嬉しそうに、ダニエルを見上げて言った。
「お父様から許可が取れたわ」
「…………ぇ?」
『はてなまーく』がたくさん飛んでいるような顔を浮かべているダニエル。
そんな顔を見て思わずクロエは吹き出した。もう一度ダニエルにもはっきりわかるように告げる。
「来年、結婚式を挙げるわよ!」
「え?! 誰の?!」
「私達のに決まってるでしょ!」
「本当に?!」
「本当に! 後、一年でいろいろ準備しないといけないし、お義父様やお義母様にも報告しないと。忙しくなるわよ!」
「やっ」
「や?」
「やったー!」
ダニエルはクロエを抱き上げ、くるくると回る。周りで静かに控えていたメイドや執事達が焦って止めようとしたが、二人があまりにも幸せそうにしているので結局再び口を閉じ、壁となった。
そして、オーリク子爵も娘の幸せそうな顔を見てさすがに邪魔はできないと、すごすごと執務室へと戻って行った。一気に老けた夫を支えながらオーリク子爵夫人も戻る。
エントランスからは、幸せそうな娘の笑い声と、未来の息子の声が響き続けていた。
――――――――
久しぶりのジョルダン男爵家。帰宅早々、両親に報告を済ませるとダニエルはクロエを抱えて自室に引きこもった。その際、扉の外に『(クロエ)補充中立ち入り禁止』看板をぶら下げるのを忘れずに。
ダニエルはソファーに腰かけ、己の足の上にクロエを乗せると、後ろから抱きしめた。満足げに息を吐きだす。クロエもされるがままだ。その顔はまんざらでもない。なんだかんだ言って、クロエもダニエルと離れているのは辛かったのだ。
ダニエルはクロエにぴったりとくっついたまま、ふと思いついた疑問を口にする。
「もしかして、クロエが実家に帰るって言ったのは結婚式の許可を取る為?」
その質問にクロエはうーん、と唸る。確かにそれも理由の一つだが……。
「それもあるし、最悪な事態を避ける為……でもあったかな」
クロエは元々王家に目をつけられていた。サラの侍女として。
オーリク子爵家は目立った功績こそないが、その頭脳の高さには定評がある一族だ。そして、クロエも学園時代に学年トップクラスの成績を残していた。
しかも、爵位がそこまで高くないからサラにつけやすい人材でもある。
そんな中、起こった今回の事件。
今回のことで王家がサラに抱く評価は大幅に下がったことだろう。このままだと王太子妃にするのは難しいと考えているはずだ。
けれど、もしクロエを取り込むことができたら……今回の噂はただの噂だったとして醜聞を消すことができる上に、サラに有能な侍女をつけることができる。
クロエはしがない子爵令嬢。ダニエルとは違い、王家に言われれば断ることはできない。つまり、その場にクロエがいたら、そのまま命令される可能性もあったのだ。もし、そうなったらダニエルは黙っていなかっただろうが、それはそれで血を見ることになっていただろう。どちらにしても最悪だ。
もちろん、これはあくまでクロエが立てた仮定の一つ。けれど、その可能性を否定もできなかった。
だから、クロエは実家に帰ることにしたのだ。
噂の解決はダニエルに任せて、自分は噂に傷ついているフリをして実家にひきこもり、絶対にサラとは会いたくないと言外に伝える。ここまですれば、強引な手は打ってこないだろう。
ダニエルにはクロエが言った最悪な事態がどんなことかはわからなかったが、クロエの要望通りにことがおさまったことだけはわかった。
よかったと頷くダニエルを見てクロエはほんわかした気分になる。
「まあ、でも、単に私がダニエルとサラ様の噂をあれ以上耳にしたくなかったっていうのもあるけどね」
つい、ぽろりと本音が零れた。
普段自分の気持ちをはっきりとは言わないクロエだ。羞恥心で顔に熱が集まる。きっと、耳まで真っ赤になっているはず。恥ずかしくなってクロエは俯いた。
だから、気づかなかった。ダニエルが歓喜に震え、顔を真っ赤にしていることに。
「好きっ。好き好き好き好き」
「ちょ、く、くるしっ」
ダニエルは感極まって力を入れすぎた腕を慌てて解いた。クロエは振り向いてダニエルを睨みつける。
「ご、ごめんなさい」
しょんぼり俯いて反省するダニエル。
――――くっ。そんな顔されたら怒りたくても怒れないじゃない!
クロエは叱る代わりに、両手を伸ばしてダニエルの両頬に手を当てた。強引に顔を上げさせると……問答無用で唇を奪った。
「んうっ?!」
あわあわとダニエルが慌てているのがわかるが、放してはやらない。
クロエはダニエルに覆いかぶさるようにして唇を何度も重ねる。唇に隙間が生まれれば、そこから舌をねじ込む。
これに驚いたのはダニエルだ。動揺して、両手が泳ぐ。このままクロエを抱きしめていいものか。抱きしめたら……なんか、ヤバい気がする。
そんな葛藤を抱くダニエル。だが、クロエはまだ離れるつもりはない。
次第に、ダニエルもおずおずと舌を絡めだした。
いつの間にか、ダニエルの腕がクロエの背中に回っている。
熱い身体。ダニエルの瞳が揺れ、情欲の色が灯る。その目を見て……
「ストップ」
クロエは離れた。
「え」と呆けた顔のダニエル。クロエはいたずらっ子のように微笑み、ダニエルに告げる。
「約束してたご褒美はここまで。この先は、式を挙げた後ね」
そんなと絶望の表情を浮かべるダニエル。けれど、クロエの父親と約束したことが頭を過り、仕方なく頷いた。
必死に、己の欲望を抑え込もうと耐えているダニエルをクロエは愛しげに見つめる。
「ダニエル」
「ん?」
「好きよ」
そう言って、ダニエルの顎に指をかけるとクイッと上を向かせた。そして、のどぼとけにチュッと口づける。本当はキスマークの一つでも残しておきたいが、さすがに恥ずかしい。クロエにはこの一瞬だけで精一杯だ。
さっとダニエルから離れるクロエ。ダニエルの反応を窺えば、ダニエルは全身を真っ赤にして固まっていた。
「ク」
「く?」
「クロエが俺に好きって言ってくれた~うれじいいいいいいい」
そう言ってドバドバ涙を零すダニエル。そう言えば自分から言うのはあまりなかったかもしれない。
大の男が、自分が言った「好き」の一言で男泣きしている。これがダニエルでなければ「ええ~?」と引いてしまっていたかもしれない。けれど、相手は自分の愛する人だ。引くわけがない。むしろ……。
クロエはダニエルの隣に座りなおすと、そっとダニエルを抱きしめ、頭を優しく撫でた。