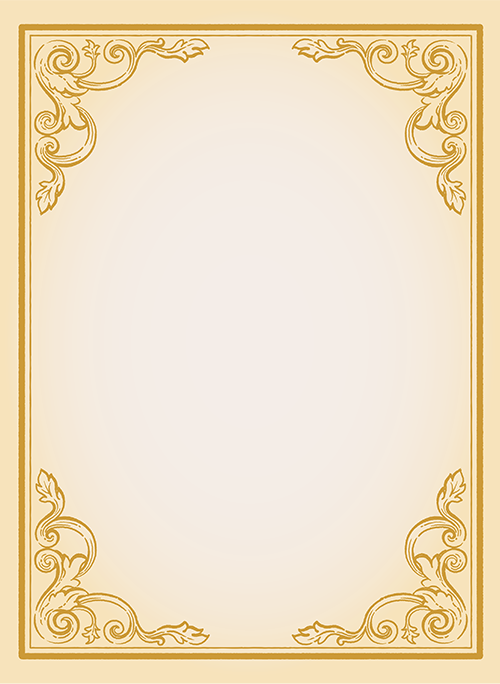「――なぁんて。冗談」
大貫はそう誤魔化して箸を置いた。
いやいやいや、まてまてまて。
「ごめん、大貫くん」
私は大貫のゴツゴツした冷たい手の上に自分の手を重ねた。
冗談じゃないでしょう。
それ、本気でしょう。
私との時間、もっと欲しいんじゃないの。
私は彼の手をギュッと握る。
「大貫くん、遠慮してるよね? 私に残業が多いの、わかってるから? それともまだ、空き巣の罪悪感があるから?」
どうしても聞きたかった。罪悪感があるなら、もう気にしないでと言いたい。
けれど大貫の視線はキッチンへ逃げる。
私と向き合うことから逃げようとする、その態度が腹立つ。
「ねえ、言いたいこと言って」
私がそう言うと、大貫はスッと手を引っ込めて立ち上がった。なにも答えず絵の前へ戻り、筆をとる。
私とは話したくない。
背中がそう告げている。
こうやって私と線を引くから、大貫はこの同居が上手くいくと思っているのだ。お互い干渉しない。ただ部屋を分け合っている人。それが私と大貫。
大貫はその線の内側へすぐに引っ込んでしまう。
それが私はつらかった。
大貫はそう誤魔化して箸を置いた。
いやいやいや、まてまてまて。
「ごめん、大貫くん」
私は大貫のゴツゴツした冷たい手の上に自分の手を重ねた。
冗談じゃないでしょう。
それ、本気でしょう。
私との時間、もっと欲しいんじゃないの。
私は彼の手をギュッと握る。
「大貫くん、遠慮してるよね? 私に残業が多いの、わかってるから? それともまだ、空き巣の罪悪感があるから?」
どうしても聞きたかった。罪悪感があるなら、もう気にしないでと言いたい。
けれど大貫の視線はキッチンへ逃げる。
私と向き合うことから逃げようとする、その態度が腹立つ。
「ねえ、言いたいこと言って」
私がそう言うと、大貫はスッと手を引っ込めて立ち上がった。なにも答えず絵の前へ戻り、筆をとる。
私とは話したくない。
背中がそう告げている。
こうやって私と線を引くから、大貫はこの同居が上手くいくと思っているのだ。お互い干渉しない。ただ部屋を分け合っている人。それが私と大貫。
大貫はその線の内側へすぐに引っ込んでしまう。
それが私はつらかった。