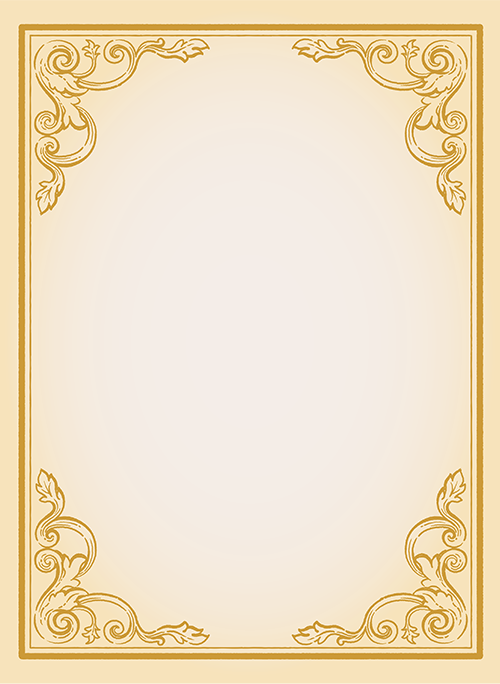ダイニングと続くリビングは大貫のアトリエである。
大貫は絵の具で汚れたエプロンに着替え、キャンバスに向かった。鉛筆で下書きされた絵を見るに、介護施設の利用者さんたちを描いているらしい。
邪魔しないように、私は料理をそしゃくしながら黙って大貫の動きを目で追っている。
大貫は筆に絵の具をベットリつけ、睨むように目を開いた。
ピリリと緊張感が走る。
作家のスイッチが入ると、大貫は神様が憑依したみたいに表情が変わる。手に炎が宿り、鬼気迫る勢いで筆をザッザッとキャンバスに押し付ける。見開いた目からチカチカと情熱の光が見えた。
ニート、なんて揶揄できない。彼は芸術家だ。
大貫は魂をガツンガツンとキャンバスにぶつけて、力を、情熱を、愛を、慈しみを真っ白な土台に乗せていく。
恐ろしく美しかった。
絵と大貫の熱量がグチャグチャになって、火山の噴火みたいに周囲を照らし流れ出す。普通の人間から放たれることのない七色の風が部屋中にいきわたり、私の身体をも巻き込んで、大貫の世界に引きずり込んでいく。
恐ろしく魅力的な沼。
触れてしまったら二度と出られなくなる。
それが大貫だった。
私は食事がのどを通らなくなって、キャンバスに舞う大貫の圧に耐えることしかできなくなった。
格好いい、なんて安っぽい言葉じゃ言い表せないほど、大貫はその存在感を爆発させ、私の心を奪っていく。
私はもう大貫から離れられないのだと、絵を描く彼の姿を眺めながら悟る。
これは恋なんて子どもっぽいものではない。もう、人生の一部にしたいほどだった。
人生の一部。
なんて厚かましいのだろう。恋人でもないのに。
考えれば考えるほど、この状況の意味不明さに嫌気がさしてくる。
不意に、大貫が筆を握る手を止め、私の方へ振り向いた。
大貫は絵の具で汚れたエプロンに着替え、キャンバスに向かった。鉛筆で下書きされた絵を見るに、介護施設の利用者さんたちを描いているらしい。
邪魔しないように、私は料理をそしゃくしながら黙って大貫の動きを目で追っている。
大貫は筆に絵の具をベットリつけ、睨むように目を開いた。
ピリリと緊張感が走る。
作家のスイッチが入ると、大貫は神様が憑依したみたいに表情が変わる。手に炎が宿り、鬼気迫る勢いで筆をザッザッとキャンバスに押し付ける。見開いた目からチカチカと情熱の光が見えた。
ニート、なんて揶揄できない。彼は芸術家だ。
大貫は魂をガツンガツンとキャンバスにぶつけて、力を、情熱を、愛を、慈しみを真っ白な土台に乗せていく。
恐ろしく美しかった。
絵と大貫の熱量がグチャグチャになって、火山の噴火みたいに周囲を照らし流れ出す。普通の人間から放たれることのない七色の風が部屋中にいきわたり、私の身体をも巻き込んで、大貫の世界に引きずり込んでいく。
恐ろしく魅力的な沼。
触れてしまったら二度と出られなくなる。
それが大貫だった。
私は食事がのどを通らなくなって、キャンバスに舞う大貫の圧に耐えることしかできなくなった。
格好いい、なんて安っぽい言葉じゃ言い表せないほど、大貫はその存在感を爆発させ、私の心を奪っていく。
私はもう大貫から離れられないのだと、絵を描く彼の姿を眺めながら悟る。
これは恋なんて子どもっぽいものではない。もう、人生の一部にしたいほどだった。
人生の一部。
なんて厚かましいのだろう。恋人でもないのに。
考えれば考えるほど、この状況の意味不明さに嫌気がさしてくる。
不意に、大貫が筆を握る手を止め、私の方へ振り向いた。