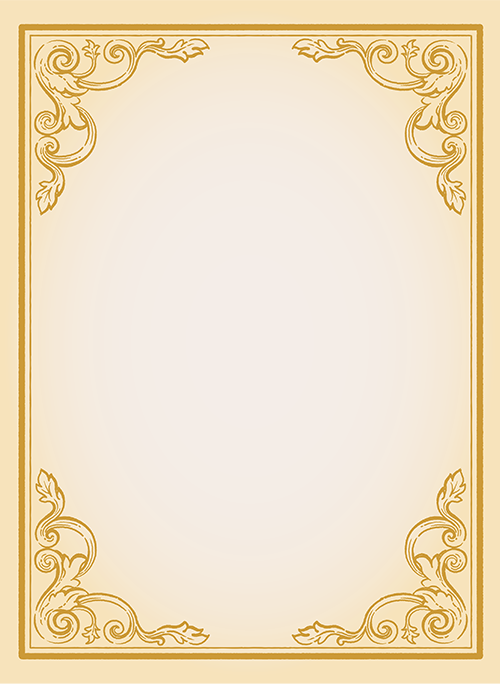「すごい、ね」
まあ、何がすごいのかはわからないけれど。
でも私の言葉に、大貫は口元を緩めている。
嬉しそうな大貫は、笑うと非常に可愛い。どんなアイドルのトレカよりも人を惹きつける、優しい魅力が彼にはあった。むしろ、絵よりも大貫の写真を売った方が儲かるんじゃないか。
「俺、本当に個展を開きたかったんだ」
大貫はそう言いながら、ほほ笑む男女の絵に手を添えた。
抽象的でわかりづらいけれど、描かれた女性は優しい目元と穏やかな笑みが聖母みたい。
「もしかしてその絵、大貫くんのご両親がモデルだったりする?」
なんとなく聞いた私を、大貫が大きな瞳で見つめる。
「なんでわかるの?」
大貫のくっきりした二重がジンジンと赤く染まっていく。瞳は涙で輝きを増した。
「そうだよ。俺の、初めてのファン。唯一のファン。それが両親だった。だから描いた」
大貫が自分の絵を見上げる。
力の入った目元は両親の絵をガッチリ捉え、強い意志をぶつけている。
「俺の頑張りを見せたかった。個展を見せたかった」
絵の両親の明るさが、影を背負う大貫とは対照的だ。両親の絵は部屋に飾られた無数の絵をニコニコ笑いながら眺めている。
「大貫くん。さっき、両親の遺産って言ってたよね。ご両親は、その」
「うん、5年前に死んだ。交通事故。それで俺はこの家を相続して、大学を辞めた。そこから親の遺産で食いつなぎつつ絵を描いてる」
大貫の目に影が落ちる。
部屋の奥にはスケッチブックや画用紙、キャンバスがいくつも積み上げられている。この5年の歴史だろう。
「俺、美大に行きたかったんだ。でも才能がなくて無理だった。代わりに絵の専門学校に行きたいって言ったら、親に『それは大学を卒業してから趣味でやれ』って言われた。それで行きたくもない大学に行って、いつか絵を描くために頑張ってた。けど両親が死んで、なんかもう将来とか、どうでもよくなっちゃったんだよね」
大貫は伏し目がちのまま、「だから貯金がなくなるまでは、絵だけ描いて生活するつもり」と自虐的に笑った。
なんだか、不憫になる。
親への想いはわかったし、無職の絵描きってどうなの? と思うし、個展の言葉につられてホイホイ空き巣をするって馬鹿すぎないかと思うけれど、そこがどうしても放っておけない。
「ねえ、大貫くん」
私は、自分も大概だなと思いながら大貫に声をかける。
「明日、私の職場に来ない?」
まあ、何がすごいのかはわからないけれど。
でも私の言葉に、大貫は口元を緩めている。
嬉しそうな大貫は、笑うと非常に可愛い。どんなアイドルのトレカよりも人を惹きつける、優しい魅力が彼にはあった。むしろ、絵よりも大貫の写真を売った方が儲かるんじゃないか。
「俺、本当に個展を開きたかったんだ」
大貫はそう言いながら、ほほ笑む男女の絵に手を添えた。
抽象的でわかりづらいけれど、描かれた女性は優しい目元と穏やかな笑みが聖母みたい。
「もしかしてその絵、大貫くんのご両親がモデルだったりする?」
なんとなく聞いた私を、大貫が大きな瞳で見つめる。
「なんでわかるの?」
大貫のくっきりした二重がジンジンと赤く染まっていく。瞳は涙で輝きを増した。
「そうだよ。俺の、初めてのファン。唯一のファン。それが両親だった。だから描いた」
大貫が自分の絵を見上げる。
力の入った目元は両親の絵をガッチリ捉え、強い意志をぶつけている。
「俺の頑張りを見せたかった。個展を見せたかった」
絵の両親の明るさが、影を背負う大貫とは対照的だ。両親の絵は部屋に飾られた無数の絵をニコニコ笑いながら眺めている。
「大貫くん。さっき、両親の遺産って言ってたよね。ご両親は、その」
「うん、5年前に死んだ。交通事故。それで俺はこの家を相続して、大学を辞めた。そこから親の遺産で食いつなぎつつ絵を描いてる」
大貫の目に影が落ちる。
部屋の奥にはスケッチブックや画用紙、キャンバスがいくつも積み上げられている。この5年の歴史だろう。
「俺、美大に行きたかったんだ。でも才能がなくて無理だった。代わりに絵の専門学校に行きたいって言ったら、親に『それは大学を卒業してから趣味でやれ』って言われた。それで行きたくもない大学に行って、いつか絵を描くために頑張ってた。けど両親が死んで、なんかもう将来とか、どうでもよくなっちゃったんだよね」
大貫は伏し目がちのまま、「だから貯金がなくなるまでは、絵だけ描いて生活するつもり」と自虐的に笑った。
なんだか、不憫になる。
親への想いはわかったし、無職の絵描きってどうなの? と思うし、個展の言葉につられてホイホイ空き巣をするって馬鹿すぎないかと思うけれど、そこがどうしても放っておけない。
「ねえ、大貫くん」
私は、自分も大概だなと思いながら大貫に声をかける。
「明日、私の職場に来ない?」