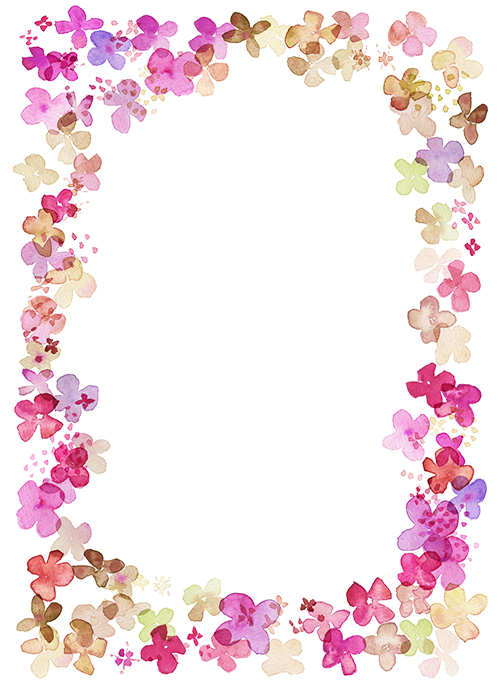「純粋に、楽しい話や嬉しかったことも伝えていれば良かったんでしょうけど、毎日ゆとりがなかったなって反省しました」
「でも、俺は今の藤宮さんしか知らないから、すごく感じの良いひとだなって思うよ」
「ありがとうございます……」
こんな風に直截的な言葉で褒められることは、多くない。それも、一度ならず二度までも。
どこまで本気なのかわからない真っ直ぐな言葉に、何と返せば良いのかわからず、視線を彷徨わせる。
目を逸らしても、鷺沼の目が美咲を見つめているのがわかって、心臓がどぎまぎと音を立てていた。
「あ」
ふと、思いついて美咲は顔を上げた。
「そういえば、こう考えられるようになったのは、ポッドキャストのおかげもあるかもしれないです」
「え?」
「週に三回、日常で出会った良かったことを、幸せのかけらとして語ってくれる番組があるんです。私、この番組に出会ってから、自分でも幸せのかけら集めをしていて。といっても、ちょっといいなって思ったことをノートにメモしておくくらいなんですけど。でも、毎日『何か書けることないかな』って探して生活しているだけで、ずいぶんポジティブになれました。あと、お話されているのが、男性の方なんですけど、低くてとっても耳障りの良い声なんですよ! 私はその人の考え方にも影響を受けましたけど、ただ流すだけでもおすすめです。多分、良く眠れると思います」
「……へえ」
鷺沼は短く相槌を打つと、そのまま黙ってしまった。美咲はちらりとその整った顔を仰ぎ見る。
機嫌を害したわけではなさそうだけれど、もうしゃべる気はない、と言わんばかりに鷺沼は口を噤んでいた。
何か、気に触ることを言っただろうか。それとも、あまりに夢中で番組のことを話しすぎた?
確かに、このお気に入りのポッドキャストのことを誰かに喋るのが初めてだったから、ついつい熱が入ってしまった自覚はある。
どうしよう、余計なことを言ってごめんなさい、と謝ったほうが良いだろうか、と美咲が考えていると、
「じゃあ、俺、コーヒー買って戻るので」
鷺沼は美咲のことを見ることなく、すっと離れてそのままコーヒーチェーン店の方へと足を向けた。美咲が返事をする前に、鷺沼が潜った自動ドアが閉まった。
その後ろ姿はまるで、美咲との間に見えない壁を造ったような、そんな感覚に陥った。
「でも、俺は今の藤宮さんしか知らないから、すごく感じの良いひとだなって思うよ」
「ありがとうございます……」
こんな風に直截的な言葉で褒められることは、多くない。それも、一度ならず二度までも。
どこまで本気なのかわからない真っ直ぐな言葉に、何と返せば良いのかわからず、視線を彷徨わせる。
目を逸らしても、鷺沼の目が美咲を見つめているのがわかって、心臓がどぎまぎと音を立てていた。
「あ」
ふと、思いついて美咲は顔を上げた。
「そういえば、こう考えられるようになったのは、ポッドキャストのおかげもあるかもしれないです」
「え?」
「週に三回、日常で出会った良かったことを、幸せのかけらとして語ってくれる番組があるんです。私、この番組に出会ってから、自分でも幸せのかけら集めをしていて。といっても、ちょっといいなって思ったことをノートにメモしておくくらいなんですけど。でも、毎日『何か書けることないかな』って探して生活しているだけで、ずいぶんポジティブになれました。あと、お話されているのが、男性の方なんですけど、低くてとっても耳障りの良い声なんですよ! 私はその人の考え方にも影響を受けましたけど、ただ流すだけでもおすすめです。多分、良く眠れると思います」
「……へえ」
鷺沼は短く相槌を打つと、そのまま黙ってしまった。美咲はちらりとその整った顔を仰ぎ見る。
機嫌を害したわけではなさそうだけれど、もうしゃべる気はない、と言わんばかりに鷺沼は口を噤んでいた。
何か、気に触ることを言っただろうか。それとも、あまりに夢中で番組のことを話しすぎた?
確かに、このお気に入りのポッドキャストのことを誰かに喋るのが初めてだったから、ついつい熱が入ってしまった自覚はある。
どうしよう、余計なことを言ってごめんなさい、と謝ったほうが良いだろうか、と美咲が考えていると、
「じゃあ、俺、コーヒー買って戻るので」
鷺沼は美咲のことを見ることなく、すっと離れてそのままコーヒーチェーン店の方へと足を向けた。美咲が返事をする前に、鷺沼が潜った自動ドアが閉まった。
その後ろ姿はまるで、美咲との間に見えない壁を造ったような、そんな感覚に陥った。