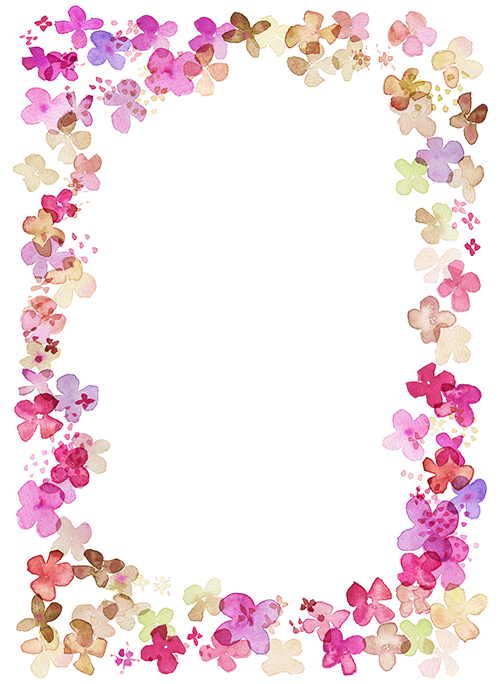翌日のことだった。
同じ時間にコーヒーを淹れていると、また鷺沼が姿を現した。
その手には、シルバーのシンプルなタンブラーが握られていた。たっぷり入りそうな大きさのそれを見せてくる鷺沼は、どこか嬉しそうだ。
「飲み終わったら、ここのドリップコーヒー使ってくださいね。まだまだありますから」
「藤宮さんの楽しみを減らすようで悪い気がするけど」
「もう、私だけのコーヒーじゃないんですよ。社員みんなのなんですから、飲んでください」
「はは。わかった。あとで淹れにくる」
そう言って給湯室を出て行こうとした鷺沼は、ふと足を止めた。
「そうだ、これ。昨日渡そうと思ってたんだけど」
そう言って差し出されたのは、つややかな満月のようなマドレーヌだった。
「え……?」
「昨日来た取引先がくれたんだけど、よかったら」
「え、いいんですか……?」
高級感のあるロゴには見覚えがあった。デパートの地下で何時間待ちにもなるという、有名店のマドレーヌだ。
「もちろん。俺、甘いものそんなに得意じゃないから」
「あ、ありがとうございます。嬉しいです」
「そんなに喜んでもらえるならあげた甲斐があるよ」
そう言われて、緩んだ口元を抑える。
「これで今日の残業も頑張れそうです」
「よかった。じゃあ」
今度こそ鷺沼は去っていく。その後ろ姿を見送りながら、冷酷王子なんていったいどこからそんなあだ名がついたのだろう、と美咲は首を傾げたのだった。
幸せのかけらを記したノートに、毎日鷺沼のことばかり増えていく。忙しいせいで、毎日必死に絞り出さなくて済むのは助かった。
けれどあまりに突然、鷺沼のことばかりが増えたから、違和感を覚えてしまう。何より自分の文字が、疲れているはずなのに浮かれている。
こんなに突然距離が縮んで、意識をするなという方が無理がある。しかも他の女性社員には相変わらずの塩対応なのだ。まるで自分にだけ優しくしてくれるのでは、と思ってしまうのを止められない。
話しやすい、と思ってもらっているようだから、ひとりの人として、親しみを覚えてくれているだけだ、とそう言い聞かせる。
そもそも鷺沼は好きな人から投げかけられた言葉がショックで、社内で恋愛をするつもりはないと言っていた。そのことを思い出して、がつんと頭を殴られたような衝撃が走った。そうだ。鷺沼は会社の人を好きになることはないと言っていた。余計な気持ちを抱いたら、せっかく信用してもらったのにそれすら裏切ることになる。
美咲はペンを握ったまま止まっていた。気づけば二十二時を過ぎていて、慌ててポッドキャストをつける。
穏やかな声によって語られる幸せのかけらは、いつも通りのあたたかさを感じさせるものだったのに、美咲の頭のなかを滑っていくばかりで、そのまま消えてしまったのだった。
同じ時間にコーヒーを淹れていると、また鷺沼が姿を現した。
その手には、シルバーのシンプルなタンブラーが握られていた。たっぷり入りそうな大きさのそれを見せてくる鷺沼は、どこか嬉しそうだ。
「飲み終わったら、ここのドリップコーヒー使ってくださいね。まだまだありますから」
「藤宮さんの楽しみを減らすようで悪い気がするけど」
「もう、私だけのコーヒーじゃないんですよ。社員みんなのなんですから、飲んでください」
「はは。わかった。あとで淹れにくる」
そう言って給湯室を出て行こうとした鷺沼は、ふと足を止めた。
「そうだ、これ。昨日渡そうと思ってたんだけど」
そう言って差し出されたのは、つややかな満月のようなマドレーヌだった。
「え……?」
「昨日来た取引先がくれたんだけど、よかったら」
「え、いいんですか……?」
高級感のあるロゴには見覚えがあった。デパートの地下で何時間待ちにもなるという、有名店のマドレーヌだ。
「もちろん。俺、甘いものそんなに得意じゃないから」
「あ、ありがとうございます。嬉しいです」
「そんなに喜んでもらえるならあげた甲斐があるよ」
そう言われて、緩んだ口元を抑える。
「これで今日の残業も頑張れそうです」
「よかった。じゃあ」
今度こそ鷺沼は去っていく。その後ろ姿を見送りながら、冷酷王子なんていったいどこからそんなあだ名がついたのだろう、と美咲は首を傾げたのだった。
幸せのかけらを記したノートに、毎日鷺沼のことばかり増えていく。忙しいせいで、毎日必死に絞り出さなくて済むのは助かった。
けれどあまりに突然、鷺沼のことばかりが増えたから、違和感を覚えてしまう。何より自分の文字が、疲れているはずなのに浮かれている。
こんなに突然距離が縮んで、意識をするなという方が無理がある。しかも他の女性社員には相変わらずの塩対応なのだ。まるで自分にだけ優しくしてくれるのでは、と思ってしまうのを止められない。
話しやすい、と思ってもらっているようだから、ひとりの人として、親しみを覚えてくれているだけだ、とそう言い聞かせる。
そもそも鷺沼は好きな人から投げかけられた言葉がショックで、社内で恋愛をするつもりはないと言っていた。そのことを思い出して、がつんと頭を殴られたような衝撃が走った。そうだ。鷺沼は会社の人を好きになることはないと言っていた。余計な気持ちを抱いたら、せっかく信用してもらったのにそれすら裏切ることになる。
美咲はペンを握ったまま止まっていた。気づけば二十二時を過ぎていて、慌ててポッドキャストをつける。
穏やかな声によって語られる幸せのかけらは、いつも通りのあたたかさを感じさせるものだったのに、美咲の頭のなかを滑っていくばかりで、そのまま消えてしまったのだった。