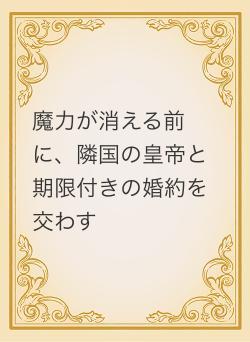(やっぱり親切な人だな……)
あそこで転んでいたら、ドレスを汚し、お花を潰していたことだろう。助けてもらえてよかった。私は左目に傷のある男性にすっかり気を許してしまっていた。
「外から戻られたんですか?」
「うん……」
「侵攻がなくても警戒を続けているんですね。」
「油断すると攻撃されるから。」
「敵国の侵攻って頻繁にあるものなんですか?」
「まぁね。」
王都にいた時は遠いところで起きているものだった。でも、ここでは常に戦場が隣り合わせだ。
「目の傷は、戦った時のものですか?」
男性は少しだけ目を見開いた。聞いてはいけなかったと思ったが、遅かった。
「これは……剣を覚えるときに受けた傷なんだ。名誉の負傷じゃない。」
男性は肩をすくませて笑った。まるで後ろめたいことのように思っているのだろうか。剣士の心得は私にはわからない。だけど──
「もっと自信を持った方がいいと思います。」
「えっ?」
「傷を負ってまで剣を習得されたのは、国を守るためですよね?私にはできませんし、他の人だって真似できないことだと思います。その傷は国を守っている証です。誇りを持っていいと思います。」
「…………うん。ありがとう。」
男性は少しだけ笑った。何も知らない小娘が大きな口を叩いてしまったという自覚はあるけれど、言わずにはいられなかった。
「ここが君の部屋。」
「ありがとうございました、助かりました。」
支えのように握りしめていた男性の腕を離すと、そのまま手を握られた。
「アリシア……?」
名前を呼ばれると、急に心臓がドキドキし始めた。手を離そうとしても、男性は手を離してくれない。
「あ……あの、私、名前を聞いていませんでした。」
「クロードだよ。」
「ありがとうございました、クロードさん。」
「うん……」
クロードさんは、じっと私を見つめたまま手を握りしめている。
「クロードさん?」
「なに?」
「手を離してもらっても……」
「あ!ごめん……」
クロードさんは私の手をぱっと離した。握っていた自覚がなかったのだろうか。
「アリシア……あの……け、結婚の話……なんだけど……」
「やっぱりだめでしたか?」
「ん?」
「まだ辺境伯様とお会いしていないんです。だから……」
「俺は結婚したい。君が好きだ。」
「??」
首を傾げると、廊下の向こうからマーシャとたくさんの使用人たちが歩いてきた。
「お帰りなさいませ、旦那様!」
私の視線はマーシャとクロードさんの間を行ったり来たりした。
「アリシア様、こちらが悪魔と名高いヴェルシュタールの辺境伯、クロード様です!」
(え─────!!??)
使用人たちは大袈裟にパチパチと拍手をしている。顔に体の熱が全て集結して、私は思わず両手で顔を覆い隠した。
あそこで転んでいたら、ドレスを汚し、お花を潰していたことだろう。助けてもらえてよかった。私は左目に傷のある男性にすっかり気を許してしまっていた。
「外から戻られたんですか?」
「うん……」
「侵攻がなくても警戒を続けているんですね。」
「油断すると攻撃されるから。」
「敵国の侵攻って頻繁にあるものなんですか?」
「まぁね。」
王都にいた時は遠いところで起きているものだった。でも、ここでは常に戦場が隣り合わせだ。
「目の傷は、戦った時のものですか?」
男性は少しだけ目を見開いた。聞いてはいけなかったと思ったが、遅かった。
「これは……剣を覚えるときに受けた傷なんだ。名誉の負傷じゃない。」
男性は肩をすくませて笑った。まるで後ろめたいことのように思っているのだろうか。剣士の心得は私にはわからない。だけど──
「もっと自信を持った方がいいと思います。」
「えっ?」
「傷を負ってまで剣を習得されたのは、国を守るためですよね?私にはできませんし、他の人だって真似できないことだと思います。その傷は国を守っている証です。誇りを持っていいと思います。」
「…………うん。ありがとう。」
男性は少しだけ笑った。何も知らない小娘が大きな口を叩いてしまったという自覚はあるけれど、言わずにはいられなかった。
「ここが君の部屋。」
「ありがとうございました、助かりました。」
支えのように握りしめていた男性の腕を離すと、そのまま手を握られた。
「アリシア……?」
名前を呼ばれると、急に心臓がドキドキし始めた。手を離そうとしても、男性は手を離してくれない。
「あ……あの、私、名前を聞いていませんでした。」
「クロードだよ。」
「ありがとうございました、クロードさん。」
「うん……」
クロードさんは、じっと私を見つめたまま手を握りしめている。
「クロードさん?」
「なに?」
「手を離してもらっても……」
「あ!ごめん……」
クロードさんは私の手をぱっと離した。握っていた自覚がなかったのだろうか。
「アリシア……あの……け、結婚の話……なんだけど……」
「やっぱりだめでしたか?」
「ん?」
「まだ辺境伯様とお会いしていないんです。だから……」
「俺は結婚したい。君が好きだ。」
「??」
首を傾げると、廊下の向こうからマーシャとたくさんの使用人たちが歩いてきた。
「お帰りなさいませ、旦那様!」
私の視線はマーシャとクロードさんの間を行ったり来たりした。
「アリシア様、こちらが悪魔と名高いヴェルシュタールの辺境伯、クロード様です!」
(え─────!!??)
使用人たちは大袈裟にパチパチと拍手をしている。顔に体の熱が全て集結して、私は思わず両手で顔を覆い隠した。