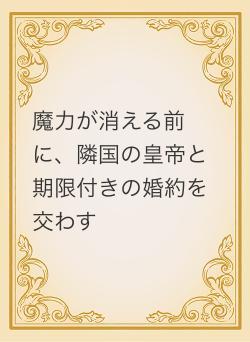辺境伯様のお屋敷を訪ねるのは1週間後。だけど、王都からヴェルシュタールまでは騎士でも丸2日かかる距離にある。夜間は宿屋でちゃんと休み、日が高い間に馬を進めると考えると、3日は必要だ。出発の日は、あっという間にやってきた。
「父さん、みんなと仲良くね。喧嘩しちゃだめだからね。」
「心配するな。母さんのこともな。」
こんな小さな村でヴェルシュタールへ行くなんて言ったら大騒ぎになってしまう。私は夜が明ける前に、静かに家を出た。
「すまない、アリシア……お前にこんな思いをさせるために育ててきたわけじゃないんだが……」
「泣かないで、父さん。ヴェルシュタールに行っても追い返されちゃうかもしれないんだから。」
辺境伯様はまさかこんな貧乏な家の娘が来るとは思っていないだろう。門前払いされて、会った日に帰って来ることになるかもしれない。
「宿屋は覚えているか?陽が出ているうちにできるだけ進んで、夜は必ず休むんだぞ?」
「何度も確認したもの、大丈夫よ。行ってくるわね。」
私は父が借りてきた立派な馬に跨った。
「さあ、行くわよ。よろしくね!」
手綱を握ると、馬はゆっくり歩き始めた。振り返ると父は小さく手を振っていた。私は手を振り返して、慣れ親しんだ故郷を目に焼き付けた。
「走って!」
父の姿が見えなくなると、私は勢いよく馬を走らせた。涼しい風が吹き抜けていく。おかげで涙を流さずに済んだ。
「泣いてる場合じゃないわ。早く最初の宿屋へ行かないと!」
畑仕事を手伝っていたから体力はあるけれど、油断していたら間に合わない。その日はほとんど休憩も取らずに走り続けた。
1日目に滞在する宿屋の女将さんは、私を特別な客のようにもてなしてくれた。貧乏な客にはそれなりの対応しかしてくれないものだと思っていたから意外だった。
「お代はお父様から頂いておりますからね。」
にこやかに微笑む女将さんの顔を見て、私は父がヴェルシュタールまでの旅を念入りに計画していたことを知った。
2日目も夜が明ける前に宿屋を出て、日中はひたすら馬を走らせた。日が暮れる頃に次の宿屋が見えてきた。
「あそこの女将さんは、少しクセがあるって言ってたな……」
私は呼吸を整えてから宿屋へ向かった。
「女の子が1人でヴェルシュタールへ!?あそこは女の子が行く場所じゃないわ!何の用があるの!?」
ヴェルシュタールは戦地で女性が単身で行くことは珍しい。疑問に思われるのも無理はない。
「父に代わって、お花の苗を受け取りに来たんです。」
「あら、お花屋さんだったのね!」
父に言われていた通りに答えると、女将さんは安堵したように微笑んだ。親の手伝いだと言えば怪しまれないというのが、父の仕入れた情報だった。
「あなた、その格好で行くつもり?ヴェルシュタールは寒いわよ。これを着て行きなさい。あー返さなくていいわ。お父さんからお代は頂いてるから。」
「ありがとうございます。」
私は女将さんからもらったフードのついた黒いローブを羽織って、夜が明ける前に出発した。
宿から続く道をひたすら進んでいくと、薄暗い森が現れた。森の中から吹いてくる風は、ひんやりとして冷たい。この森を抜けるとヴェルシュタールだ。
「……よし。」
私は手綱を握りしめた。森の中を進んでいくにつれて、どんどん寒くなっていく。私は思わず体を震わせた。
「女将さんにもらってよかった……」
ローブがなかったら、耐えられなかったかもしれない。私はフードをかぶり、襟元を締めて森を抜けた。
「ここがヴェルシュタール……!」
遠くまで続く大地には、野菜や果物、花などの畑が広がっている。思っていたよりずっと長閑だ。
「辺境伯様のお屋敷はあそこか……」
監視塔のある要塞のような建物が悠然と立っている。長閑な風景の中で、お屋敷のある場所だけが異質に見えた。
「もうすぐよ、がんばろうね!」
声をかけたけれど、馬の足はだんだん遅くなり、そのうち立ち止まってしまった。父が借りてくれた馬は、強靭な肉体を持つ長距離用の馬で、ほぼ休むことなく走り続けてくれた。だけど、この寒さで限界が来てしまったらしい。
私も馬も吐く息が白い。まだ昼間だというのに空は暗く、今にも雪が降り出しそうだ。早く行きたいけれど、馬に無理をさせるわけにもいかない。
「ちょっと休んでからにしようか。」
馬を降りて、いざという時のために持ってきたエサを食べさせた。一呼吸置くと、道の向こうから馬が走ってくるのが見えた。
(来た……)
『ヴェルシュタールは監視の目が厳しい。領内に足を踏み入れたら、必ず監視役に声をかけられる。』
父の言葉を思い出して、私はローブを握りしめた。
「父さん、みんなと仲良くね。喧嘩しちゃだめだからね。」
「心配するな。母さんのこともな。」
こんな小さな村でヴェルシュタールへ行くなんて言ったら大騒ぎになってしまう。私は夜が明ける前に、静かに家を出た。
「すまない、アリシア……お前にこんな思いをさせるために育ててきたわけじゃないんだが……」
「泣かないで、父さん。ヴェルシュタールに行っても追い返されちゃうかもしれないんだから。」
辺境伯様はまさかこんな貧乏な家の娘が来るとは思っていないだろう。門前払いされて、会った日に帰って来ることになるかもしれない。
「宿屋は覚えているか?陽が出ているうちにできるだけ進んで、夜は必ず休むんだぞ?」
「何度も確認したもの、大丈夫よ。行ってくるわね。」
私は父が借りてきた立派な馬に跨った。
「さあ、行くわよ。よろしくね!」
手綱を握ると、馬はゆっくり歩き始めた。振り返ると父は小さく手を振っていた。私は手を振り返して、慣れ親しんだ故郷を目に焼き付けた。
「走って!」
父の姿が見えなくなると、私は勢いよく馬を走らせた。涼しい風が吹き抜けていく。おかげで涙を流さずに済んだ。
「泣いてる場合じゃないわ。早く最初の宿屋へ行かないと!」
畑仕事を手伝っていたから体力はあるけれど、油断していたら間に合わない。その日はほとんど休憩も取らずに走り続けた。
1日目に滞在する宿屋の女将さんは、私を特別な客のようにもてなしてくれた。貧乏な客にはそれなりの対応しかしてくれないものだと思っていたから意外だった。
「お代はお父様から頂いておりますからね。」
にこやかに微笑む女将さんの顔を見て、私は父がヴェルシュタールまでの旅を念入りに計画していたことを知った。
2日目も夜が明ける前に宿屋を出て、日中はひたすら馬を走らせた。日が暮れる頃に次の宿屋が見えてきた。
「あそこの女将さんは、少しクセがあるって言ってたな……」
私は呼吸を整えてから宿屋へ向かった。
「女の子が1人でヴェルシュタールへ!?あそこは女の子が行く場所じゃないわ!何の用があるの!?」
ヴェルシュタールは戦地で女性が単身で行くことは珍しい。疑問に思われるのも無理はない。
「父に代わって、お花の苗を受け取りに来たんです。」
「あら、お花屋さんだったのね!」
父に言われていた通りに答えると、女将さんは安堵したように微笑んだ。親の手伝いだと言えば怪しまれないというのが、父の仕入れた情報だった。
「あなた、その格好で行くつもり?ヴェルシュタールは寒いわよ。これを着て行きなさい。あー返さなくていいわ。お父さんからお代は頂いてるから。」
「ありがとうございます。」
私は女将さんからもらったフードのついた黒いローブを羽織って、夜が明ける前に出発した。
宿から続く道をひたすら進んでいくと、薄暗い森が現れた。森の中から吹いてくる風は、ひんやりとして冷たい。この森を抜けるとヴェルシュタールだ。
「……よし。」
私は手綱を握りしめた。森の中を進んでいくにつれて、どんどん寒くなっていく。私は思わず体を震わせた。
「女将さんにもらってよかった……」
ローブがなかったら、耐えられなかったかもしれない。私はフードをかぶり、襟元を締めて森を抜けた。
「ここがヴェルシュタール……!」
遠くまで続く大地には、野菜や果物、花などの畑が広がっている。思っていたよりずっと長閑だ。
「辺境伯様のお屋敷はあそこか……」
監視塔のある要塞のような建物が悠然と立っている。長閑な風景の中で、お屋敷のある場所だけが異質に見えた。
「もうすぐよ、がんばろうね!」
声をかけたけれど、馬の足はだんだん遅くなり、そのうち立ち止まってしまった。父が借りてくれた馬は、強靭な肉体を持つ長距離用の馬で、ほぼ休むことなく走り続けてくれた。だけど、この寒さで限界が来てしまったらしい。
私も馬も吐く息が白い。まだ昼間だというのに空は暗く、今にも雪が降り出しそうだ。早く行きたいけれど、馬に無理をさせるわけにもいかない。
「ちょっと休んでからにしようか。」
馬を降りて、いざという時のために持ってきたエサを食べさせた。一呼吸置くと、道の向こうから馬が走ってくるのが見えた。
(来た……)
『ヴェルシュタールは監視の目が厳しい。領内に足を踏み入れたら、必ず監視役に声をかけられる。』
父の言葉を思い出して、私はローブを握りしめた。