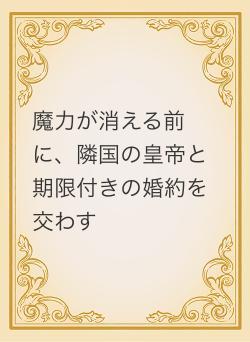「アリシア、これを見てくれないか。」
深刻な顔をした父は、貧相な家には似つかわしくない上質な紙をテーブルの上に広げた。
「これは何?」
「国王陛下からの書状だ。ヴェルシュタールの辺境伯様と結婚するようにと書いてある。」
私は驚いて紙を手に取った。確かにそう書かれている。だけど──
「父さん、これって本物なの?偽物ってことはない?」
私の家は、王都のはずれにあるお世辞にも綺麗とは言えない小さな小屋。畑を耕して、近所の手伝いをしてなんとか生計を立てている。そんな私が辺境伯様と結婚だなんて、身分が釣り合わない。
「この手紙を届けてくれたのは、お城の人だったんだ。何度も聞いたが、家で間違いないと言うんだよ。でもやっぱりおかしい。明日、城へ行って聞いてみよう。」
ヴェルシュタールの辺境伯といえば、城で何度も聞いた悪魔と噂される人物。そんな人と突然結婚しろなんて言われても──再び手紙に視線を落とした私は目を見開いた。
「子爵って書いてある……!」
「ははは、そうなんだ。そんな風に呼ばれたのは生まれて初めてだよ。」
遠い昔、父から爵位を持っているという話を聞いたことがある。冗談だと思ったいたけれど、本当だったらしい。
「だから手紙が来たのね。私のこと、陛下は貴族の令嬢だと思っているんだわ。」
「あぁ、そういうことか。」
父は納得したように頷いた。
「辺境伯様から手紙が来ても、ちゃんとした貴族のご令嬢はお断りしてるんでしょうね。」
「ははは、だから私のところに手紙が来たというわけか。」
「たぶんね。」
辺境伯様は『悪魔』だなんて呼ばれてるし、嫁ぎ先は戦地ヴェルシュタール。そんなところへお嫁に行きたいと思う人はいないだろう。
「そういうことなら簡単だ。城へ行って我が家の状況を説明して来る。そうすれば、陛下も取り下げてくださるだろう。」
父は手紙をくるくると丸めて立ち上がった。
「母さんのところへ行ってくるよ。」
「わかった。」
病にかかった母は、数か月前から遠い親戚を頼って離れた場所で療養している。だけど、お金がないから大した治療はできていない。このままじゃ母は──
「父さん……」
「なんだい?」
「私が結婚すれば、母さんの病気も治せるかな……」
父は小さくため息をついた。
「そんなことは考えなくていい。」
「でも今のままじゃ、母さんはずっと良くならない。」
お金があれば母は治療を受けることができる。父と一緒にこの家で暮らすことができるようになるかもしれない。
「父さん、私、ヴェルシュタールへ行く。辺境伯様と話をしてみるわ。」
「アリシア、ヴェルシュタールは戦地なんだ。何があるかわからないんだよ?」
「辺境伯様は『悪魔』と呼ばれるほど強いのよ。それに、国王陛下の命令に背いたら罰を受けるかもしれないでしょ?」
「アリシア……」
「ほら、母さんのところへ行くんでしょ?いってらっしゃい。」
父を見送った後、私は家の外に出て大きく息を吸い込んだ。森の木や畑の野菜が風に揺れている。この景色は、私が大好きな風景だ。
「大丈夫……大丈夫よ……」
国王陛下の手紙には、1週間後にヴェルシュタールへ出向くようにと書かれていた。この風景を見られるのはあと少し。そう思ったら、視界が歪んで涙となって落ちた。
好きな人と結婚して、たまに両親がいる実家に戻ってきて懐かしい仲間たちに囲まれて昔話をする。そんな生活が当たり前のようにやってくると思っていた。
「母さんを助けるためよ……絶対大丈夫だから……」
遠くから近所の花屋さんが歩いて来るのが見えて、私はゴシゴシと涙を拭った。
深刻な顔をした父は、貧相な家には似つかわしくない上質な紙をテーブルの上に広げた。
「これは何?」
「国王陛下からの書状だ。ヴェルシュタールの辺境伯様と結婚するようにと書いてある。」
私は驚いて紙を手に取った。確かにそう書かれている。だけど──
「父さん、これって本物なの?偽物ってことはない?」
私の家は、王都のはずれにあるお世辞にも綺麗とは言えない小さな小屋。畑を耕して、近所の手伝いをしてなんとか生計を立てている。そんな私が辺境伯様と結婚だなんて、身分が釣り合わない。
「この手紙を届けてくれたのは、お城の人だったんだ。何度も聞いたが、家で間違いないと言うんだよ。でもやっぱりおかしい。明日、城へ行って聞いてみよう。」
ヴェルシュタールの辺境伯といえば、城で何度も聞いた悪魔と噂される人物。そんな人と突然結婚しろなんて言われても──再び手紙に視線を落とした私は目を見開いた。
「子爵って書いてある……!」
「ははは、そうなんだ。そんな風に呼ばれたのは生まれて初めてだよ。」
遠い昔、父から爵位を持っているという話を聞いたことがある。冗談だと思ったいたけれど、本当だったらしい。
「だから手紙が来たのね。私のこと、陛下は貴族の令嬢だと思っているんだわ。」
「あぁ、そういうことか。」
父は納得したように頷いた。
「辺境伯様から手紙が来ても、ちゃんとした貴族のご令嬢はお断りしてるんでしょうね。」
「ははは、だから私のところに手紙が来たというわけか。」
「たぶんね。」
辺境伯様は『悪魔』だなんて呼ばれてるし、嫁ぎ先は戦地ヴェルシュタール。そんなところへお嫁に行きたいと思う人はいないだろう。
「そういうことなら簡単だ。城へ行って我が家の状況を説明して来る。そうすれば、陛下も取り下げてくださるだろう。」
父は手紙をくるくると丸めて立ち上がった。
「母さんのところへ行ってくるよ。」
「わかった。」
病にかかった母は、数か月前から遠い親戚を頼って離れた場所で療養している。だけど、お金がないから大した治療はできていない。このままじゃ母は──
「父さん……」
「なんだい?」
「私が結婚すれば、母さんの病気も治せるかな……」
父は小さくため息をついた。
「そんなことは考えなくていい。」
「でも今のままじゃ、母さんはずっと良くならない。」
お金があれば母は治療を受けることができる。父と一緒にこの家で暮らすことができるようになるかもしれない。
「父さん、私、ヴェルシュタールへ行く。辺境伯様と話をしてみるわ。」
「アリシア、ヴェルシュタールは戦地なんだ。何があるかわからないんだよ?」
「辺境伯様は『悪魔』と呼ばれるほど強いのよ。それに、国王陛下の命令に背いたら罰を受けるかもしれないでしょ?」
「アリシア……」
「ほら、母さんのところへ行くんでしょ?いってらっしゃい。」
父を見送った後、私は家の外に出て大きく息を吸い込んだ。森の木や畑の野菜が風に揺れている。この景色は、私が大好きな風景だ。
「大丈夫……大丈夫よ……」
国王陛下の手紙には、1週間後にヴェルシュタールへ出向くようにと書かれていた。この風景を見られるのはあと少し。そう思ったら、視界が歪んで涙となって落ちた。
好きな人と結婚して、たまに両親がいる実家に戻ってきて懐かしい仲間たちに囲まれて昔話をする。そんな生活が当たり前のようにやってくると思っていた。
「母さんを助けるためよ……絶対大丈夫だから……」
遠くから近所の花屋さんが歩いて来るのが見えて、私はゴシゴシと涙を拭った。