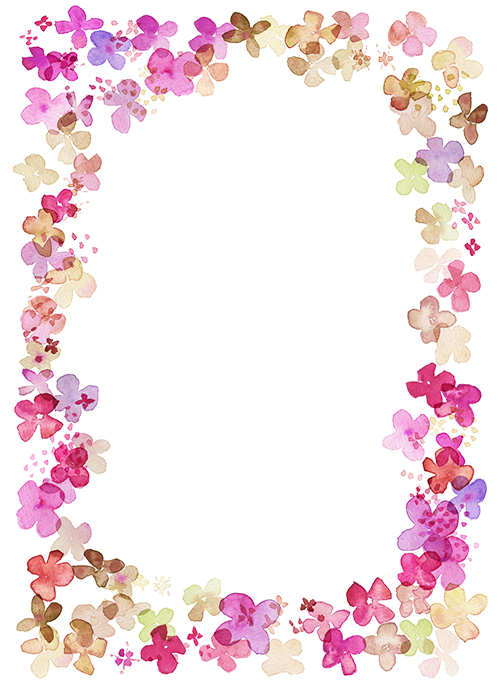俺は思わず息を呑んだ。
ワンショルダーの清楚な桜色のドレス。脚をかくすほど長い。Aラインに似ているがすそがほんの少し広がる。
髪はきっちりとした夜会巻きになっている。なんと表現すれば良いのか……
さおりさんは手に銀色のフルートを持っていた。ピアニストとしてさおりさんと仲の良い同い年の先生が現れた。ふたりで深々とお辞儀をするが、俺はさおりさんから目を離せない。
さおりさんがフルートを口に当てる。ピアニストと目で合図をしあい、最初の一音を、魂を愛器に吹き込む。
優しくあたたかく包まれるような音色だった。曲名はわからない。さおりさんは家で楽器の練習をしないから。
とてもほっこりする。小さい頃からずっとお気に入りの毛布にくるまれているような安心感と同時に、小さい頃の孤独だった自分を思い出して切なくなった。
- おまえ、何考えてんのかわかんない。
- 本ばっか読んで。何様だよ。
いじめられていたわけではない。だが、小さい頃の俺はずっとずっと心の中に寂しさを抱えていた。その寂しさは年々硬度を増し、胸の中でずっしりと重くなった。つき過ぎて取れなくなったぜい肉のように。
年を重ねてそれなりの処世術や作り笑顔も身につけ、表面上は孤独ではなくなったし、友だちもできたけれど、
さおりさんのフルートを初めて聴いたとき、思ったんだ。
(あ、俺、
孤独な自分を肯定して良い)
孤独なのは弱いことではない。悪いことでもない。それによってたくさんの本が読めたし、たくさんのことを学べた。
今では、最愛の妻がそばにいてくれる。世界一大好きなさおりさんが、毎日、俺といっしょにいてくれる。
(癒されるなぁ)
見惚れてしまいます。さおりさん。あなたに。
ただ、目が自然にあなたを追ってしまいます。それは恋だ。
ワンショルダーの清楚な桜色のドレス。脚をかくすほど長い。Aラインに似ているがすそがほんの少し広がる。
髪はきっちりとした夜会巻きになっている。なんと表現すれば良いのか……
さおりさんは手に銀色のフルートを持っていた。ピアニストとしてさおりさんと仲の良い同い年の先生が現れた。ふたりで深々とお辞儀をするが、俺はさおりさんから目を離せない。
さおりさんがフルートを口に当てる。ピアニストと目で合図をしあい、最初の一音を、魂を愛器に吹き込む。
優しくあたたかく包まれるような音色だった。曲名はわからない。さおりさんは家で楽器の練習をしないから。
とてもほっこりする。小さい頃からずっとお気に入りの毛布にくるまれているような安心感と同時に、小さい頃の孤独だった自分を思い出して切なくなった。
- おまえ、何考えてんのかわかんない。
- 本ばっか読んで。何様だよ。
いじめられていたわけではない。だが、小さい頃の俺はずっとずっと心の中に寂しさを抱えていた。その寂しさは年々硬度を増し、胸の中でずっしりと重くなった。つき過ぎて取れなくなったぜい肉のように。
年を重ねてそれなりの処世術や作り笑顔も身につけ、表面上は孤独ではなくなったし、友だちもできたけれど、
さおりさんのフルートを初めて聴いたとき、思ったんだ。
(あ、俺、
孤独な自分を肯定して良い)
孤独なのは弱いことではない。悪いことでもない。それによってたくさんの本が読めたし、たくさんのことを学べた。
今では、最愛の妻がそばにいてくれる。世界一大好きなさおりさんが、毎日、俺といっしょにいてくれる。
(癒されるなぁ)
見惚れてしまいます。さおりさん。あなたに。
ただ、目が自然にあなたを追ってしまいます。それは恋だ。