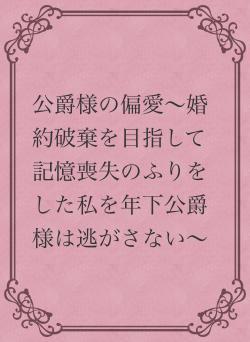「リーゼロッテ、君との婚約を破棄させてもらう」
王宮の応接室。
婚約者──いや、元婚約者となったロベルト殿下の言葉に、私はわずかに目を見開いた。
「聖女としての力を失った君では、もう僕には釣り合わない。だから、これからは君に代わって彼女が僕の新しい婚約者だ」
そう言って殿下は、隣に座る女性へと視線を向ける。彼女の名はソフィー。ローゼ男爵家のご令嬢だ。
……なるほど。以前からやけに距離が近いとは思っていたけれど、そういうことだったのね。
「ソフィーは男爵家の娘だが、光魔法が使える。父上も喜んで彼女を迎え入れてくださったよ」
殿下がソフィー様の肩を抱けば、彼女もまた恍惚とした表情で殿下を見つめる。
二人の世界に入り込む勢いは、もはや私など最初から存在していないかのようだ。あまりの甘さに、胸焼けしそうになる。
……できることなら、私がいないところでやってほしい。
そう思いながら、私は静かに立ち上がった。
「かしこまりました。これからは一国民として、殿下のご多幸を心よりお祈りいたします」
スカートの裾をつまみ、深く礼をする。
そして、一刻も早くこの場を去ろうと歩き出した、その時──。
「ああ、そうだ。言い忘れていたが、君にはルシファリア王国へ行ってもらう」
「……はい?」
「ルシファリア王国が、光魔法を使える人間の女を探しているらしくてな。多額の資金を支払ってでも欲しいと打診があった」
……この男は、一体何を言っているのだろう。
私とお金を交換だなんて、ほとんど人身売買ではないか。
思い切り嫌悪感が顔に出てしまったが、殿下はソフィー様に夢中で、私の表情など見てもいなかった。
今日ほど殿下が女にだらしなくてよかったと、思った日はない。
「我が国としても、魔族の多いあの国とは友好な関係を築きたいだろう? 君の両親も、国家のためだと喜んで送り出すと言ってくれたよ」
光魔法を使える人間は極めて少なく、魔族は扱えない。だから、ルシファリア王国が光魔法の使い手を求める理由はわかる。
……けれど、今の私は光魔法を扱えない。向こうにとって何の価値もないはずだ。
そう訴えても、殿下は軽く頷くだけだった。
「ああ、そうだな。今の君は光魔法も使えない、ただの無能な女だ。だが、この国で光魔法を扱えるのはソフィーと君だけなんだ」
「ですから──」
「まさか、ソフィーを野蛮な魔族の元へ行かせろと? 君はどれだけ非情な人間なんだ!」
その言葉と同時に殿下が勢いよく机を叩いた。大きな音が響いて、身体が小さく揺れる。
私を非情な人間だというなら、多額の資金と交換をして、私をその野蛮な魔族の元へと行かせる彼らだって、非情な人間ではないのだろうか。
しかし、まるで私だけが悪者だと言わんばかりに、ソフィー様は「リーゼロッテ様ったらひどいです……」と目を潤ませている。
そんな彼女を守るように、殿下は優しく慰めた。そして、鋭い視線を私へと向ける。
「そもそも、奴らは光魔法について詳しくない。適当に誤魔化しておけばいいだろう。とにかく、これは決定事項だから諦めろ」
吐き捨てるような声音で言われ、私はそれ以上何も返せなかった。
「最後にもう一つ。ルシファリアの王は、冷酷で残忍だと噂だ。……せいぜい、無能だとバレて殺されないよう気をつけたまえ」
殿下のその言葉に、ソフィー様が小馬鹿にしたように笑う。好かれているとは思っていなかったが、ここまで嫌われていたとは……。
その事実に少しだけ胸が痛んだが、気づかないふりをして、私はその場から立ち去った。
そうして、私は婚約破棄からの半ば追放という形でルシフェリア王国へと向かうこととなった。
ルシファリア王国へ到着したのは、夕日が沈みきる直前だった。
(ここがルシフェリア王国……)
昼間でも薄暗いと噂だが、夕暮れの今はさらに禍々しさが増している。どことなく異様なその雰囲気に、顔が強張るのがわかった。
(……だめだめ、ここまできたらもう腹を括るのよ)
震える足で馬車を降りると、出迎えてくれたのは獣耳の青年だった。琥珀色の瞳が鋭く私を見下ろしている。
「お前が、光魔法の使い手か?」
「え、ええっ……そうです……」
本当はもう使えないのだけど──今ここで正直に話せば、ロベルト殿下の言う通り、殺されてしまうかもしれない。
なので、必死に頷いていれば、青年は私を怪訝そうに見つめた後、「ついてこい」と歩き出した。
言われるがまま、青年の後をついていく。足の長い彼の歩幅に合わせていれば、すぐに息が上がってしまう。
すると、私の様子に気づいた彼がため息を漏らした。
「……ったく、弱い人間だな」
「す、すみません……」
冷たい物言いだが、その後からは私の歩幅に合わせてくれたのが分かった。その優しさに胸が温かくなる。
(怖いと思っていたが、優しいのね……)
それよりも、気になって仕方がないのが、彼の頭でぴょこぴょこと揺れるふわふわの耳だ。
こんなことを言ったら殺されそうだけど、とてもキュートだ。
(一度でいいから触らせてもらえないかな……)
そんなことを考えていれば、ルシフェリア王国の王城が視界に入った。
「いいか、人間。王に失礼のないようにしろよ」
「……はい」
何が失礼にあたるのかは分からない。だけど、多額の資金と交換した人間が光魔法どころか、初期魔法すら危ういような女な時点で、もうダメな気がする。
(ああ、もし殺されるならいっそ、ひと思いにお願いしたい)
そう祈っていれば、青年が門を押した。すると、ギィっと音を立てて、重厚な扉が開いた。
「これはこれは、ようこそお越しくださいました。リーゼロッテ様」
中から現れたのは、人懐っこい笑みを浮かべた青年だった。
一見、人間と変わらない容姿をしているが、わずかに尖った耳と口元でのぞく牙が、彼が魔族であることを教えてくれる。
「ルカくん、ご苦労様でしたー。後は僕にお任せを」
「……よろしくっス」
ルカと呼ばれた獣耳の青年が頭を下げると、すっと脇に退いた。どうやら、彼の案内はここまでらしい。
なので「ありがとうございました」と頭を下げると、琥珀色の瞳が驚いたように見開いた。
(え? 私、何か変なこと言った?)
「ささ、どうぞ中へ。僕は案内役のリエルと申します、以後お見知りおきを」
「よ、よろしくお願いします……」
私が小さく会釈をすると、リエルが満足げに頷き、軽い足取りで歩き出す。
彼の後を追って足を踏み入れた先は、どこまでも高い天井と真っ赤な絨毯が敷かれた廊下だった。
「ここが魔王城の中心通路です。少し長いので、迷わず僕についてきてくださいねー」
そう話すリエルの声は明るいのに、彼は足音一つしない。魔族特有の気配の消し方なのだろうか。
「魔王様はね、寛大なお方ですよ。……まあ、最初はちょっと怖いかもしれないですけどー」
「こ、怖いんですか……?」
「それは会ってからのお楽しみにしましょう」
軽い調子でかわされてしまい、返す言葉に困る。
そして、長い廊下の突き当たり、ある扉の前で彼は足を止めた。
「さあ、ここが魔王様がおられる場所です。心の準備はいいですか?」
ここまできたらもう逃げられない。そう思い、私はゆっくりと頷く。その様子にリエルがニヤリと笑い、扉に手を添えた。
途端、重たいはずの扉が音もなくゆっくりと開いた。
冷たい空気が頬を撫でる。広い空間の奥、漆黒の階段の上に彼は居た。
まるで血のような真っ赤な瞳と漆黒の長い髪、頭に生えた二本の角と尻尾。そして、人間離れした美しい容姿に、思わず息を呑んだ。
「……ようやく、来たか」
低く重い声が、胸の奥まで響く。
怒っているわけではないのに、全身が硬直するほどの威圧感だ。
(これがルシフェリア王国の王──ゼノン・ルシフェリア)
その圧倒的な存在感に何も言えずにいれば、彼はゆるりと立ち上がり、王座から降りてきた。
そして、その視線が、まっすぐ私に向けられた瞬間。
「……かわいい」
予想外の言葉が、その場に響き渡った。
(ん? いま、かわいいって言った?)
「よかったですねー、ゼノン様。リーゼロッテ様がお嫁に来てくれて」
(………嫁?!)
「……別に」
「またまた、照れちゃってー。あんなに楽しみにしていたではありませんかー」
「黙れ! 余計なことを言うな、リエル!」
ゼノン様の怒鳴り声がその場に響いた。しかし、リエルは、ニヤニヤと笑みを浮かべるだけ。
(さっきから私だけが話についていけてない……一体、どういうことなの?!)
二人のやり取りを困惑した様子で眺めていれば、やがて、私の視線に気がついたゼノン様と目が合う。
しかし、次の瞬間、ぷいっと視線を逸らされる。
何か不快な思いをさせてしまったのかと不安に思っていれば、リエルがこそっと耳打ちをした。
「すみませんね、リーゼロッテ様。ゼノン様はああ見えて照れ屋なものでして」
言われてみれば、ゼノン様の横顔は僅かに赤い。
「でも、ご安心を。貴女が花嫁として我が国にやってきて、とても喜んでおりますよー」
「は、はぁ……」
どうして、私が花嫁ということになっているのかは分からないが、歓迎されているのならよかった……のか?
未だ状況が飲み込めず、じっとゼノン様を見つめていれば、こちらに視線を向けた彼とまた目が合う。
しかし、今度は逸らされることがなかった。なので、私は薄らと微笑みを浮かべる。
すると、彼は尖った耳まで真っ赤にしたまま、口をはくはくと動かす。その初心な反応に思わず胸がキュッと音を立てた。
(待って、かわいいかも……?)
冷酷で残忍だと聞いていた彼の意外な一面を知って、私は思わず顔が緩んでしまったのだった。