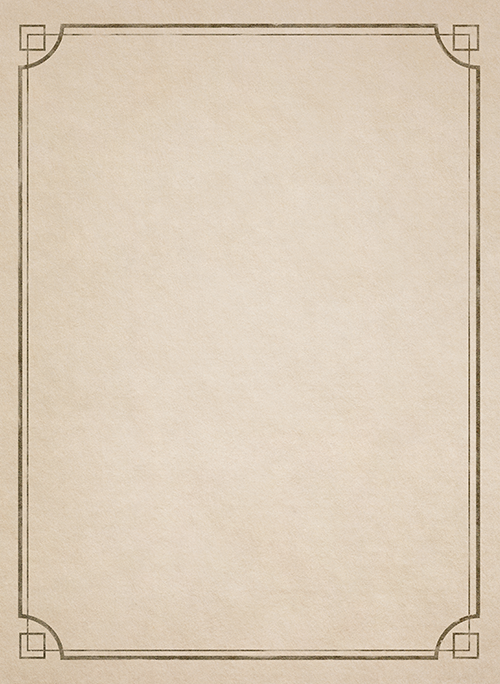チャイムが鳴って、ざわめく教室。
「起立、礼!」の声と同時に、椅子が一斉に引かれる音が重なる。
窓の外はオレンジ色。校庭の端で部活の声が響いていた。
「ふぅ、今日も長かったね」
都花がストレッチをしながら言うと、
理人がのんびり鞄を肩にかけた。
「おう。……あー、からかわれすぎて疲れたわ」
「ほんとだよ……“夫婦登校”とか、“朝からラブラブ”とか……!」
都花がぷくっと頬をふくらませると、理人は思わず笑った。
「でも、楽しそうだったじゃん?」
「たのしくないし!」
「はいはい、怒るな怒るな」
理人の余裕ある笑い方が、なんだかずるい。
そう思いながらも、都花は笑いをこらえきれず、肩をすくめた。
校門を出ると、秋の風が頬を撫でた。
空は少しだけ茜色を溶かしはじめていて、雲の端が金色に光っている。
いつもの帰り道。
でも今日はどこか、胸の奥がふわふわしていた。
「ねぇ、理人」
「ん?」
「……いよいよだね。明日」
その言葉に、理人の歩みがほんの少しだけゆっくりになる。
「……ああ。やっと帰ってくるな」
「二年ぶり、だもんね」
「仁奈、きっと最初びっくりするな」
「うん……覚えてないかもって心配してたもんね」
都花は夕焼けに照らされた理人の横顔を見上げた。
少し大人びて見えるその横顔に、胸がきゅっとなる。
「朔都はきっと覚えてるよ。あのとき、すごく甘えてたし」
「だな。……あいつ、明日テンション爆上がりだろうな」
「仁奈も“おめかしする!”とか言いそう」
「想像つく」
二人で笑い合いながら、並んで歩く。
通学路に伸びる影が、夕日に伸ばされて長く交わった。
ふと、都花がぽつりと言う。
「……なんかね、ちょっとだけドキドキする」
「なにが?」
「久しぶりに“家族”がそろうのが。嬉しいけど、うまく言えない気持ち」
理人は少し考えてから、小さくうなずいた。
「わかるよ。俺も、ちょっと緊張してる」
「理人でも?」
「おう。だってさ……俺たち、もう子どもじゃないし」
その言葉に、風が一瞬止まったように感じた。
都花は口を開きかけて、結局何も言えず、うつむいた。
すると理人が、ふっと笑って続ける。
「でも、まぁ。大丈夫だろ。俺ら、ちゃんとやってきたし」
「……そうだね」
「明日、みんなで笑って迎えようぜ」
「うん!」
「起立、礼!」の声と同時に、椅子が一斉に引かれる音が重なる。
窓の外はオレンジ色。校庭の端で部活の声が響いていた。
「ふぅ、今日も長かったね」
都花がストレッチをしながら言うと、
理人がのんびり鞄を肩にかけた。
「おう。……あー、からかわれすぎて疲れたわ」
「ほんとだよ……“夫婦登校”とか、“朝からラブラブ”とか……!」
都花がぷくっと頬をふくらませると、理人は思わず笑った。
「でも、楽しそうだったじゃん?」
「たのしくないし!」
「はいはい、怒るな怒るな」
理人の余裕ある笑い方が、なんだかずるい。
そう思いながらも、都花は笑いをこらえきれず、肩をすくめた。
校門を出ると、秋の風が頬を撫でた。
空は少しだけ茜色を溶かしはじめていて、雲の端が金色に光っている。
いつもの帰り道。
でも今日はどこか、胸の奥がふわふわしていた。
「ねぇ、理人」
「ん?」
「……いよいよだね。明日」
その言葉に、理人の歩みがほんの少しだけゆっくりになる。
「……ああ。やっと帰ってくるな」
「二年ぶり、だもんね」
「仁奈、きっと最初びっくりするな」
「うん……覚えてないかもって心配してたもんね」
都花は夕焼けに照らされた理人の横顔を見上げた。
少し大人びて見えるその横顔に、胸がきゅっとなる。
「朔都はきっと覚えてるよ。あのとき、すごく甘えてたし」
「だな。……あいつ、明日テンション爆上がりだろうな」
「仁奈も“おめかしする!”とか言いそう」
「想像つく」
二人で笑い合いながら、並んで歩く。
通学路に伸びる影が、夕日に伸ばされて長く交わった。
ふと、都花がぽつりと言う。
「……なんかね、ちょっとだけドキドキする」
「なにが?」
「久しぶりに“家族”がそろうのが。嬉しいけど、うまく言えない気持ち」
理人は少し考えてから、小さくうなずいた。
「わかるよ。俺も、ちょっと緊張してる」
「理人でも?」
「おう。だってさ……俺たち、もう子どもじゃないし」
その言葉に、風が一瞬止まったように感じた。
都花は口を開きかけて、結局何も言えず、うつむいた。
すると理人が、ふっと笑って続ける。
「でも、まぁ。大丈夫だろ。俺ら、ちゃんとやってきたし」
「……そうだね」
「明日、みんなで笑って迎えようぜ」
「うん!」