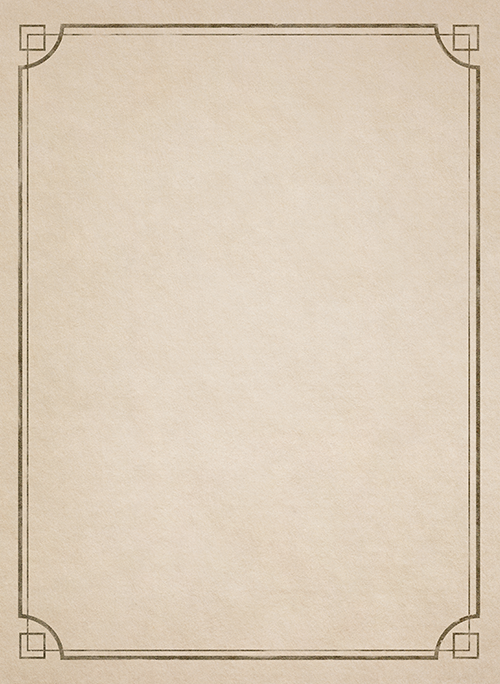あっという間に、二人を起こす時間になった。
こういうとき、仁奈は理人みたいに寝起きが悪くなくて、助かるなと思う。
「……おねえちゃん……ごはん……」
まだ眠そうな声で、仁奈が都花の袖をぎゅっとつかむ。
寝癖がぴょんぴょん跳ねていて、まるで小さなひな鳥みたいだ。
「おはよ、仁奈。よく寝れた?」
「うんー、お腹空いた。」
都花が笑いながらリビングまで抱いていくと、理人はお味噌汁を運んでいた。
「おう、仁奈。おはよ。」
「おはよー、お兄ちゃん! 朔ちゃんは?」
その言葉に、理人は苦笑いしながら仁奈の頭を軽く撫でた。
「仁奈は朔都のこと、ほんと好きだなー」
「わたし、おっきくなったらさくちゃんと結婚するの!」
そんなやり取りを聞きながら、都花はふっと笑う。
仁奈はまだ年中さん。二年前のことなんて、ほとんど覚えていない。
だから、明日帰ってくる理人と都花の両親のことも、きっと“ぼんやり”した記憶しかない。
それを少しだけ、二人は心配していた。
「理人、朔都のこと起こした?」
「ああ、すぐくると思うけど……」
そのとき、廊下の向こうから足音がして、朔都が顔をのぞかせた。
「おはよー! もう朝ごはんできた?」
「おはよ、朔都。卵焼き、もうすぐ焼けるよ」
「やった! やっぱおねえちゃんの卵焼きがいちばんうまい!」
「そういえばさ」理人が言う。
「仁奈、朔都。明日ね、ママとパパが帰ってくるよ」
「えっ! ほんと!?」
仁奈の目がまんまるになり、朔都が思わず声を弾ませる。
「やったー! おにいちゃんとおねえちゃんもいっしょにおむかえ行こう!」
「もちろん!」
都花が笑顔で答えると、仁奈が勢いよく抱きついてきた。
理人はそんな二人を見ながら、静かに湯呑を置いた。
「……今日の朝ごはん、なんか特別にうまそうだな」
「でしょ? お祝いの予行演習!」
「お祝いって?」と仁奈が首をかしげる。
「さぁね!」
都花がウインクすると、仁奈は嬉しそうに笑い、朔都と手を叩いた。
こういうとき、仁奈は理人みたいに寝起きが悪くなくて、助かるなと思う。
「……おねえちゃん……ごはん……」
まだ眠そうな声で、仁奈が都花の袖をぎゅっとつかむ。
寝癖がぴょんぴょん跳ねていて、まるで小さなひな鳥みたいだ。
「おはよ、仁奈。よく寝れた?」
「うんー、お腹空いた。」
都花が笑いながらリビングまで抱いていくと、理人はお味噌汁を運んでいた。
「おう、仁奈。おはよ。」
「おはよー、お兄ちゃん! 朔ちゃんは?」
その言葉に、理人は苦笑いしながら仁奈の頭を軽く撫でた。
「仁奈は朔都のこと、ほんと好きだなー」
「わたし、おっきくなったらさくちゃんと結婚するの!」
そんなやり取りを聞きながら、都花はふっと笑う。
仁奈はまだ年中さん。二年前のことなんて、ほとんど覚えていない。
だから、明日帰ってくる理人と都花の両親のことも、きっと“ぼんやり”した記憶しかない。
それを少しだけ、二人は心配していた。
「理人、朔都のこと起こした?」
「ああ、すぐくると思うけど……」
そのとき、廊下の向こうから足音がして、朔都が顔をのぞかせた。
「おはよー! もう朝ごはんできた?」
「おはよ、朔都。卵焼き、もうすぐ焼けるよ」
「やった! やっぱおねえちゃんの卵焼きがいちばんうまい!」
「そういえばさ」理人が言う。
「仁奈、朔都。明日ね、ママとパパが帰ってくるよ」
「えっ! ほんと!?」
仁奈の目がまんまるになり、朔都が思わず声を弾ませる。
「やったー! おにいちゃんとおねえちゃんもいっしょにおむかえ行こう!」
「もちろん!」
都花が笑顔で答えると、仁奈が勢いよく抱きついてきた。
理人はそんな二人を見ながら、静かに湯呑を置いた。
「……今日の朝ごはん、なんか特別にうまそうだな」
「でしょ? お祝いの予行演習!」
「お祝いって?」と仁奈が首をかしげる。
「さぁね!」
都花がウインクすると、仁奈は嬉しそうに笑い、朔都と手を叩いた。