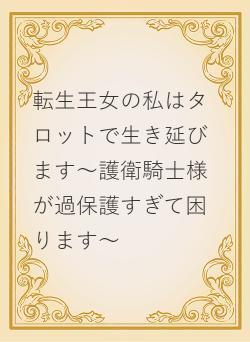「あぁ〜。ゆっくり味わいたいのに〜」
そういいながらも焼いた食パンにサラダを挟んで、一口齧る。それだけで、パリッといい音がした。さらに焼き加減も私好み。ちゃんと咀嚼したい気持ちにかられたが、グリフィスが私の目の前にカップを差し出してきた。さっさと流し込め、と無言の圧力をかけてくる。
「んー!」
「だから起こす、と言っているではありませんか。それなのにアゼリアは……」
「いや、それは……ちょっと……」
なんというか、グリフィスという人間は、どのように他人が自身を見ているのか、それが分かっていない。
一言でいうと、彼は……見た目が綺麗。いや、美し過ぎて神々しいのだ。加えて今は、台所の小窓から射す光に当てられて、金色の髪がいつも以上に輝いている。その奥に見える紫の瞳なんて、アメジストだと勘違いしてしまうだろう。
う〜ん。私にもっと語彙力と詩的センスがあれば、グリフィスの美しさを表現できたのに……それが恨めしかった。
「手が止まっていますよ。大丈夫なんですか?」
「よくないに決まっているでしょう!」
私はグリフィスの手から奪うように、コーヒーの入ったカップを受け取った。甘さ控えめなのも私好み。
そういいながらも焼いた食パンにサラダを挟んで、一口齧る。それだけで、パリッといい音がした。さらに焼き加減も私好み。ちゃんと咀嚼したい気持ちにかられたが、グリフィスが私の目の前にカップを差し出してきた。さっさと流し込め、と無言の圧力をかけてくる。
「んー!」
「だから起こす、と言っているではありませんか。それなのにアゼリアは……」
「いや、それは……ちょっと……」
なんというか、グリフィスという人間は、どのように他人が自身を見ているのか、それが分かっていない。
一言でいうと、彼は……見た目が綺麗。いや、美し過ぎて神々しいのだ。加えて今は、台所の小窓から射す光に当てられて、金色の髪がいつも以上に輝いている。その奥に見える紫の瞳なんて、アメジストだと勘違いしてしまうだろう。
う〜ん。私にもっと語彙力と詩的センスがあれば、グリフィスの美しさを表現できたのに……それが恨めしかった。
「手が止まっていますよ。大丈夫なんですか?」
「よくないに決まっているでしょう!」
私はグリフィスの手から奪うように、コーヒーの入ったカップを受け取った。甘さ控えめなのも私好み。