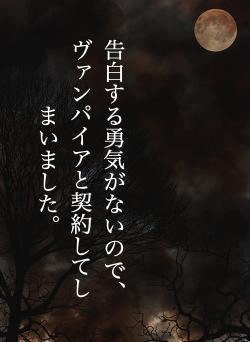それから一週間ほど月子と特に話すことはなかった。
別に気まずいわけではない。俺が一方的に意識しすぎているだけなのだろう。
一週間ぶりに図書館へ行く。
静かに、『D坂の殺人事件』を読む。
「あ、それ..」
俺の目の前で、俺が一番聞きたかった声が流れる。
「『D坂の殺人事件』。私一番好きなの。」
月子だ。夕日があたり、いつもよりも透き通って見える。
彼女は俺の隣に座ると、
「どう?その本」と尋ねてくる。
彼女は、俺が読んでいるページを、一緒に目で追ってくれた。
やめてほしい。近づかないでほしい。勘違いするから。
二人の顔が、ゆっくりと近づいていく。 彼女の髪から、微かに、シャンプーの匂いがした。
そのとき、ふいに手が震え、本を落としそうになる。俺は、本を落とさないようにと、本を持つ手に力を込めた。その拍子に、彼女の指先が、俺の手にそっと触れた。 彼女は驚いて、手を引っ込めようとしたが、俺は、彼女の指を、そのまま握りしめていた。
少しの間沈黙が流れる。
「…ごめん」
俺は、精一杯の声で謝った。
しばらくの沈黙が続いた後、月子は、ゆっくりと俺の手を解き、俯いた。
俺は、もう一度、心臓が大きく鳴るのを感じた。
気のせいだろうか。彼女の顔がほんのり赤く染まっているように見えた。
「あの…朝倉くんって、どうして…」
彼女は、蚊の鳴くような声で、言葉を紡ぎ始めた。
「どうして、私と話してくれるの?」
俺は、その言葉に、驚きを隠せなかった。 彼女は、顔を上げないまま、続けた。
「私、目立たないし…暗いし。クラスでも、誰とも話さないし…朝倉くんみたいなキラキラした人が、近くにいると、なんか変な気分なの..。これまで関わったことなかったから..。」
俺のつまらない日常を、一瞬で色鮮やかに変えてくれた、静かな月の光のような彼女。 そんな彼女が、自分を卑下する言葉を口にするのが、俺は、たまらなく嫌だった。
「…そんなこと、ない」
俺は、精一杯の強さで、そう言った。 月子が、ゆっくりと顔を上げた。その瞳には、不安と、少しの期待が入り混じっていた。
「俺は、葉山さんが...」
言葉が出ない。いつもそうだ。肝心なところで、言葉が見つからない。 でも、今、伝えなければいけない。 俺は、深く息を吸い込んだ。
「俺は、葉山さんが、一番素敵だと思ってる」
俺の言葉に、月子は、大きく目を見開いた。 彼女の顔が、ゆっくりと、赤く染まっていく。 その表情は、俺が今まで見てきた、どの女子の表情よりも、美しかった。
「…あの、ごめん私、そういうこと言われたことなくて..その勘違いしちゃうから…やめてほしい」
彼女は、震える声で言った。 その言葉に、俺は、たまらなく愛おしくなった。 勘違いなんかじゃない。 俺は、今までの人生で、一番真剣な顔で、彼女の目を見た。
「勘違いじゃない」
俺の言葉に、月子は、また少しだけ、目を丸くした。 俺は、もう一度、彼女に、俺の心の内を伝えようと思った。
「俺は、葉山さんを…好きになった」
そう言って、俺は、彼女の手を、もう一度、握った。
別に気まずいわけではない。俺が一方的に意識しすぎているだけなのだろう。
一週間ぶりに図書館へ行く。
静かに、『D坂の殺人事件』を読む。
「あ、それ..」
俺の目の前で、俺が一番聞きたかった声が流れる。
「『D坂の殺人事件』。私一番好きなの。」
月子だ。夕日があたり、いつもよりも透き通って見える。
彼女は俺の隣に座ると、
「どう?その本」と尋ねてくる。
彼女は、俺が読んでいるページを、一緒に目で追ってくれた。
やめてほしい。近づかないでほしい。勘違いするから。
二人の顔が、ゆっくりと近づいていく。 彼女の髪から、微かに、シャンプーの匂いがした。
そのとき、ふいに手が震え、本を落としそうになる。俺は、本を落とさないようにと、本を持つ手に力を込めた。その拍子に、彼女の指先が、俺の手にそっと触れた。 彼女は驚いて、手を引っ込めようとしたが、俺は、彼女の指を、そのまま握りしめていた。
少しの間沈黙が流れる。
「…ごめん」
俺は、精一杯の声で謝った。
しばらくの沈黙が続いた後、月子は、ゆっくりと俺の手を解き、俯いた。
俺は、もう一度、心臓が大きく鳴るのを感じた。
気のせいだろうか。彼女の顔がほんのり赤く染まっているように見えた。
「あの…朝倉くんって、どうして…」
彼女は、蚊の鳴くような声で、言葉を紡ぎ始めた。
「どうして、私と話してくれるの?」
俺は、その言葉に、驚きを隠せなかった。 彼女は、顔を上げないまま、続けた。
「私、目立たないし…暗いし。クラスでも、誰とも話さないし…朝倉くんみたいなキラキラした人が、近くにいると、なんか変な気分なの..。これまで関わったことなかったから..。」
俺のつまらない日常を、一瞬で色鮮やかに変えてくれた、静かな月の光のような彼女。 そんな彼女が、自分を卑下する言葉を口にするのが、俺は、たまらなく嫌だった。
「…そんなこと、ない」
俺は、精一杯の強さで、そう言った。 月子が、ゆっくりと顔を上げた。その瞳には、不安と、少しの期待が入り混じっていた。
「俺は、葉山さんが...」
言葉が出ない。いつもそうだ。肝心なところで、言葉が見つからない。 でも、今、伝えなければいけない。 俺は、深く息を吸い込んだ。
「俺は、葉山さんが、一番素敵だと思ってる」
俺の言葉に、月子は、大きく目を見開いた。 彼女の顔が、ゆっくりと、赤く染まっていく。 その表情は、俺が今まで見てきた、どの女子の表情よりも、美しかった。
「…あの、ごめん私、そういうこと言われたことなくて..その勘違いしちゃうから…やめてほしい」
彼女は、震える声で言った。 その言葉に、俺は、たまらなく愛おしくなった。 勘違いなんかじゃない。 俺は、今までの人生で、一番真剣な顔で、彼女の目を見た。
「勘違いじゃない」
俺の言葉に、月子は、また少しだけ、目を丸くした。 俺は、もう一度、彼女に、俺の心の内を伝えようと思った。
「俺は、葉山さんを…好きになった」
そう言って、俺は、彼女の手を、もう一度、握った。