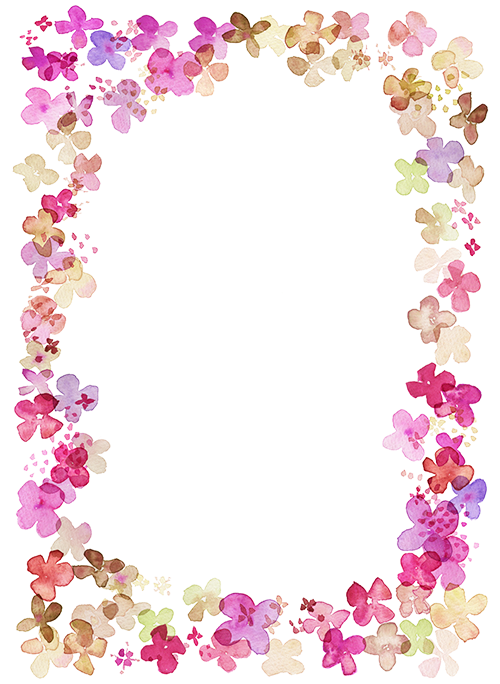違和感は前からあった。
ずっと前から、ボタンをちがう穴にはめているような感覚があった。
「これ」
夕食の代わりに1枚の白い紙をダイニングのテーブルにそっと置いた。
「え」
「私の分は名前書いてあるから。
あなたの名前書いて」
彼は会社から帰って来たばかりで、ネクタイを緩めようとしていた。かつては愛しくて愛しくてたまらないと思っていた汗のにおいが今はただただ不快で早く逃れたい。
「夕飯は」
「ないよ」
「なんで!?」
子どものようにそう聞く彼も年相応に老いたな、と思う。まだ20代後半ではあるけれど、あまりにも社会に染まってしまった。悪い方向に。
「おまえの役目だろ!!」
「ちがうよ」
最初は照れくさくて直視できなかったその目も、今は冷静に見られる。黒の中に茶色がわずかに混じる。太陽のコロナみたいに黒い点が丸い形に散る。白目が大きくて血走っている。
「炊事も洗たくも掃除もゴミ出しも、トイレットペーパーの取り替えもシャンプーの詰め替えも、
私の役目じゃない」
「生理か?」
ずっと前から、ボタンをちがう穴にはめているような感覚があった。
「これ」
夕食の代わりに1枚の白い紙をダイニングのテーブルにそっと置いた。
「え」
「私の分は名前書いてあるから。
あなたの名前書いて」
彼は会社から帰って来たばかりで、ネクタイを緩めようとしていた。かつては愛しくて愛しくてたまらないと思っていた汗のにおいが今はただただ不快で早く逃れたい。
「夕飯は」
「ないよ」
「なんで!?」
子どものようにそう聞く彼も年相応に老いたな、と思う。まだ20代後半ではあるけれど、あまりにも社会に染まってしまった。悪い方向に。
「おまえの役目だろ!!」
「ちがうよ」
最初は照れくさくて直視できなかったその目も、今は冷静に見られる。黒の中に茶色がわずかに混じる。太陽のコロナみたいに黒い点が丸い形に散る。白目が大きくて血走っている。
「炊事も洗たくも掃除もゴミ出しも、トイレットペーパーの取り替えもシャンプーの詰め替えも、
私の役目じゃない」
「生理か?」