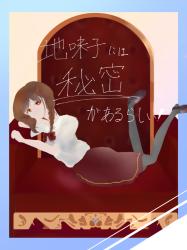そう言い切り、自分の手が痛いことに気付く。
視線を下せば、そこには力の籠り過ぎた手が。
「あっ!すみません。痛かったですよね」
慌てて手を振り解き、視線をそっぽに向ける。
なんだか、思いっきり格好付けてしまった……
遅れてやってきた、手の痛みと羞恥心。
頭を占めるのは、この先の嫌な展開たち。
キモっと吐き捨てられる覚悟をし、一秒後。
感じたのは辛辣な反応……ではなく。
自分の手を包む、温もりだった。
驚きに顔を上げれば、そこには微笑む彼女が。
夕日が後光の様に、彼女の輪郭を照らしている。
それは、どこぞの女神を想起させるものだった。
「いえ。それよりも、凄く……心強いです。」
そんな彼女の言葉からは、震えが消えていた。
橙を背にした少女から、目を逸らせなかった。
視線を下せば、そこには力の籠り過ぎた手が。
「あっ!すみません。痛かったですよね」
慌てて手を振り解き、視線をそっぽに向ける。
なんだか、思いっきり格好付けてしまった……
遅れてやってきた、手の痛みと羞恥心。
頭を占めるのは、この先の嫌な展開たち。
キモっと吐き捨てられる覚悟をし、一秒後。
感じたのは辛辣な反応……ではなく。
自分の手を包む、温もりだった。
驚きに顔を上げれば、そこには微笑む彼女が。
夕日が後光の様に、彼女の輪郭を照らしている。
それは、どこぞの女神を想起させるものだった。
「いえ。それよりも、凄く……心強いです。」
そんな彼女の言葉からは、震えが消えていた。
橙を背にした少女から、目を逸らせなかった。