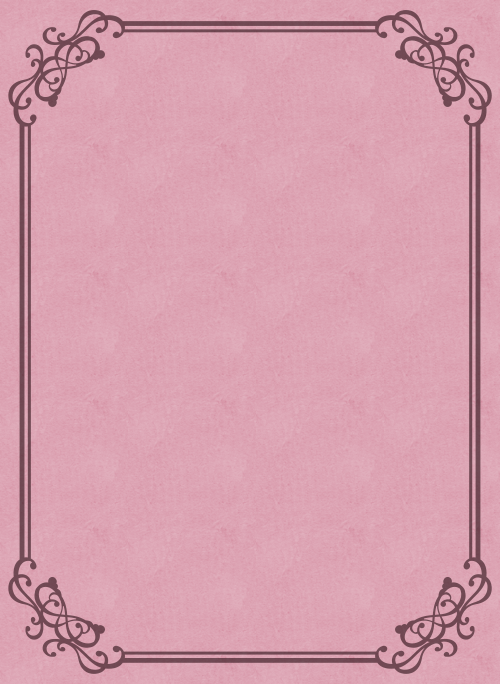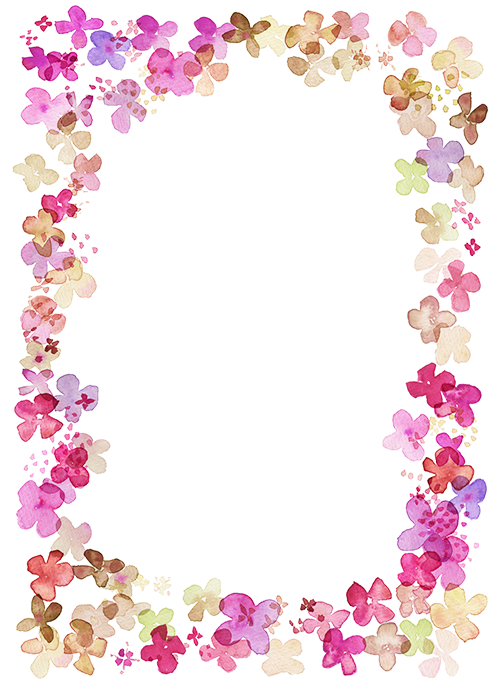雨上がりの午後だった。
職場の休憩スペース、ふと視線を上げた先に、見覚えのある横顔があった。
「……瑛菜?」
振り向いた瞳が、十年分の記憶を軽く飛び越えてくる。
高校時代、同じクラスで、同じ通学路を歩いた人。いつも誰かの輪の中にいて、飾らない笑顔を向けてくれた人。
一方の私は、人に気持ちを伝えるのが苦手で、胸に湧いた言葉を飲み込んでばかりだった。
「やっぱり蒼海だ! 久しぶり!」
彼女の変わらない声が、休憩室を一瞬で春の空気に変えてしまう。
その日から、職場の廊下で会えば挨拶を交わし、退勤時にたまに一緒に歩くようになった。
数週間後、ひょんな流れで出た言葉に、私は自分でも驚いた。
「……家、しばらく空けるって言ってたけど、うち来る?」
「いいの? じゃあお言葉に甘えて――同棲、だね」
あくまで期間限定、そう思っていたはずなのに、玄関に並ぶ二足の靴と、夕飯時の湯気、洗面台に並ぶ歯ブラシの光景が、日々をやわらかく塗り変えていった。
瑛菜は優しい。
帰宅が遅い日には温かいお茶を用意してくれて、疲れた顔をすると何も聞かずにそばに座る。
「無理しないでいいよ」という笑顔に、胸の奥の固く結ばれた糸が、少しずつほどけていくのを感じた。
ある晩、ソファで並んで映画を観ていると、瑛菜がぽつりとつぶやいた。
「蒼海って、本当は優しいよね。でも、自分のことあんまり話してくれないから、ちょっと寂しい」
戸惑いと、何かを託されたような温かさが同時に押し寄せた。
私は深呼吸して、今まで言えなかった言葉を、ひとつだけ口にする。
「……瑛菜といると、安心する」
彼女は驚いた後、ふわっと笑った。
それは高校のときに見た笑顔と同じで、でももっと近くにあった。
窓の外には、夜風に揺れるカーテン。
この暮らしがいつまで続くのかはわからない。それでも、もう怖がらずに、少しずつでも気持ちを渡していきたい――
そう思える自分が、今ここにいる。
職場の休憩スペース、ふと視線を上げた先に、見覚えのある横顔があった。
「……瑛菜?」
振り向いた瞳が、十年分の記憶を軽く飛び越えてくる。
高校時代、同じクラスで、同じ通学路を歩いた人。いつも誰かの輪の中にいて、飾らない笑顔を向けてくれた人。
一方の私は、人に気持ちを伝えるのが苦手で、胸に湧いた言葉を飲み込んでばかりだった。
「やっぱり蒼海だ! 久しぶり!」
彼女の変わらない声が、休憩室を一瞬で春の空気に変えてしまう。
その日から、職場の廊下で会えば挨拶を交わし、退勤時にたまに一緒に歩くようになった。
数週間後、ひょんな流れで出た言葉に、私は自分でも驚いた。
「……家、しばらく空けるって言ってたけど、うち来る?」
「いいの? じゃあお言葉に甘えて――同棲、だね」
あくまで期間限定、そう思っていたはずなのに、玄関に並ぶ二足の靴と、夕飯時の湯気、洗面台に並ぶ歯ブラシの光景が、日々をやわらかく塗り変えていった。
瑛菜は優しい。
帰宅が遅い日には温かいお茶を用意してくれて、疲れた顔をすると何も聞かずにそばに座る。
「無理しないでいいよ」という笑顔に、胸の奥の固く結ばれた糸が、少しずつほどけていくのを感じた。
ある晩、ソファで並んで映画を観ていると、瑛菜がぽつりとつぶやいた。
「蒼海って、本当は優しいよね。でも、自分のことあんまり話してくれないから、ちょっと寂しい」
戸惑いと、何かを託されたような温かさが同時に押し寄せた。
私は深呼吸して、今まで言えなかった言葉を、ひとつだけ口にする。
「……瑛菜といると、安心する」
彼女は驚いた後、ふわっと笑った。
それは高校のときに見た笑顔と同じで、でももっと近くにあった。
窓の外には、夜風に揺れるカーテン。
この暮らしがいつまで続くのかはわからない。それでも、もう怖がらずに、少しずつでも気持ちを渡していきたい――
そう思える自分が、今ここにいる。