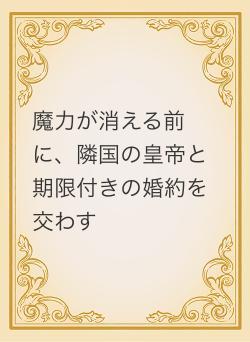「詩織、そろそろ帰ろうか。」
「そうですね。」
この短時間で何度も名前を呼ばれてだいぶ慣れてきた。でも、専務を名前で呼ぶことにはまだ慣れない。
「親父さん、ご馳走様でした。また来ますね!」
「あぁ。次もそちらの彼女さんと一緒に来るんだよ?」
「そうします。」
お店を出ると、外はすっかり夜になっていた。空には綺麗な満月が輝いている。
「彼女と一緒にって念を押されちゃったな。」
「また寝ると思われてるんですね。」
「たぶんね。」
専務は私の前に手を差し出した。首を傾げると、専務は勝手に私の手を握った。
「恋人なんだから。」
(恋人のふり……だよね……?)
月明りの下を何を話すわけでもなく、手を繋いで歩いている。居酒屋の個室で何を話して良いかわからない気まずさはもう無い。一緒に歩いているだけで心地いいのだから、私は専務のことが好きなのだ。だけど──
「月が綺麗だね。」
専務はピタリと足を止めて空を見上げた。視線を追うと、まんまるの満月が私たちを見下ろしていた。
「本当ですね。」
「俺の部屋ならもっと綺麗に見えるよ。」
専務は繋いでる手を持ち上げると、見せつけるように指を絡めた。手のひらから熱が伝わってくる。専務は少しだけ私の手を引いて、耳元で囁いた。
「もう少し飲まない?」
艶のある声が頭の中に響き、わずかに息を呑んだ。もうだめかもしれない。どんなに拒もうとしても、私の心はずっと前から専務に握られてしまっている。
「詩織?」
名前を呼ばれて顔を上げると、専務の顔がゆっくり近づいてきた。拒みたい、拒まなければいけないのに、私の手は専務の手に包まれて動かない。腰を引き寄せられて目を閉じると、月明かりに照らされた2人の影が1つに重なった──
「そうですね。」
この短時間で何度も名前を呼ばれてだいぶ慣れてきた。でも、専務を名前で呼ぶことにはまだ慣れない。
「親父さん、ご馳走様でした。また来ますね!」
「あぁ。次もそちらの彼女さんと一緒に来るんだよ?」
「そうします。」
お店を出ると、外はすっかり夜になっていた。空には綺麗な満月が輝いている。
「彼女と一緒にって念を押されちゃったな。」
「また寝ると思われてるんですね。」
「たぶんね。」
専務は私の前に手を差し出した。首を傾げると、専務は勝手に私の手を握った。
「恋人なんだから。」
(恋人のふり……だよね……?)
月明りの下を何を話すわけでもなく、手を繋いで歩いている。居酒屋の個室で何を話して良いかわからない気まずさはもう無い。一緒に歩いているだけで心地いいのだから、私は専務のことが好きなのだ。だけど──
「月が綺麗だね。」
専務はピタリと足を止めて空を見上げた。視線を追うと、まんまるの満月が私たちを見下ろしていた。
「本当ですね。」
「俺の部屋ならもっと綺麗に見えるよ。」
専務は繋いでる手を持ち上げると、見せつけるように指を絡めた。手のひらから熱が伝わってくる。専務は少しだけ私の手を引いて、耳元で囁いた。
「もう少し飲まない?」
艶のある声が頭の中に響き、わずかに息を呑んだ。もうだめかもしれない。どんなに拒もうとしても、私の心はずっと前から専務に握られてしまっている。
「詩織?」
名前を呼ばれて顔を上げると、専務の顔がゆっくり近づいてきた。拒みたい、拒まなければいけないのに、私の手は専務の手に包まれて動かない。腰を引き寄せられて目を閉じると、月明かりに照らされた2人の影が1つに重なった──