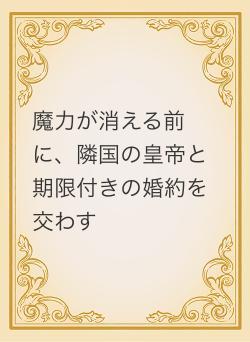帰国した後も、私は毎日そわそわしながら過ごしていた。食事をしていても、本を読んでいても、頭の中はシュナイデルさんのことでいっぱいだった。
「いつ、会えるのかしら……」
窓の外を眺めていると、部屋にノックの音が響いた。
「マリー様、お客様でございます。」
「お客様?どなた?」
「その……花園急便と仰る方でして……」
「花園急便!?すぐにお通ししてください!」
私は勢いよく立ち上がり、手ぐしで髪を整えた。ようやく会える。姿勢を正して待っていると、心臓の音がドキドキと高鳴り始めて、私は思わず胸を押さえた。
「こんにちは。花園急便です。」
扉が開かれて入ってきたのは、私が知るシュナイデルさんとは違った。
「シュナイデルさん……なのですか?」
白を基調とした軍服には、華やかな金の刺繍が施され、光沢のある赤いマントが揺れている。
「マリー様にお届け物です。」
シュナイデルさんは、片膝をついて私の前に小箱を差し出した。
「マリー様、私と結婚してください。」
小箱の中には、宝石が施された可愛らしい指輪が納められていた。熱いものが込み上げてきて、涙となって溢れ出した。
「シュナイデルさん……あなたは……」
すると、廊下が騒がしくなって勢いよくドアが開いた。なだれ込んできたのは、7人の小人たちだった。
「マリー様、こちらはおまけのお届け物でございます。」
「ひどいぜ、殿下!」
「終わるまで待ってたんだぞ!」
「褒めてくれよ!」
「わかったわかった。礼を言おう、諸君。」
部屋の中が懐かしい声に包まれていく。別れ際にすぐ会えると言ってくれた意味が、ようやくわかった。
「花園急便さんは、王子様だったのですね。」
「まぁ、そうかもしれません。」
私は薬指に輝く指輪を見つめた。
「マリー様、殿下は花園急便の格好でお会いしようとしていたのですよ?」
「せっかくのプロポーズなのに、森の運び屋の格好だなんて。」
「だからみんなで止めました。」
「プリンセスのお相手はプリンスと相場が決まっていますからね。」
「そういうことは言わなくていい。」
シュナイデル様は、小人たちに揶揄われて顔を赤くしている。
「私は……花園急便の格好でも良かったですよ?」
「森の運び屋ですよ?」
「王子様じゃないんですよ?」
「シュナイデル様でしたら、どんな格好でも構いません。」
「これからは、ずっとそばにいます。毒リンゴが届かないように、ちゃんと見張っていますからね。」
そう言って笑い合う私たちのまわりで、小人たちは楽しそうに踊っていた。
「いつ、会えるのかしら……」
窓の外を眺めていると、部屋にノックの音が響いた。
「マリー様、お客様でございます。」
「お客様?どなた?」
「その……花園急便と仰る方でして……」
「花園急便!?すぐにお通ししてください!」
私は勢いよく立ち上がり、手ぐしで髪を整えた。ようやく会える。姿勢を正して待っていると、心臓の音がドキドキと高鳴り始めて、私は思わず胸を押さえた。
「こんにちは。花園急便です。」
扉が開かれて入ってきたのは、私が知るシュナイデルさんとは違った。
「シュナイデルさん……なのですか?」
白を基調とした軍服には、華やかな金の刺繍が施され、光沢のある赤いマントが揺れている。
「マリー様にお届け物です。」
シュナイデルさんは、片膝をついて私の前に小箱を差し出した。
「マリー様、私と結婚してください。」
小箱の中には、宝石が施された可愛らしい指輪が納められていた。熱いものが込み上げてきて、涙となって溢れ出した。
「シュナイデルさん……あなたは……」
すると、廊下が騒がしくなって勢いよくドアが開いた。なだれ込んできたのは、7人の小人たちだった。
「マリー様、こちらはおまけのお届け物でございます。」
「ひどいぜ、殿下!」
「終わるまで待ってたんだぞ!」
「褒めてくれよ!」
「わかったわかった。礼を言おう、諸君。」
部屋の中が懐かしい声に包まれていく。別れ際にすぐ会えると言ってくれた意味が、ようやくわかった。
「花園急便さんは、王子様だったのですね。」
「まぁ、そうかもしれません。」
私は薬指に輝く指輪を見つめた。
「マリー様、殿下は花園急便の格好でお会いしようとしていたのですよ?」
「せっかくのプロポーズなのに、森の運び屋の格好だなんて。」
「だからみんなで止めました。」
「プリンセスのお相手はプリンスと相場が決まっていますからね。」
「そういうことは言わなくていい。」
シュナイデル様は、小人たちに揶揄われて顔を赤くしている。
「私は……花園急便の格好でも良かったですよ?」
「森の運び屋ですよ?」
「王子様じゃないんですよ?」
「シュナイデル様でしたら、どんな格好でも構いません。」
「これからは、ずっとそばにいます。毒リンゴが届かないように、ちゃんと見張っていますからね。」
そう言って笑い合う私たちのまわりで、小人たちは楽しそうに踊っていた。