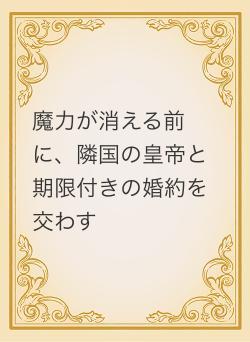インターホンを押すと、ドアが開いて気怠げなユウくんが顔を出した。ユウくんはいつもなんだか眠たそう。
「早かったじゃん。バイト?」
「うん。近くまで来てたから……」
「ん。」
私は当たり前のように玄関で靴を脱いで、部屋に上がり込むと、リビングに置かれている黒いソファーにどかりと腰を下ろした。
「はぁ〜……ここ落ち着くなぁ〜」
「そ?」
ユウくんはグラスに麦茶を入れて、持ってきてくれた。
「ありがと。」
「それで?なんの相談?」
「何も言ってないのにわかるんだ。」
「相談もなしに来ないだろ?」
「まぁね〜」
ユウくんは、何も言わなくてもわかってくれる。幼なじみだからだろうか。
「実は……サークルの先輩に誘われていまして……」
「ふーん。何?デート?」
ユウくんは麦茶を飲みながら、視線をこちらへ向けた。
「わかんないけど、2人で行きたいって言われてて……」
「へー、どんな人?」
「いい人だよ。1つ上の先輩で、頼り甲斐があるし、人気もあるし……」
「顔は?」
「まぁ、カッコいいと思う。」
「じゃあ、いいじゃん。」
私もそう思う。良い先輩だ。付き合ったら良い彼氏になってくれる気がする。
「でもなんかさー……」
「なに?何が気になってんの?」
「なんか気になるんだよね……なんかちょっとこう……」
その何かがわからない。
「引っ張りすぎな感じ?」
「うん……」
そんな気がする。
「俺様ってわけじゃないけど、なんとなく口出せないような感じで、これやろうぜーみたいな?」
「そう、それ!なんでわかるの?」
ユウくんはいつも私の心を代弁してくれる。
「イチカって頼られたい側じゃん。だから、気になるんじゃないの?」
「そうなんだよねー……彼氏には頼りたいんだよ。でも、私も決めたいからさ、こっちの話も聞かないで、ここ行くから来てよ〜みたいに言われるとちょっと……」
「萎えるよね。」
「うん。萎える。」
彼氏にリードされたいとは思ってるんだけど。
「断った方がいいんじゃない?」
「そうなのかなぁ。」
「そこまでわかってるなら、付き合っても楽しくないでしょ。」
「でも断ったら彼氏できないじゃん。」
断り続けていたら、彼氏はできない。
「そんなことないだろ。」
「ユウくんは彼女できたの?」
彼女と別れたって聞いたけど、その後どうしたのか聞いてない。
「いない。」
「彼女いなくて平気なの?」
男なのにさ。
「なんだよ。平気だよ、べつに。」
「いや、年頃の男子はなんか、そういう気持ちになるって言うし……」
欲求みたいな……ね。
「いなくてもなんとかなってるから。」
「えっ……」
どういうこと?
「なに?」
「彼女いないんだよね?」
「いないよ。」
「そういう相手がいるってこと?」
彼女じゃない人が。
「……さぁ?」
「うわー……なんかイメージ変わったー」
「男なんてそんなもんじゃないの?」
「そんなことないでしょ。」
そんなことない。絶対。
「俺、モテるから。イチカと違って。」
「傷つくからやめて。」
でも本当にそう。ユウくんはモテる。
「イチカはちゃんと好きな人とした方がいい。」
「なに真面目に言ってんの、腹立つなー」
体の関係だけの相手がいるくせに。
「無駄にしたらだめだ。」
「ユウくんは無駄にしてるってこと?」
「俺は男だから。」
「ふーん……」
なんかよくわかんない。
「イチカは好きな人いないの?告白された人じゃなくて、イチカが好きだと思う人。」
「……いないなぁ。」
そんな人がいたら、もう告白してる。
「じゃ、待ってたら?王子様が来るでしょ、そのうち。」
「待ってても来ないよ。」
シンデレラじゃあるまいし。
「べつに焦る必要ないと思うけど?」
「ユウくんはいいの?彼女じゃなくて、そういう関係だけって割り切れるの?」
そういうのって繋がってるものじゃないのかな。気持ちとか、心に。
「俺は気持ちがなくてもできるから。」
「それ言ったら、私ともできることになんない?」
「え?」
「女なら誰でも良いってことでしょ?」
理屈的にはそうなっちゃうよね。
「そこまでは言ってないけど。」
「じゃあ、私ともできる?」
私ってどう思われてるんだろう。
「ユウくんは、私ともできるんですか?」
麦茶を飲んでいたユウくんの顔を覗き込んだ。
(やっぱり誰とでもできるなんて……)
「──っ、ちょっ……!!」
気づいたらユウくんに押し倒されていた。両手を強く掴まれて動けない。ユウくんに見下ろされて、心臓がバクバクと音を立てている。
「イチカが言ってるのは、こういうことなんだけど。」
「……」
「めっちゃ怖がってんじゃん……」
「……こ、怖がってないし。」
必死に強がったけど、声が震えていた。
「していいならするけど?」
少しも力が入らない。私は必死に瞬きだけを繰り返した。
「どうすんの?」
私は……
「あーあ。」
ユウくんはため息をついて、あっけなく私の上から退いた。
「ほら、起きて。」
差し出されたユウくんの手を握ると、優しく起こしてくれた。私は目を伏せたまま、なんとなく髪を直した。
「そういうことは簡単に言うな。」
「……うん。ごめん。」
「俺はしないから。イチカにはしない。」
ぎゅっと胸が苦しくなった。心臓はまだドキドキしている。
「先輩の誘いは断った方がいいんじゃない?イチカには合わないと思う。」
「……うん。そうだね。」
声を絞り出すと、ユウくんは立ち上がった。
「シャワー浴びてくるわ。帰ってていいから。」
「……うん。」
ユウくんがシャワールームへ入ると、私は麦茶を一気に飲み干した。そして、ソファーの脇に置いてあったバッグを持って玄関を出た。
ユウくんは私の幼なじみ。
なんでも相談できる友達──
「ごめん。試すようなことして。」
私はマンションの階段を降りて行った。顔に当たる風が妙に冷たく感じた。
「早かったじゃん。バイト?」
「うん。近くまで来てたから……」
「ん。」
私は当たり前のように玄関で靴を脱いで、部屋に上がり込むと、リビングに置かれている黒いソファーにどかりと腰を下ろした。
「はぁ〜……ここ落ち着くなぁ〜」
「そ?」
ユウくんはグラスに麦茶を入れて、持ってきてくれた。
「ありがと。」
「それで?なんの相談?」
「何も言ってないのにわかるんだ。」
「相談もなしに来ないだろ?」
「まぁね〜」
ユウくんは、何も言わなくてもわかってくれる。幼なじみだからだろうか。
「実は……サークルの先輩に誘われていまして……」
「ふーん。何?デート?」
ユウくんは麦茶を飲みながら、視線をこちらへ向けた。
「わかんないけど、2人で行きたいって言われてて……」
「へー、どんな人?」
「いい人だよ。1つ上の先輩で、頼り甲斐があるし、人気もあるし……」
「顔は?」
「まぁ、カッコいいと思う。」
「じゃあ、いいじゃん。」
私もそう思う。良い先輩だ。付き合ったら良い彼氏になってくれる気がする。
「でもなんかさー……」
「なに?何が気になってんの?」
「なんか気になるんだよね……なんかちょっとこう……」
その何かがわからない。
「引っ張りすぎな感じ?」
「うん……」
そんな気がする。
「俺様ってわけじゃないけど、なんとなく口出せないような感じで、これやろうぜーみたいな?」
「そう、それ!なんでわかるの?」
ユウくんはいつも私の心を代弁してくれる。
「イチカって頼られたい側じゃん。だから、気になるんじゃないの?」
「そうなんだよねー……彼氏には頼りたいんだよ。でも、私も決めたいからさ、こっちの話も聞かないで、ここ行くから来てよ〜みたいに言われるとちょっと……」
「萎えるよね。」
「うん。萎える。」
彼氏にリードされたいとは思ってるんだけど。
「断った方がいいんじゃない?」
「そうなのかなぁ。」
「そこまでわかってるなら、付き合っても楽しくないでしょ。」
「でも断ったら彼氏できないじゃん。」
断り続けていたら、彼氏はできない。
「そんなことないだろ。」
「ユウくんは彼女できたの?」
彼女と別れたって聞いたけど、その後どうしたのか聞いてない。
「いない。」
「彼女いなくて平気なの?」
男なのにさ。
「なんだよ。平気だよ、べつに。」
「いや、年頃の男子はなんか、そういう気持ちになるって言うし……」
欲求みたいな……ね。
「いなくてもなんとかなってるから。」
「えっ……」
どういうこと?
「なに?」
「彼女いないんだよね?」
「いないよ。」
「そういう相手がいるってこと?」
彼女じゃない人が。
「……さぁ?」
「うわー……なんかイメージ変わったー」
「男なんてそんなもんじゃないの?」
「そんなことないでしょ。」
そんなことない。絶対。
「俺、モテるから。イチカと違って。」
「傷つくからやめて。」
でも本当にそう。ユウくんはモテる。
「イチカはちゃんと好きな人とした方がいい。」
「なに真面目に言ってんの、腹立つなー」
体の関係だけの相手がいるくせに。
「無駄にしたらだめだ。」
「ユウくんは無駄にしてるってこと?」
「俺は男だから。」
「ふーん……」
なんかよくわかんない。
「イチカは好きな人いないの?告白された人じゃなくて、イチカが好きだと思う人。」
「……いないなぁ。」
そんな人がいたら、もう告白してる。
「じゃ、待ってたら?王子様が来るでしょ、そのうち。」
「待ってても来ないよ。」
シンデレラじゃあるまいし。
「べつに焦る必要ないと思うけど?」
「ユウくんはいいの?彼女じゃなくて、そういう関係だけって割り切れるの?」
そういうのって繋がってるものじゃないのかな。気持ちとか、心に。
「俺は気持ちがなくてもできるから。」
「それ言ったら、私ともできることになんない?」
「え?」
「女なら誰でも良いってことでしょ?」
理屈的にはそうなっちゃうよね。
「そこまでは言ってないけど。」
「じゃあ、私ともできる?」
私ってどう思われてるんだろう。
「ユウくんは、私ともできるんですか?」
麦茶を飲んでいたユウくんの顔を覗き込んだ。
(やっぱり誰とでもできるなんて……)
「──っ、ちょっ……!!」
気づいたらユウくんに押し倒されていた。両手を強く掴まれて動けない。ユウくんに見下ろされて、心臓がバクバクと音を立てている。
「イチカが言ってるのは、こういうことなんだけど。」
「……」
「めっちゃ怖がってんじゃん……」
「……こ、怖がってないし。」
必死に強がったけど、声が震えていた。
「していいならするけど?」
少しも力が入らない。私は必死に瞬きだけを繰り返した。
「どうすんの?」
私は……
「あーあ。」
ユウくんはため息をついて、あっけなく私の上から退いた。
「ほら、起きて。」
差し出されたユウくんの手を握ると、優しく起こしてくれた。私は目を伏せたまま、なんとなく髪を直した。
「そういうことは簡単に言うな。」
「……うん。ごめん。」
「俺はしないから。イチカにはしない。」
ぎゅっと胸が苦しくなった。心臓はまだドキドキしている。
「先輩の誘いは断った方がいいんじゃない?イチカには合わないと思う。」
「……うん。そうだね。」
声を絞り出すと、ユウくんは立ち上がった。
「シャワー浴びてくるわ。帰ってていいから。」
「……うん。」
ユウくんがシャワールームへ入ると、私は麦茶を一気に飲み干した。そして、ソファーの脇に置いてあったバッグを持って玄関を出た。
ユウくんは私の幼なじみ。
なんでも相談できる友達──
「ごめん。試すようなことして。」
私はマンションの階段を降りて行った。顔に当たる風が妙に冷たく感じた。