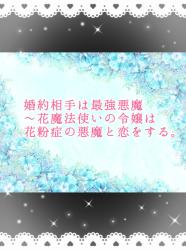私たちはレストランに来た。券売機で食券を買うために結構並んでいた。なんとか無事に買えてギリギリ空いている席に座れ、ほっとする。
夏樹と向かい合わせになって座った。
「こういう場所もたまにはいいよね。遥、楽しめてる?」
「すごく楽しいよ。連れてきてくれてありがとう」
「遥が楽しんでいて、良かった」
夏樹が無邪気な笑顔を見せてきた。
「……普段も誰かに、そんな笑顔を見せてるの?」
ふとした疑問を口にした。私は何故こんな質問を夏樹にしてしまったのだろう。
「昔から、遥にだけかな? こんな風に自分を見せられるの」
「何それ……」
言葉と共に最高の笑顔を見せてきたから、私は照れてうつむいた。
――私にだけ見せてくれるんだ。
胸の辺りが柔らかい桃色で包まれていくような感覚になった。夏樹のこの容姿と性格は、多くの人を引き寄せるタイプだと思う。優しくて人好きだから、来る人拒まずな感じで受け入れるのだろうな、きっと。
だけど他の誰にも見せない部分を私にだけ見せてくれる――。
私は優越感に浸った。同時にずっと私にだけ見せてくれれば良いのになと欲張ってしまう。
「五十番、五十一番のお客様――」
「あ、私たちだ」
夏樹について考えていると呼ばれ、私たちは同時に立ち上がる。
「遥は席とられないようにそのまま座ってて? 俺、持ってくる」
「ひとりで大丈夫? 持てる?」
「余裕だよ」
私は再び座る。
味噌ラーメンが乗ったお盆を両手にひとつずつ持ち、夏樹は戻ってきた。
「ふたつ持てるの凄いね、私は重たくて無理だな」
ふと、黒い半袖シャツからはみ出た腕に注目してしまう。けっこう鍛えてるのかなと思わせてくるような筋肉
「力仕事は、任せて!」
「うん、任せるね! ラーメン久しぶりだな。美味しそう! いただきます」
髪の毛を耳にかけ、ラーメンをすすりながら上目遣いでそっと夏樹を見る。大人の魅力満載に成長したのに昔のままな部分をみつける。
レンゲを使って少しずつ口に麺を入れる夏樹。もしゃもしゃした食べ方がリスみたいで可愛い。
「ラーメンすするの苦手なのだけは変わらないんだね」
「だけ? 俺、全部昔と変わってないよ」
「いや、変わったよ」
「そっか? 例えば?」
「明るくなったところとか、恰好良くなったところとか?」
映画の停止ボタンを押したかのように微動だにしなくなった夏樹。夏樹の目は見開く。そして顔が赤くなっていく。
そうだろ?なんて、自信満々を装いながら言ってくると思っていたのに、何その反応。
「あっ、ラーメンのびちゃう。早く食べないとね」
「そうだな」
私のラーメンをすする音だけがやけに大きく聞こえて、響いている気がした。
*
夏樹と向かい合わせになって座った。
「こういう場所もたまにはいいよね。遥、楽しめてる?」
「すごく楽しいよ。連れてきてくれてありがとう」
「遥が楽しんでいて、良かった」
夏樹が無邪気な笑顔を見せてきた。
「……普段も誰かに、そんな笑顔を見せてるの?」
ふとした疑問を口にした。私は何故こんな質問を夏樹にしてしまったのだろう。
「昔から、遥にだけかな? こんな風に自分を見せられるの」
「何それ……」
言葉と共に最高の笑顔を見せてきたから、私は照れてうつむいた。
――私にだけ見せてくれるんだ。
胸の辺りが柔らかい桃色で包まれていくような感覚になった。夏樹のこの容姿と性格は、多くの人を引き寄せるタイプだと思う。優しくて人好きだから、来る人拒まずな感じで受け入れるのだろうな、きっと。
だけど他の誰にも見せない部分を私にだけ見せてくれる――。
私は優越感に浸った。同時にずっと私にだけ見せてくれれば良いのになと欲張ってしまう。
「五十番、五十一番のお客様――」
「あ、私たちだ」
夏樹について考えていると呼ばれ、私たちは同時に立ち上がる。
「遥は席とられないようにそのまま座ってて? 俺、持ってくる」
「ひとりで大丈夫? 持てる?」
「余裕だよ」
私は再び座る。
味噌ラーメンが乗ったお盆を両手にひとつずつ持ち、夏樹は戻ってきた。
「ふたつ持てるの凄いね、私は重たくて無理だな」
ふと、黒い半袖シャツからはみ出た腕に注目してしまう。けっこう鍛えてるのかなと思わせてくるような筋肉
「力仕事は、任せて!」
「うん、任せるね! ラーメン久しぶりだな。美味しそう! いただきます」
髪の毛を耳にかけ、ラーメンをすすりながら上目遣いでそっと夏樹を見る。大人の魅力満載に成長したのに昔のままな部分をみつける。
レンゲを使って少しずつ口に麺を入れる夏樹。もしゃもしゃした食べ方がリスみたいで可愛い。
「ラーメンすするの苦手なのだけは変わらないんだね」
「だけ? 俺、全部昔と変わってないよ」
「いや、変わったよ」
「そっか? 例えば?」
「明るくなったところとか、恰好良くなったところとか?」
映画の停止ボタンを押したかのように微動だにしなくなった夏樹。夏樹の目は見開く。そして顔が赤くなっていく。
そうだろ?なんて、自信満々を装いながら言ってくると思っていたのに、何その反応。
「あっ、ラーメンのびちゃう。早く食べないとね」
「そうだな」
私のラーメンをすする音だけがやけに大きく聞こえて、響いている気がした。
*