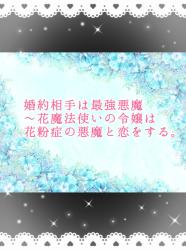実は、一番は夏樹だけど。それは言えないな。口に出すのは恥ずかしくて、怖い。
「恋人は一生欲しくないの?」
「一生って、規模がデカイな。分からないよ、未来にどう思うかなんて……」
なんとなく、私はパソコンに目を向けた。
恋愛小説を書くのは好きだけど、自分が恋愛をして恋人を作るのは別。異次元のよう。
高校時代、友達が恋愛で傷つく姿を見て、恋愛は面倒だと決めつけていた。大人になってから良い感じになった人がいたけれど、実際に恋愛をすると自分の気持ちが整理できなくて苦しくなって、不自由で怖くなった。恋人なんて作ってしまえば、もっと苦しむ。
「俺じゃ、駄目か?」
「えっ?」
パソコンから視線をそらし、私は顔を上げた。夏樹と私は見つめ合う。
「俺は、本気で遥と恋人になりたいと思っているから……考えといて? あと、思い詰めすぎないでな」
夏樹は私の頭をぽんと叩くと、白い歯を見せながら微笑み、コートを羽織ってカフェから出ていった。
――夏樹のこと、恋人だとか……。そんな風に考えたことはなかった。だって、夏樹はいつも私の後ろに隠れている弟のような存在だったから。
『俺は本気で遥と恋人になりたいと思っているから』。
頭の中で言葉が鮮明に何度も流れる。
それから最近一緒に過ごした日々も。
胸の奥がきゅっと締まるように疼いた。
見慣れたカフェの景色が輝いて、違う空間に思えてきた。
こうもはっきりと言われるとは――。
小説の文章をもう一度復元する方法を探すか、新たにまた書こうかなと考えていたのに。夏樹の言葉が頭を占領して、手が全く動かない。
今の二人の関係なままなら何も壊れる心配はないし。あえて深入りする必要もない?
でも、いつの間にか私の中で夏樹の存在は大きくなっていた。
もう、ただの幼なじみではなかった。
その気持ちは、もしかしてもっと前から?
イルカのキーホルダーを優しく握りしめる。
「夏樹と恋人、か……」
窓の外を眺める。雪の降る量がさっきよりも増えていた。夏樹の真剣な目と、私の頭をぽんと叩く仕草が浮かび上がる。夏樹が触れた自分の頭にそっと触れた。
――夏樹と、きちんと向き合いたい。
「オーナー、戻ってくるのでカルボナーラできたらテーブルに置いといてください。ちょっと外に出てきます」
「行ってらっしゃい。夏樹くんも戻ってくるのかな? カルボナーラで良いかい?」
「はい、夏樹もお腹すいてると思うので。お願いします!」
恋人になるのは怖い。だけど夏樹となら、一緒に怖さを乗り越えられる気がする。
「恋人は一生欲しくないの?」
「一生って、規模がデカイな。分からないよ、未来にどう思うかなんて……」
なんとなく、私はパソコンに目を向けた。
恋愛小説を書くのは好きだけど、自分が恋愛をして恋人を作るのは別。異次元のよう。
高校時代、友達が恋愛で傷つく姿を見て、恋愛は面倒だと決めつけていた。大人になってから良い感じになった人がいたけれど、実際に恋愛をすると自分の気持ちが整理できなくて苦しくなって、不自由で怖くなった。恋人なんて作ってしまえば、もっと苦しむ。
「俺じゃ、駄目か?」
「えっ?」
パソコンから視線をそらし、私は顔を上げた。夏樹と私は見つめ合う。
「俺は、本気で遥と恋人になりたいと思っているから……考えといて? あと、思い詰めすぎないでな」
夏樹は私の頭をぽんと叩くと、白い歯を見せながら微笑み、コートを羽織ってカフェから出ていった。
――夏樹のこと、恋人だとか……。そんな風に考えたことはなかった。だって、夏樹はいつも私の後ろに隠れている弟のような存在だったから。
『俺は本気で遥と恋人になりたいと思っているから』。
頭の中で言葉が鮮明に何度も流れる。
それから最近一緒に過ごした日々も。
胸の奥がきゅっと締まるように疼いた。
見慣れたカフェの景色が輝いて、違う空間に思えてきた。
こうもはっきりと言われるとは――。
小説の文章をもう一度復元する方法を探すか、新たにまた書こうかなと考えていたのに。夏樹の言葉が頭を占領して、手が全く動かない。
今の二人の関係なままなら何も壊れる心配はないし。あえて深入りする必要もない?
でも、いつの間にか私の中で夏樹の存在は大きくなっていた。
もう、ただの幼なじみではなかった。
その気持ちは、もしかしてもっと前から?
イルカのキーホルダーを優しく握りしめる。
「夏樹と恋人、か……」
窓の外を眺める。雪の降る量がさっきよりも増えていた。夏樹の真剣な目と、私の頭をぽんと叩く仕草が浮かび上がる。夏樹が触れた自分の頭にそっと触れた。
――夏樹と、きちんと向き合いたい。
「オーナー、戻ってくるのでカルボナーラできたらテーブルに置いといてください。ちょっと外に出てきます」
「行ってらっしゃい。夏樹くんも戻ってくるのかな? カルボナーラで良いかい?」
「はい、夏樹もお腹すいてると思うので。お願いします!」
恋人になるのは怖い。だけど夏樹となら、一緒に怖さを乗り越えられる気がする。