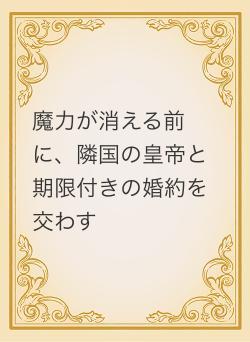レオ様は朝が遅い。起きてくるのは日が落ちた後、夜になってからだ。でも、その日は夜になっても部屋から出て来なかった。
すぐ食べられるように、ロールキャベツの支度を整えたけれど、レオ様はいつまで待っても来ない。
(どうしたんだろう……)
なんだか胸騒ぎがする。エプロンを外してレオ様の部屋へ向かうと、お屋敷の廊下が明るく照らされていた。今日は満月。窓の外には大きな月が輝いている。
「綺麗……」
私は足を止めて月を見上げた。すると、廊下の奥から衣擦れの音と、わずかな息づかいが聞こえてきた。
目を凝らすと、レオ様が壁を伝ってふらふらと歩いている。
「レオ様!?」
「だめだ!こっちへ来るな!」
駆け寄ろうとした私は足を止めた。
「リゼル……ここから出て行って……今すぐに……」
「レオ様……どうしたのですか……?」
「今日が満月だってことを忘れてた……」
膝をついて倒れ込んだレオ様のところへ駆け寄ると、レオ様は私の腕を掴んだ。
「リゼル……俺から離れて……俺はヴァンパイアなんだ……わかるでしょ?」
離れてと言いつつ、レオ様は私の腕をがっしりと掴んでいる。そして、愛しげに目を細めながら、長い指先で私の首筋をそっと撫でた。
「血が……欲しいのですか……?」
「違う……違うのに……!」
レオ様の行動は、言葉と合っていない。言葉では私を拒絶しているのに、レオ様はぐいぐいと私を引き寄せる。
「だめだ……このままじゃ、俺はリゼルを……」
私がレオ様のところへ来た理由は、ロールキャベツを作るためじゃない。レオ様の生贄になるためだ。
「私は、ここへ来る時に覚悟を決めて来ました。」
ここでの生活は、思ったよりもずっと楽しかった。レオ様と過ごした時間を思い出すと涙が溢れた。
「終わったら、ロールキャベツ……食べてくださいね?……たくさん作りましたから……」
レオ様の手を握ると、涙がぽつりと落ちた。すると──
「逃げる時間をやったのに。」
別人のような低い声に驚いて顔を上げると、レオ様の瞳は真っ赤に染まっていた。
「望み通り俺の物にしてやるよ。」
ロールキャベツを作って欲しいと言った優しい青年はここにはいない。でもこれでいい。
「これがレオ様の本当のお姿なんですね。」
レオ様の頬を撫でると、赤い瞳が少しだけ揺れた。
「俺を煽ったことを後悔しろ…………リゼル……」
耳元で囁く声が、すごく優しく聞こえたのは、気のせいだったかもしれない──
すぐ食べられるように、ロールキャベツの支度を整えたけれど、レオ様はいつまで待っても来ない。
(どうしたんだろう……)
なんだか胸騒ぎがする。エプロンを外してレオ様の部屋へ向かうと、お屋敷の廊下が明るく照らされていた。今日は満月。窓の外には大きな月が輝いている。
「綺麗……」
私は足を止めて月を見上げた。すると、廊下の奥から衣擦れの音と、わずかな息づかいが聞こえてきた。
目を凝らすと、レオ様が壁を伝ってふらふらと歩いている。
「レオ様!?」
「だめだ!こっちへ来るな!」
駆け寄ろうとした私は足を止めた。
「リゼル……ここから出て行って……今すぐに……」
「レオ様……どうしたのですか……?」
「今日が満月だってことを忘れてた……」
膝をついて倒れ込んだレオ様のところへ駆け寄ると、レオ様は私の腕を掴んだ。
「リゼル……俺から離れて……俺はヴァンパイアなんだ……わかるでしょ?」
離れてと言いつつ、レオ様は私の腕をがっしりと掴んでいる。そして、愛しげに目を細めながら、長い指先で私の首筋をそっと撫でた。
「血が……欲しいのですか……?」
「違う……違うのに……!」
レオ様の行動は、言葉と合っていない。言葉では私を拒絶しているのに、レオ様はぐいぐいと私を引き寄せる。
「だめだ……このままじゃ、俺はリゼルを……」
私がレオ様のところへ来た理由は、ロールキャベツを作るためじゃない。レオ様の生贄になるためだ。
「私は、ここへ来る時に覚悟を決めて来ました。」
ここでの生活は、思ったよりもずっと楽しかった。レオ様と過ごした時間を思い出すと涙が溢れた。
「終わったら、ロールキャベツ……食べてくださいね?……たくさん作りましたから……」
レオ様の手を握ると、涙がぽつりと落ちた。すると──
「逃げる時間をやったのに。」
別人のような低い声に驚いて顔を上げると、レオ様の瞳は真っ赤に染まっていた。
「望み通り俺の物にしてやるよ。」
ロールキャベツを作って欲しいと言った優しい青年はここにはいない。でもこれでいい。
「これがレオ様の本当のお姿なんですね。」
レオ様の頬を撫でると、赤い瞳が少しだけ揺れた。
「俺を煽ったことを後悔しろ…………リゼル……」
耳元で囁く声が、すごく優しく聞こえたのは、気のせいだったかもしれない──