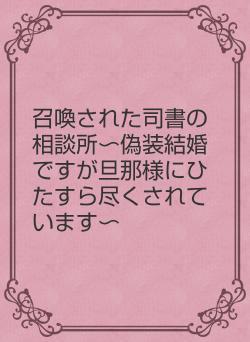私の帰還を知らせる号令が、謁見の間に響き渡る。それと共に、私は赤い絨毯の上を歩いていく。周りには、我がアルフェリオン王国の重鎮たちが立っているのだろう。視線は痛かったが、そのほとんどは厳しいものではなかった。
それは偏に、正面の玉座に座るお父様の存在が大きいのだろう。前を見据えると、お父様の頭には王冠が乗っていた。いつもお会いする時はしていない、国王としての姿だった。
「よくぞ、無事に戻ってきた」
「まるで戦にでも行っていたかのようなお言葉ですね。けれど……リュシアナ・アルフェリオン、ただいま戻りました」
私を避難させるために作り上げた名目もあったせいか、少しだけ皮肉を言いたかった。だが、そこはお父様。国王なだけあって、ビクともしていない。
「ある意味、似たようなものだろう。離宮へ向かう道中、何者かに狙われたと聞いたぞ」
「確かに襲われましたが、王宮に残っていた私の侍女と護衛騎士のお陰で怪我もなく、無事に着くことができました。どうか、私の侍女と護衛騎士に褒美を授けてください」
「いいだろう。それについては後ほど希望を聞くとしよう」
「ありがとうございます」
カイルがミサの分も含めて礼をした。私はその姿に安堵し、再び前を向き、お父様を見据える。
それは偏に、正面の玉座に座るお父様の存在が大きいのだろう。前を見据えると、お父様の頭には王冠が乗っていた。いつもお会いする時はしていない、国王としての姿だった。
「よくぞ、無事に戻ってきた」
「まるで戦にでも行っていたかのようなお言葉ですね。けれど……リュシアナ・アルフェリオン、ただいま戻りました」
私を避難させるために作り上げた名目もあったせいか、少しだけ皮肉を言いたかった。だが、そこはお父様。国王なだけあって、ビクともしていない。
「ある意味、似たようなものだろう。離宮へ向かう道中、何者かに狙われたと聞いたぞ」
「確かに襲われましたが、王宮に残っていた私の侍女と護衛騎士のお陰で怪我もなく、無事に着くことができました。どうか、私の侍女と護衛騎士に褒美を授けてください」
「いいだろう。それについては後ほど希望を聞くとしよう」
「ありがとうございます」
カイルがミサの分も含めて礼をした。私はその姿に安堵し、再び前を向き、お父様を見据える。