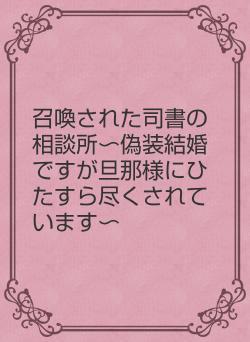「陛下から、無理強いはさせるな、との仰せですので、いくらでも待つつもりです」
「ということは、陛下も俺と同じ気持ちということか」
椅子に座る私の背後に立っているカイルが、ボソッと呟いた。
確かに処刑を見るのは怖い。この世界は、私がいた世界よりも古い時代のように感じるから、おそらく処刑といったら……ギロチンだろう。王族として、妹として見なければならない。
私に耐えられるかしら。
「私も含め、民たちは真実を我々に知らせてくれたのが、リュシアナ殿下だと知っています。クラリーチェ殿下の復讐に、我々が命を落とさずにいられたのも、リュシアナ殿下のお陰だとも。ですから、どうか王宮にお戻り願いたいのです」
「団長。さっき無理強いはさせるな、と陛下から言われたと」
「だが、戦争を食い止めてくださったのは、リュシアナ殿下だ。民たちはその姿を拝見したいと願っている」
「っ!」
民たちの期待……それに応えるのが、王族に生まれた者の責務。これからもリュシアナとして生きていくのなら、尚更、必要な覚悟である。
もう、お父様とお兄様に任せておくことができない立場と状況になりつつあった。
「ということは、陛下も俺と同じ気持ちということか」
椅子に座る私の背後に立っているカイルが、ボソッと呟いた。
確かに処刑を見るのは怖い。この世界は、私がいた世界よりも古い時代のように感じるから、おそらく処刑といったら……ギロチンだろう。王族として、妹として見なければならない。
私に耐えられるかしら。
「私も含め、民たちは真実を我々に知らせてくれたのが、リュシアナ殿下だと知っています。クラリーチェ殿下の復讐に、我々が命を落とさずにいられたのも、リュシアナ殿下のお陰だとも。ですから、どうか王宮にお戻り願いたいのです」
「団長。さっき無理強いはさせるな、と陛下から言われたと」
「だが、戦争を食い止めてくださったのは、リュシアナ殿下だ。民たちはその姿を拝見したいと願っている」
「っ!」
民たちの期待……それに応えるのが、王族に生まれた者の責務。これからもリュシアナとして生きていくのなら、尚更、必要な覚悟である。
もう、お父様とお兄様に任せておくことができない立場と状況になりつつあった。