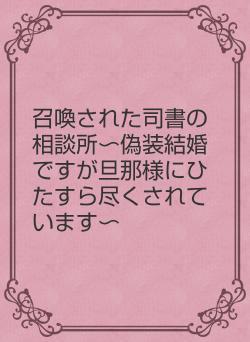タリアにとって私の占いは、十分説得力があったのか、早速婚約者に掛け合ってくれた。証拠となる手紙を、説得する材料として持たせたのも功を奏したらしい。手紙を返しに来てくれた時のタリアはとてもいい顔をしていた。
手紙の証人がタリアだけ、というのは弱いため、婚約者にも同じ責務を背負ってもらう魂胆があったのだが、そこは黙っておこう。あとはもう待つしかないのだ。この離宮で、国の行く末を。
「自信が戻りましたか?」
「え?」
私の代わりにタリアを見送りに行っていたカイルが、戻ってきて早々、そんなことを言ってきた。頑なに部屋の外どころか、ベッドの外さえも出させてくれないというのに。なんの話を言っているのだろうか。
「占いのことです。クラリーチェ殿下のことで、自信を失くされていたようでしたので」
「あぁ……そうね。タリアを見ていたら、王宮で占いをしていた時のことを思い出したの。皆に占って、感謝されて……ほとんどの人が初対面だったから、緊張の連続だったけど、とても楽しかったわ」
「……俺を占った時は?」
「え?」
「あ、いえ。失言でした」
いつもならグイグイくるのに、なぜか照れくさそうに口元を手で隠すカイル。思わずクスリと笑ってしまった。
手紙の証人がタリアだけ、というのは弱いため、婚約者にも同じ責務を背負ってもらう魂胆があったのだが、そこは黙っておこう。あとはもう待つしかないのだ。この離宮で、国の行く末を。
「自信が戻りましたか?」
「え?」
私の代わりにタリアを見送りに行っていたカイルが、戻ってきて早々、そんなことを言ってきた。頑なに部屋の外どころか、ベッドの外さえも出させてくれないというのに。なんの話を言っているのだろうか。
「占いのことです。クラリーチェ殿下のことで、自信を失くされていたようでしたので」
「あぁ……そうね。タリアを見ていたら、王宮で占いをしていた時のことを思い出したの。皆に占って、感謝されて……ほとんどの人が初対面だったから、緊張の連続だったけど、とても楽しかったわ」
「……俺を占った時は?」
「え?」
「あ、いえ。失言でした」
いつもならグイグイくるのに、なぜか照れくさそうに口元を手で隠すカイル。思わずクスリと笑ってしまった。