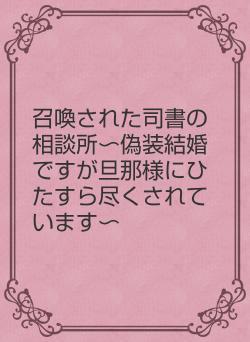「申し訳ありません。今はそれどころではなく……失礼します」
何が? と聞く暇もなく、カイルは扉を閉め、なぜか私の隣に腰を下ろした。途端、もの凄い勢いで馬車が走り出したのだ。思わず何かに掴まりたくて、咄嗟にカイルに抱きついた。背中に回る手のぬくもりに、場違いだと分かっているのに安堵してしまう。
「おそらく、これで撒ければ大丈夫でしょう」
「撒く? まだ刺客がいるの?」
「舌を噛みますから、黙って――……」
「それならカイルは?」
「俺は大丈夫です。慣れていますから」
不公平では? と思うものの、時折、さらに強く揺れるため、大人しくすることにした。カイルが傍にいること。こうしてぬくもりを感じていたい、という想いも強かったのかもしれない。
けれどカイルはその間、状況説明をしてくれた。おそらく私が不安に感じている、と思ったのだろう。その気遣いもまた、嬉しかった。
何が? と聞く暇もなく、カイルは扉を閉め、なぜか私の隣に腰を下ろした。途端、もの凄い勢いで馬車が走り出したのだ。思わず何かに掴まりたくて、咄嗟にカイルに抱きついた。背中に回る手のぬくもりに、場違いだと分かっているのに安堵してしまう。
「おそらく、これで撒ければ大丈夫でしょう」
「撒く? まだ刺客がいるの?」
「舌を噛みますから、黙って――……」
「それならカイルは?」
「俺は大丈夫です。慣れていますから」
不公平では? と思うものの、時折、さらに強く揺れるため、大人しくすることにした。カイルが傍にいること。こうしてぬくもりを感じていたい、という想いも強かったのかもしれない。
けれどカイルはその間、状況説明をしてくれた。おそらく私が不安に感じている、と思ったのだろう。その気遣いもまた、嬉しかった。