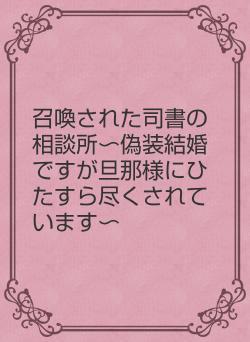そんな裏があったのか。当時、俺は六歳だったから、事件の詳細は発表されていることしか知らない。ユーリウス殿下は当然、知っているんだろうな。だからクラリーチェ殿下に対して、陛下ほど当たりが強かったのも頷ける。
クラリーチェ殿下の憎しみと怒りの矛先が、リュシアナ様に向くことを恐れたのだ。
「リュシアナが向かった離宮は、かつてオクタヴィアの保養地として使っていたところだ。長い間、行っていないが、常に当時のままの状態を維持させていたから、使用するのには不便はないだろう。使用人たちもいるし、警備も当時のまま置いている。だからリュシアナの警護は必要ない」
「し、しかし……」
リュシアナ様のお傍にいたい。まだお怒りかもしれないが、せめて近くで守らせてほしい。
「それでも行きたい、というのならば、ユーリウスでも近衛騎士団長でも使って、名目を作れ。私がリュシアナのためにできることは、離宮へ行かせることだけなのだ」
「……ありがとうございます」
「リュシアナなら、その手紙を活用してくれるかもしれないな」
最後の一言は、独り言かと思うほど小さな声だった。クラリーチェ殿下を止めてほしい。そんな願いのような想いを受けて、俺は陛下に一礼して執務室を後にした。
クラリーチェ殿下の憎しみと怒りの矛先が、リュシアナ様に向くことを恐れたのだ。
「リュシアナが向かった離宮は、かつてオクタヴィアの保養地として使っていたところだ。長い間、行っていないが、常に当時のままの状態を維持させていたから、使用するのには不便はないだろう。使用人たちもいるし、警備も当時のまま置いている。だからリュシアナの警護は必要ない」
「し、しかし……」
リュシアナ様のお傍にいたい。まだお怒りかもしれないが、せめて近くで守らせてほしい。
「それでも行きたい、というのならば、ユーリウスでも近衛騎士団長でも使って、名目を作れ。私がリュシアナのためにできることは、離宮へ行かせることだけなのだ」
「……ありがとうございます」
「リュシアナなら、その手紙を活用してくれるかもしれないな」
最後の一言は、独り言かと思うほど小さな声だった。クラリーチェ殿下を止めてほしい。そんな願いのような想いを受けて、俺は陛下に一礼して執務室を後にした。