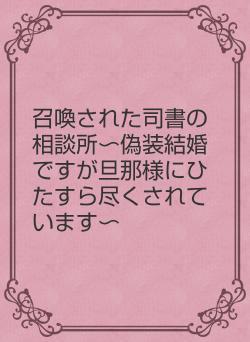「お、お父様。私は大丈夫です。だから二人を叱らないでください。それにベッドの上では失礼だと思い、このような形にしたいと言ったのは私なのです。だから……」
「リュシアナ……そなた、記憶がないと聞いたが……」
「はい。だからこそ、失礼に当たると思ったのです」
お父様にとっては娘との対面だけど、私にとっては初対面、しかも国王との謁見に等しい。
戸惑う私に、意外にもお父様は呆れるわけでもなく、柔らかい表情を向けてくれた。
「その他者を気遣うところは変わらないのだな。記憶を失ったことで、多少は我が儘になってもいいのだぞ?」
「えっと……」
「父上。リュシアナが困っていますよ。あと、いつまでも立たせていてよろしいのですか?」
「お、おぉ。そうであった。今からベッドに入れとは言わないが、無理をしてはならん。いいな」
「はい」
私は椅子に腰を下ろし、お父様の背後に立つ兄、ユーリウス・アルフェリオンに目を向けた。ミサの言う通り、王族特有のネイビーの髪と水色の瞳をしている。リュシアナと同じ亡き王妃の子どもということもあり、王太子なのだそうだ。
けれど私は、プラチナブロンドの髪にライラックグレーの瞳。王族特有の色は、何一つ持っていなかった。顔立ちも、お兄様とは似ていない。
「リュシアナ……そなた、記憶がないと聞いたが……」
「はい。だからこそ、失礼に当たると思ったのです」
お父様にとっては娘との対面だけど、私にとっては初対面、しかも国王との謁見に等しい。
戸惑う私に、意外にもお父様は呆れるわけでもなく、柔らかい表情を向けてくれた。
「その他者を気遣うところは変わらないのだな。記憶を失ったことで、多少は我が儘になってもいいのだぞ?」
「えっと……」
「父上。リュシアナが困っていますよ。あと、いつまでも立たせていてよろしいのですか?」
「お、おぉ。そうであった。今からベッドに入れとは言わないが、無理をしてはならん。いいな」
「はい」
私は椅子に腰を下ろし、お父様の背後に立つ兄、ユーリウス・アルフェリオンに目を向けた。ミサの言う通り、王族特有のネイビーの髪と水色の瞳をしている。リュシアナと同じ亡き王妃の子どもということもあり、王太子なのだそうだ。
けれど私は、プラチナブロンドの髪にライラックグレーの瞳。王族特有の色は、何一つ持っていなかった。顔立ちも、お兄様とは似ていない。