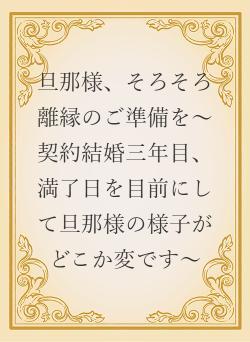「…………リ、ディ……?」
虚ろな瞳が、リディアの姿を捉える。
”リディ”――その呼びかけに、涙が込み上げた。
「ジェイド様……どうして、こんな馬鹿なこと……」
責める言葉を吐きつつも、心の中ではわかっていた。
ジェイドはこれほどの危険を犯してまで、リディの記憶を取り戻したかったのだ。
それほどまでに、彼は過去の自分を愛している――その事実が、どうしようもなく苦しかった。
ジェイドは、ぼろぼろと涙を零すリディアをぼんやりと瞳に映しながら、震える指で、リディアの手を握りしめる。
「……泣くな……リディ」
弱々しく呟いて、リディアに何かを握らせた。
手を開くと、そこにあるのは、青く輝く魔力石。
「……これ」
「ああ。……それが……最後の、一つ。……これで、君の、記憶……を……」
うわごとのように、ジェイドは続ける。
「……待たせて……悪かった」
「――っ」
――違う、と、リディアは首を振った。
待たされてなんていない。
だって、そんなことを考える暇がないくらい、ジェイドと過ごす日々は幸せだったから。
リディアの涙が、ジェイドの頬を濡らす。
「いつ、わたしがそんなことを頼みましたか。禁忌魔法の代償が、どれほどのものか知っていて、ジェイド様は、本当にこれでわたしが喜ぶとお思いなのですか?」