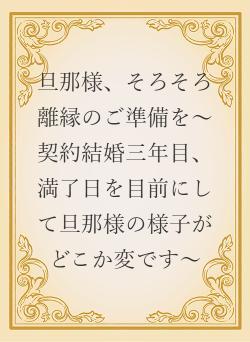「彼は素晴らしい青年だ。何より、お前を心から愛している。記憶を失ったお前のことを、誠心誠意支えてくれるであろうと分かっていた。お前のことを思うなら、婚約を認めるべきだということも。……だが、私は応じなかった」
その声は、後悔に満ちていた。
リディアは、尋ねる。
「どうして?」
すると、一拍置いて父は答えた。
「恐ろしかったのだ。きっとお前はもう一度彼を愛すだろう。だが彼は騎士だ。これから先、どれほどの危険に身を晒すことになるか分からない。もしそうなれば、お前は再び自身の命を投げ出して、彼を救おうとする。……それが、私には耐えられなかった」
「……っ」
父は、続ける。
「しかし、彼は引き下がらなかった。だから私は言ってしまったのだ。『ならば、一年以内にリディアの記憶を取り戻して見せろ。それができたら、婚約を認めてやる』と」
それは無理難題だった。
リディアの記憶が失われたのは禁忌魔法の代償だ。取り戻せるはずがない。
けれど、ジェイドはこの半年間、ずっとリディアの側にいた。
それは、つまり……。
「ジェイド様は、それを受け入れたと?」
「そうだ。彼は私に、お前の記憶を取り戻すと約束した。その代わり、お前の時間を一年くれと」
「……!」
窓の外を見つめていた父が、ゆっくりとリディアを振り返る。
「リディア。お前には、彼の言葉の意味が分かるか?」