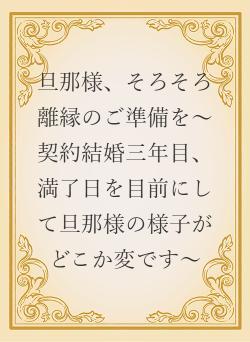夏が過ぎて秋になると、ジェイドは毎日、剣を奮うようになった。
昼間はリディアと過ごし、夕方から夜にかけて、リディアの屋敷の庭園の隅で、黙々と素振りをする。
そんなジェイドの様子を眺めるのが、リディアの新しい日課になった。
澄んだ空気に、金色の葉が舞う。
ジェイドの剣が空を裂くたび、耳に届くその音が、どうしようもなく、懐かしく思えた。
「……氷の上を、滑ってるみたい」
不意に呟くと、ジェイドが手を止める。
「今、何と言った?」
「え、っと……、ジェイド様の剣の音が、氷を滑るみたいで綺麗だな、と。すみません、おかしなことを」
真顔になったジェイドを見て、リディアは慌てて言葉を濁す。
すると、ジェイドはすぐに頬を緩めた。
「違うんだ。昔、同じことを言われたな、と、思い出しただけで」
「今の、わたしと同じことをですか?」
「ああ。ちょっと……驚いた」
その声は、必死に寂しさを隠しているようだった。
リディアはその横顔から、その相手がジェイドの大切な人だったことを悟り、ほんの少し、胸が痛んだ。
それからも二人は、毎日のように共に過ごした。
秋が終わり、冬が訪れる頃には、リディアにとってジェイドは、なくてはならない存在となっていた。