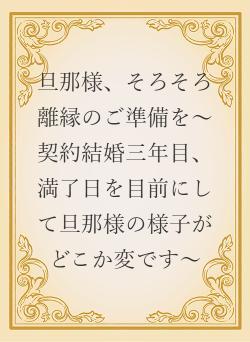夏の終わりには、バスケットにサンドイッチを詰めて、川辺でピクニックをした。
その頃には、もうすっかり、お互い気兼ねなく話せる仲になっていた。まるで、本当の"兄妹"のように。
「君の御父上に聞いたんだ。君が記憶を失う前、夏は毎年ここでピクニックをしていたって」
「まぁ、そうなのですか?」
「子供の頃は、ドレスから水が滴るくらいはしゃぎ回って、目が離せなかったと言ってたな。随分なお転婆娘だ」
「……! 父がそう言ったのですか?」
いくらジェイドが護衛だからって、異性にそんなことを話すだなんて有り得ない。
帰ったら文句の一つでも言ってやらなければ――父への不満を分かりやすく顔に出すリディアを、ジェイドは温かな目で見つめる。
「リディア、せっかくだ。川に入ってみないか?」
「えっ、でも」
「大丈夫だ。ここには、俺たちを叱る大人は誰もいない」
「そう言うジェイド様こそ、もう立派な大人だと思いますけど」
「いいじゃないか。大人になっても遊んだって」
あっと言う間に裸足になり、ざぶざぶと川に入って行くジェイドを追って、リディアも水に足を入れる。
瞬間、冷やりとした感覚が全身に広がった。
「……気持ちいい」
「だろう? ほら、もっとこっちへ。奥には魚もいるんだ」
ジェイドが手を差し出してくる。
リディアは、左手でドレスの裾を持ち上げながら、右手をそっと重ねた。
すると次の瞬間、不思議な既視感に襲われ、足を止める。
「リディア、どうした?」
「いえ……、何でも」
(今の、何かしら。一瞬、とても懐かしく思えたような……。気のせいかしら?)
リディアは違和感を覚えたが、本当に一瞬のことだったため、すぐに忘れて川遊びを楽しんだ。