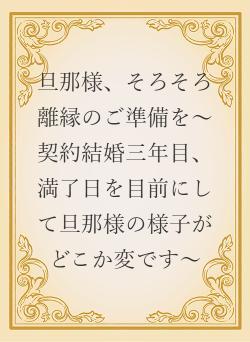半年前――リディアがある朝目覚めると、十年分の記憶がごっそり抜け落ちていた。
記憶は七つで止まっているのに、鏡の中には十七歳の自分がいて、リディアは恐ろしさのあまり何度も取り乱し、泣き喚いた。
そんな彼女を、周りは懸命に支えてくれた。
けれど、どうして自分がこんなことになっているのか、その原因だけは、誰も教えてくれなかった。
せめてもの救いは、"リディアの身体"が、生活様式を記憶してくれていたことだろう。
食事のマナーも、美しいお辞儀の仕方やダンスのステップ、刺繍の刺し方、喋り方に至るまで、忘れてはいなかった。
両親や友人たちと過ごした大切な記憶が消えてしまったこと以外は、全て覚えている。
――それでも。
リディアの中にはずっと、奇妙な空虚が漂っていた。
失ってしまった記憶のせいだろうか。
胸の奥にぽっかりと穴が空いたような寂しさが、いつも、リディアの心につき纏っていた。
(誰かを、探しているような気がするの)
この半年間、繰り返し見る夢。
花咲き乱れる丘の向こうで、自分の名前を優しく呼ぶ声。
風に揺れる柔らかな髪。
自分だけを見つめる、真っすぐな眼差し――。
けれど、そこに手を伸ばした瞬間、夢は終わってしまうのだ。
(あれは、いったい誰なのかしら)
そんな思いを抱えながら、リディアは、この半年を過ごしてきた。