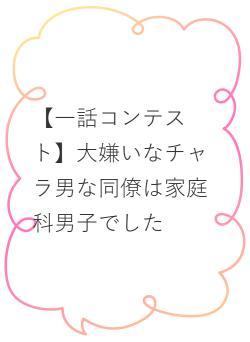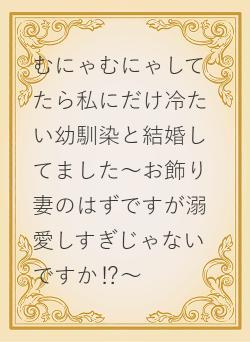『しかもこの恋愛映画、キスシーンがあるんだって』
「────はぁーーーーーー……」
学校から帰るなりにリビングの机に突っ伏した私の次第なため息が響く。
今日は春馬は授業後すぐに件《くだん》の映画の撮影の為、マネージャーさんの迎えの車で現場へと直行していった。
つかささんは夜遅くなるからご飯はいらないって言ってたし、そろそろ帰ってくるとしたら私達とは別の高校に通っている葵君、かな?
そんなことを考えてすぐだった。
かちゃりとリビングの扉が開かれて、先程考えていた葵君本人が入って来た。
「あ、おかえりなさい。葵君」
私が気づいて声をかけると、葵君はふんわりと柔らかい笑みを浮かべ「ただいま」と返してくれた。
あー、癒しだ。
さすがは微笑みの貴公子。
「ふふ」
「ん? 何?」
突然くすくすと笑い始めた葵君に首をかしげると、葵君は優しい笑みを浮かべたまま言った。
「帰ってきた時『おかえり』って言ってもらえるって、やっぱりいいね」
そう言ってリビングのソファにゆったりと腰かけると、早速葵君は手帳を開いてスケジュールの確認を始めた。
「明日は4人とも朝から歌撮りで、春馬はその後映画の撮影か……。これからもっと忙しくなるんだろうな」
映画の撮影と聞いて胸がぎゅんと締め付けれられる。
すぐに始まっているそれの存在を知ったのは今日だというのだから、疎いにもほどがある。
私がうだうだと毎日を生きている瞬間にも、春馬はずっと努力を重ねていたんだよね。
「食事後もすぐ部屋で大本読んだりしてるみたいだし、他の仕事も完ぺきにこなそうとしてるし……。すごいよね、春馬って」
感心したようにそう言う葵君に、私はただ黙ってうなずいた。
小学校の夏休みの研究でひたすら自分が納得するまで実験や調査を繰り返したり、苦手だった水泳を毎日プールに通って練習して、クラスの誰よりも泳げるようになった春馬を思い出す。
誰よりも真面目でストイックで、半端なことが大嫌いなのは昔から変わっていない。
だけど、少しは周りに頼ってくれてもいいのに。
相談してくれたらいいのに。
甘えてくれたらいいのに。
それができないくらい、周りは────私は、春馬にとってだ寄り無いのだろうか。
なんて、時々感じてしまう。
「……? 弥生ちゃ──」
「おーおー、青春してんねー」
「!?」
葵君が何か言いかけると同時に、静かな空間に明るい声が響き渡った。
「英二さん!! おかえりなさい。お疲れ様です」
いつの間にか仕事から帰って来た英二さんに私が言うと、英二さんは人懐こい笑顔で「ただいまー」と返しながらソファへと顔面ダイブした。
「英二、お疲れ」
「おうっ!! センキュー!! っていうか、さっきのちょーっと盗み聞きしてたんだけどさ」
悪びれることなく英二さんが続ける。
「もしかして、春馬が周りを頼ったり甘えてくれなくて悩んでたり、する?」
「!!」
何で分かるの!?
エスパー!?
そんな心の声が顔に出ていたのか、葵君が苦笑いして、英二さんが「やっぱり」と笑った。
「あいつ素直じゃないからさ。ぐいぐい強制的に甘えさせるのが一番じゃね?」
「強制的に……」
「そ。強制的に」
そう言うと英二さんは、不気味なほどに満面の笑みを浮かべて、持って帰った紙袋からソレを取り出した──……。