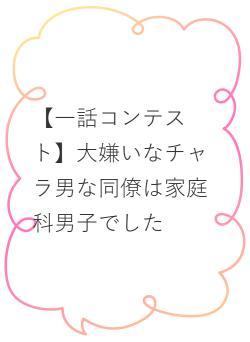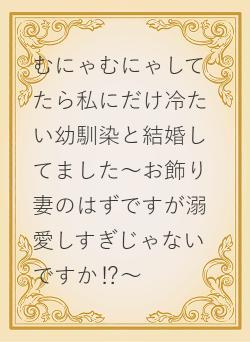昨夜つかささんたちにお別れ会を開いてもらったすぐ後に、お父さんが春馬のお父さんと一緒に私を迎えに来た。
春馬のお父さんは、これからも春馬をよろしくね、なんて言ってくれたけれど、きっともう話すことはないだろうと思う。
シェアハウスにお世話になる前の、疎遠状態に戻るだけ。
私は変わりのない日々が続いて、春馬はもっともっと忙しくなる。
「──弥生、おはよ!!」
「おはよ、梓」
「今日はツッキーと一緒じゃないんだね?」
なんだかすっかりセットになってしまったようで申し訳ないけれど、これからはもう一緒に登校することはない。
複雑な顔をして梓にそう伝えようとした、その時だった。
バンッ────「弥生!!!」
教室の扉が勢いよく開かれて、低く少しだけ焦ったような声が私の名を呼んだ。
それと同時に女子の黄色い声が飛ぶ。
こんな事態になるのは、一人しかいない。
「……春馬…………」
まさか教室に来るだなんて一ミリも思わなかった。
その表情からは何も見えてこない。
私が何も言わずに家を出ていったことへの怒りも、悲しみも、驚きも、何も。
すると春馬はずんずんと私の方まで長い足を進めると、その大きな手で私の手を取った。
「行くぞ」
「へ!? え、ちょ、ちょっとー!?」
その手を引かれるがままに、私はざわめきと悲鳴入り混じる教室を後にした。