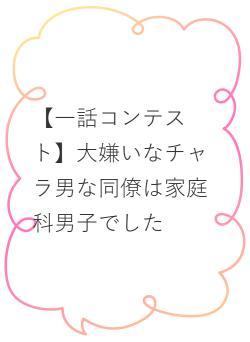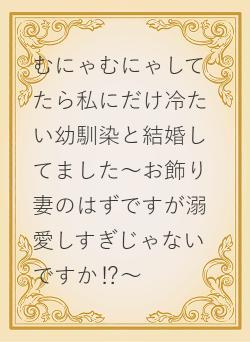俺の心は久しぶりに晴れていた。
ずっと引っ掛かっていたシーンに、ついにOKが出たのだ。
人生初の映画主演。
人生初のキスシーン。
リアルでもまだ経験がない俺は、そのシーンを撮る日をずっと緊張しながら待っていた。
そして初めてキスシーンの撮影日、何度もNGを出した末、その日の撮影は中止になった。
彼女への思いが無い。
リアルが足りない。
そんな指摘が入って、俺のせいで皆の時間を無駄にしてしまった。
『好きな相手とのキスを思い出してみればいい』
監督からはそうアドバイスをされたが、好きな相手とキスなんてしたことがないんだから思い出しようもない。
幼稚園の頃からずっと好きだった幼馴染の弥生。
高校に入って俺がアイドル業を始めるまではずっとそばにいた彼女が、父親の会社の倒産と蒸発がきっかけでこのシェアハウスに同居するようになってからしばらくが経った。
好きな女との同居生活。
何の拷問だ。
最初はそう思ったけれど、また弥生と離せるようになるきっかけになったことは確かで……。
あの日も、つい思いが溢れてしまった。
キスシーンの練習という名目で重ねた唇は、少しだけ震えていたように思う。
触れるだけのキスの後、俺はバクバクとうるさい胸を鎮めようと冷静を装って再び台本に目を移したが、あの時のことはものすごく後悔している。
告白のチャンスだったんじゃないか、と。
もっと気遣ってやることもできたんじゃないか、と。
今日の撮影が終わったら、あらためて弥生に伝えよう。
ずっと、胸に抱いていた気持ちを。
そう思っていたのに──。
「ただいま」
夜になって帰ってみると、いつもパタパタと玄関まで迎え出てくれる弥生の姿がない。
リビングに行ってみると、英二とつか兄がソファで休みながらテレビを見て、葵が宿題をしているところだった。
そこにも弥生の姿はない。
「お、春馬、お疲れー」
英二が俺に気づいて声をかける。
「おかえり春馬」
「ん。ただいま、つか兄。……弥生は?」
すぐに弥生について尋ねると、3人の空気が少しだけ変わったのを感じた。
そしてつか兄がゆっくりと口を開いた。
「弥生ちゃんなら、お父さんの会社の方がなんとかなったみたいで、さっきお父さんが迎えに来て家に帰ったよ。夕食前にお別れ会も済ませて、な」
「え……?」
突然告げられたそれに、時が止まったように感じられた。
そりゃ、おじさんが帰ってきて落ち着いたなら家に帰るだろうことぐらいわかっていた。
だけどこんな突然、それも俺に何も言わずにいなくなるだなんて、想像もしていなかった。
「お別れ会って……何で俺に何も──」
「弥生ちゃんが春馬には知らせないでって」
俺の言葉を遮って、葵が淡々と続ける。
「春馬さ、弥生ちゃんにちゃんと自分の気持ちとか伝えてる?」
「!!」
「ここのところ、弥生ちゃんずっと辛そうにしてたの、気づいてた?」
弥生が?
辛そうに、していた?
上手く言葉が出てこない俺に、今度はつか兄が言葉を繋げた。
「何か悩んでるふうでも、それ以上に切羽詰まった表情してたやつの為に色々頑張ってたんだよ、あの子は」
「!!」
そうだ。
最近は自分のことでいっぱいいっぱいで、弥生のことをちゃんと見ることが出来ていなかった。
なのにあいつは、俺のためにマフィンを焼いてくれたり、ずっと気にしていてくれた──。
「あの子だろ? お前がずっと好きで、でもアイドル業を始めてから距離が出来たって言ってた相手って」
「っ……」
前に一度、メンバーといわゆる恋愛の話になった時にぽろりと溢した話。
名前こそ出していなかったが、弥生のことを話した記憶がある。
「つか兄、気づいて──?」
「まぁ、一応最年長だからな。そうだって確信したからこそ、俺はあの子がここに住むのを賛成したんだ」
じゃなきゃもっと慎重に考える、と苦笑いするつか兄に、開いた口が塞がらない。
「俺も。春馬の反応が他の女子に対する反応と全然違ったから、すぐ気づいたよ」
葵もつか兄に同意する。
俺の反応ってそんなに分かりやすかったか……?
「俺も俺もー!!」
「いやお前は違うだろ」
英二はただ面白そうだから同意しただけだろうが、少なくとも二人に最初から気づかれていたという事実に何を返したらいいのかもうわからない。
そんな俺に、つか兄が優しく目を見て言った。
「大切なものは、ちゃんと口にしないと伝わらねぇよ。うちの事務所のモットー、忘れたわけじゃないだろ?」
「っ……」
あぁ、そうだ。
何をもたもたとしていたんだろう、俺は。
大切ならもっと言葉にすればよかった。
傍にいたいなら、その手を握って離さなければよかった。
「……ありがとう、皆」
そして俺は、顔を上げた。
もう間違わない。
そう、心に決めて。