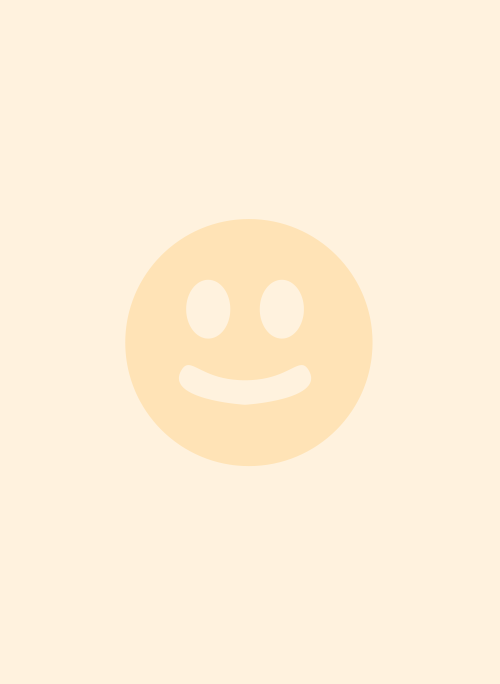リナはまだ、その名前を声に出して言えなかった。
「聖フィリア音楽院」──その響きが、自分にはまぶしすぎたから。
でも、夜のノートにだけは何度も書いた。
そのたび、胸が鳴った。
どこか遠くで潮が引いていくように、静かで確かな鼓動があった。
オーディションの日まで、あと3か月。
彼女はまだピアノを持っていない。
譜読みもできない。
でも──音を感じる力なら、誰にも負けないと思った。
最初にやったのは、学校の音楽室に通うことだった。
昼休み、放課後、誰もいない時間を見つけては、そっとピアノに触れた。
最初はただ、鍵盤に手を置くだけだった。
でも、白鍵の冷たさも、音の重なりも、彼女にとっては“風景”だった。
ひとつひとつの音が、風の粒のように立ちのぼっていく。
耳で聴くよりも、心で感じる。
目で読むよりも、音の流れを身体でなぞる。
誰かの真似じゃなく、自分の耳で曲を辿っていく。
ある日、音楽の先生に声をかけられた。
「凪咲さん、何か曲、練習してるの?」
リナは一瞬、言葉をなくした。
でも、ポケットからスケッチブックを出して、ページを見せた。
「これは……君が書いたの?」
先生は驚いたように目を見開いた。
そのページには、メロディでも楽譜でもない、言葉の断片と簡単な音符が並んでいた。
“光が跳ねる音”
“道の先にある音”
“この心臓が鳴ってる音”
「音って……描けるんですね」
リナの声は、小さく震えていた。
先生はしばらく沈黙したあと、こう言った。
「あなたは、音のことばかり考えてるのね」
「それが、音楽のはじまりだと思うわ」
その日、リナは初めて、自分が“音楽の側”に立ってもいいのかもしれないと思った。