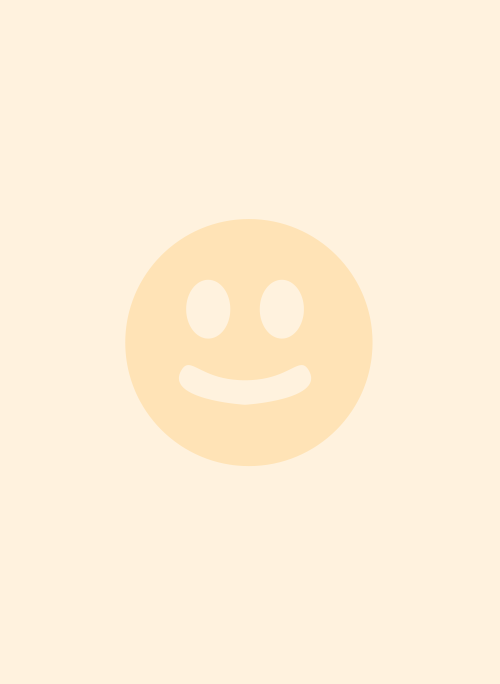「音を見つけてごらん」
ある日、椿木響也はリナに小さなスケッチブックを差し出した。
中は真っ白だった。まるで、まだ誰も知らない音が眠っているように。
「音って……描けるの?」
リナの問いに、響也は軽くうなずいた。
「音は、誰のそばにもあるよ。
でも、目をこらして耳を澄まさないと、すぐにどこかへ行ってしまう。
“聞く”んじゃなくて、“聴く”んだ。
君だけの言葉で、それを残してごらん」
その日から、リナはスケッチブックを持ち歩くようになった。
朝の波の引く音──ザザッ
商店街でパンの蒸気が抜ける音──プシュー
学校の帰り道、誰かが落とした笑い声──コロン
彼女の耳は少しずつ、世界の形を変えていった。
誰かが見過ごした音が、リナには色を持って見えた。
それは、五線譜にはのらない小さな旋律だった。
でも──
家の中だけは、音が多すぎた。
母の声。父の舌打ち。テレビのバラエティ番組の笑い声。
それをかき消すように兄が流すBGM。
部屋にいると、音はただの「ノイズ」になっていった。
リナは、窓を開けた。
風の音だけが、優しかった。誰の感情も乗せず、ただリナのそばにいてくれた。
スケッチブックのページは少しずつ埋まっていく。
言葉、線、時々メロディのかけら。
それは誰に見せるわけでもない、彼女だけの“音の地図”だった。
「“空をなでた音”…」
「“夕焼けがピアノみたいに光った”…」
リナの手書きの文字を見て、響也は静かに目を細めた。
「いい耳してる。君の中には、まだ誰も知らない旋律があるよ」
でもリナは、自分が音楽をやっていい人間なのか、わからなかった。
ピアノも習ってない。
楽譜も読めない。
家では音楽の話なんてできない。
そしてなにより──才能なんて、ない。
……そう思っていた。
けれど。
海辺で聴いたあの旋律。
空が音をまとった瞬間。
心がふるえた“なにか”だけは、本物だった。
「好き」が生まれる音が、自分の中にあった。
だから、もう少しだけ、この“風の道”を歩いてみたいと思った。