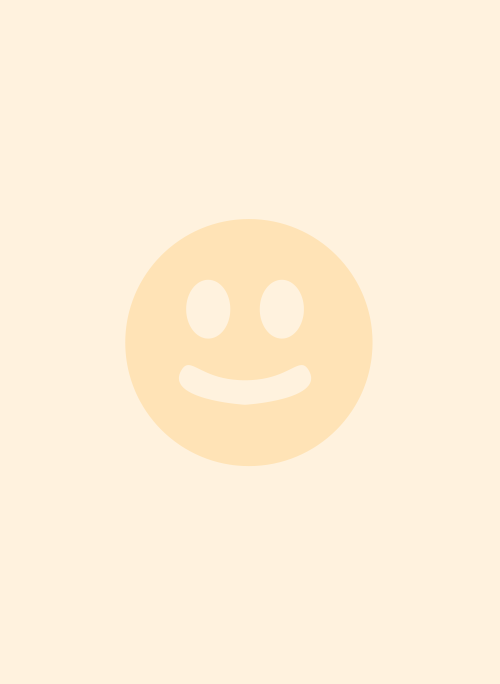リナが“音”と出会ったのは、10歳の夏だった。
海辺の町・小曽根。
波の音が毎日、目を覚まさせる。
潮の匂いの混じった風が、朝の光をすり抜けて、彼女の髪を揺らす。
音楽は、遠い世界のものだった。
母は「音楽なんて遊びよ」と言い、
父はテレビの音量を上げることで、沈黙を守っていた。
兄だけが、リナの話をうんうんと頷きながら聞いてくれる人だった。
そんな毎日の中で、リナはいつも窓を少しだけ開けていた。
理由はわからなかった。ただ、そのすきまから吹く風だけが、
自分を「誰か」として認めてくれてるような気がしたから。
そして、その風に“音”が乗ってきたのは、ある夕方のこと。
図書館の前の広場で──
1台のピアノが音を奏でていた。
風に運ばれてきた旋律は、やわらかくて、まっすぐで、どこにも所属しない音だった。
言葉じゃない。
楽譜でもない。
でも、胸の奥が熱くなって、目が覚めるような気がした。
リナは音に導かれるようにピアノへ近づいた。
そこにいたのが、椿木響也という青年だった。
彼は誰に語りかけるでもなく、静かに鍵盤をなぞっていた。
それはまるで、風と話しているようだった。
演奏が終わったあと、リナは勇気を出して声をかけた。
「……今の曲、なに?」
「曲? なんだろうね」
響也は少し笑って、空を見上げた。
「今そこにいた鳥の羽音と、君の足音と、風の強さでできたやつ」
リナは意味がよくわからなかった。でも、心はなぜか納得していた。
その日から、世界は“音”で満ちていた。